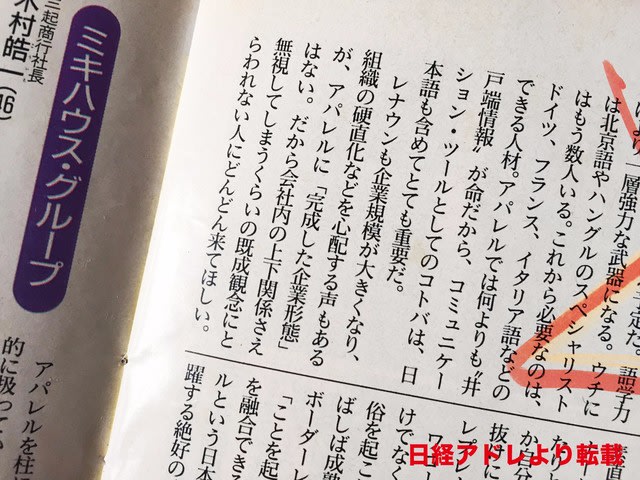アパレルの余剰在庫をどうするか。これまでは焼却処分や素材のリサイクルがメーンだったが、ここに来て在庫を引き取って、格安でリセールするオフプライスショップが増えている。先日、ついにそのオンライン版が登場した。
長崎県諫早市の法人在庫リユース業「PINCH HITTER JAPAN(ピンチヒッタージャパン)」 がその一つ。地元紙によると、「同社のオンラインショップ「LAST SALE(ラストセール)」は、国内アパレルが抱える余剰在庫を一括で買い取り、定価(メーカー希望小売価格)の60~90%オフで販売する」という。https://news.yahoo.co.jp/articles/8aaacf6cf8d2d5650a2f56b143e39ee6d91d6561
オンラインは実店舗のように立地に左右されない。地方なら在庫を保管する倉庫の家賃負担は軽く、販売用に仕分けする人件費も首都圏より安い。ローカル企業としては、コスト競争力で優位に立てるとの目算なのだろう。果たして勝算はあるのか。報道された情報をもとに考えてみたい。
報道に反してアパレル扱いは無し
ピンチヒッタージャパンは、創業が2013年の若い企業だ。スポーツ用品や自転車、工具、ゲーム、楽器などの買い取り専門サイトで急成長し、昨年3月期の取扱高は約58億円に及ぶ。そのサイトを売却して、「アパレルのオフプライスショップに乗り出す」というのだ。スポーツ用品などで蓄積した買取&再販のノウハウを生かすようだが、それがアパレルにどこまで通用するかは未知数である。
と言うのも、アパレルメーカーが余剰在庫を放出するのは、シーズンや型番、サイズ、色ですべてごちゃ混ぜになっているケース(バッタ屋ルート)がほとんど。そうした商品はセールやアウトレットでも消化できず倉庫にストックしておくと家賃負担がかかるとか、何年も在庫のままで市場に出回らなかったデッドストックなどになる。だから、基本的に引き取る側が商品を選ぶことはできない。

地元紙の報道では、「リーガルやティンバーランドなど人気ブランドの衣類(男性、女性、子ども向け)、腕時計などの小物、靴を定価より6割安く販売。一定期間が経過し売れ残った商品は9割安で売る。いずれも新品未使用」と、なっている。しかし、ラストセールのサイト(https://lastsale.shop/ )を見る限り、6月23日時点で品揃えはほぼ100%が「靴」で、報道されているような国内アパレル(衣料)は一つもない。
記事を書いた長崎新聞社の記者は、「日本の衣類廃棄量は年約100万トンで、半数以上は焼却処分され、温室効果ガス排出量増の原因の一つといわれる。国内アパレル企業が抱える在庫を一括買い取りすることで、在庫商品のキャッシュ化と衣類廃棄の削減につなげる」と、業界の課題や事業参入の背景にも触れている。だが、現状では品揃えと記事の文脈がシンクロしないわけだから、衣料廃棄に貢献したい企業姿勢もオフプライスストアの目的もかすんでしまう。
ピンチヒッターに問い合わせると、スタッフの名前入りで「現在はシューズと腕時計を掲載しておりますが、今後は衣類品も掲載してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」との回答が返ってきたが、それ以外の説明はなかった。ローカル紙が地元企業をクローズアップしたい気持ちはわかる。でも、記事内容があまりに先走りでは、「飛ばし」と言われかねない。取材した記者はせめてアパレルを販売するだいたいの時期くらいは、同社から聞き出して書くべきではなかったかと思う。
どのアパレルから、何を引き取るか
今後、LAST SALEにはどんなブランドが品揃えされるかだが、アパレルの「仕入れ」はそう簡単ではない。欧米のラグジュアリーブランドは、プロパー、セール、アウトレットとバーチカルに消化して、残ったものはブランドイメージを毀損しないように焼却処分される。海外卸しを経由した一部が二次流通に出回るケースはなくはないが、商品自体が「ニセ物」であったり、インボイスが偽造されていることもある。買い付けノウハウが6〜7年程度では、真贋を確かめて仕入れるのは難しいだろう。


ピンチヒッターのHPによると、スポーツ用品や自転車、工具、ゲーム、楽器などのメーカーや問屋に対し、まとまった余剰在庫を一括で買い取る旨が記されている。アパレルについてもこの基本スタイルを貫くなら、メーカーが依頼するのは、やはりシーズンや型、サイズ、色がごちゃ混ぜになったパッキン単位が多くなるのではないか。これらを引き取るなら価格は安いだろうが、それが売れるかどうかは別の話だ。
さらに細かく言えば、百貨店系ブランドは最近は製造調達を抑えているため、まとまった在庫が手に入れることはできない。SPAの放出品は色やサイズが揃うが、他社も続々と参入していること考えると、在庫が十分にあって引き取ることができるかどうか。他は量販店ルートの売れ残りやスポーツブランドなどがあるが、どこまで中身が充実(再販に堪えうるかどうか)しているかはわからない。

ショッピングサイトでは、靴については男性、女性、子どもごとの種類別に分けられ、サイズ別でもしっかりグルーピングされている。トップページでは「全商品1点モノ」「『下記、サイズから探す』からの商品検索をおススメしております」とある。試着にせずにネットで靴を買うのなら、そうせざるを得ないからか。ただ、アパレルは引き取りの形態を考えると、価値のあるブランドでない限り、1点ものというわけにはいかない。
引き取ったパッキン単位の中身を、男性、女性、子どもはもちろん、ブランドやシーズン別で仕分けするには相当の手間がかかり、その分のコストは某大になる。仮にマニュアルに添ってパートアルバイトが作業するにしても、シーズンやテイストまで分けるには、ある程度の商品知識やファッションセンスが要求される。そうしたノウハウを修得するには、かなりの時間を要するだろう。メディア発表されたにも関わらず、サイトにアパレルが一つもないのは、そうした理由もあるのかと、逆に勘ぐってしまう。
作業は仕分けだけに止まらない。サイトに商品をアップする「ささげ業務」がある。パッキン単位の引き取りなら、自社で撮影からアイテム名、スペック、詳細説明の記載までの作業をしなければならない。すでに靴ではしっかり写真や情報がアップされているので、ノウハウはもっているだろうが、ファッションアイテムはイメージも重要だから、置撮りだけでなくモデル撮影まで行うとさらに手間やコストがかかる。
売れるにはブランドの顔ぶれがカギ
オンラインショップの現状を考えると、単に「安い」だけでは買い上げ率を高めるのは難しいと思う。売れるには「ブランドの顔ぶれ」がカギを握るし、サイトのビジュアルや商品説明も重要だ。ECは試着ができないので、FAQ以外の問い合わせ対応、返品受付ときめ細かなサービスが顧客の信頼を生む。検索エンジンの上位にランキングされるためのSEO投資はもちろんだ。一つ一つクリアしていかなければならない。
すでに実店舗ではワールドの「アンドブリッジ」、ドンキホーテの「オフプラ」、GEOクリアの「ラックラック・クリアランスマーケット」などが参入し、多店舗化を視野に入れて展開中だ。ただ、ワールドが関わっている店舗でも、ハンギングを主体のローコストオペレーションだ。商品が未使用品というだけで、VMDや陳列方法は中古品を売る2nd Streetとほとんど変わらない。
某大な仕分け作業が発生するため、商品のピックアップも試着もセルフ化するなど運営コストを抑制しなければ、利益が出ないのだ。それでも、実店舗のみならECサイトのようなささげ業務は無くなる。逆にオンラインショップは仕分け作業の他にこの作業が必要で売価が安いと、利益は薄い。損益分岐点との格闘が待っているわけだ。ラストセールは最終的には90%オフで売り切るというが、完全消化はそれほど容易ではない。それを考えると、他の引き取り商品も含めて、第三国への三次流通まで視野に入れているのかもしれない。
2018年のデータでは、日本では年間に供給されるアパレルは29億点を超える。それに対し、総消費数量はプロパー、セール、古着をすべて合算しても13億5200万点ほど。つまり、半分以上が売れ残っているわけだ。世界的なSDGs意識の高まりや焼却処分によるCO2排出の抑制からも、オフプライス業態は注目されている。ビジネス、社会性の両面から参入する企業があるのは良い傾向である。
さらに新型コロナウイルスの感染拡大で、東京一極集中のリスクが顕在化した。すでにビジネスの仕組みを変えようという動きがあり、都市構造が変化すればローカル企業にもチャンスの芽が出て来る。ラストセールにアパレルが品揃えされるのを期待しながら、オフプライスショップのオンライン版を注視して見ていきたい。
長崎県諫早市の法人在庫リユース業「PINCH HITTER JAPAN(ピンチヒッタージャパン)」 がその一つ。地元紙によると、「同社のオンラインショップ「LAST SALE(ラストセール)」は、国内アパレルが抱える余剰在庫を一括で買い取り、定価(メーカー希望小売価格)の60~90%オフで販売する」という。https://news.yahoo.co.jp/articles/8aaacf6cf8d2d5650a2f56b143e39ee6d91d6561
オンラインは実店舗のように立地に左右されない。地方なら在庫を保管する倉庫の家賃負担は軽く、販売用に仕分けする人件費も首都圏より安い。ローカル企業としては、コスト競争力で優位に立てるとの目算なのだろう。果たして勝算はあるのか。報道された情報をもとに考えてみたい。
報道に反してアパレル扱いは無し
ピンチヒッタージャパンは、創業が2013年の若い企業だ。スポーツ用品や自転車、工具、ゲーム、楽器などの買い取り専門サイトで急成長し、昨年3月期の取扱高は約58億円に及ぶ。そのサイトを売却して、「アパレルのオフプライスショップに乗り出す」というのだ。スポーツ用品などで蓄積した買取&再販のノウハウを生かすようだが、それがアパレルにどこまで通用するかは未知数である。
と言うのも、アパレルメーカーが余剰在庫を放出するのは、シーズンや型番、サイズ、色ですべてごちゃ混ぜになっているケース(バッタ屋ルート)がほとんど。そうした商品はセールやアウトレットでも消化できず倉庫にストックしておくと家賃負担がかかるとか、何年も在庫のままで市場に出回らなかったデッドストックなどになる。だから、基本的に引き取る側が商品を選ぶことはできない。

地元紙の報道では、「リーガルやティンバーランドなど人気ブランドの衣類(男性、女性、子ども向け)、腕時計などの小物、靴を定価より6割安く販売。一定期間が経過し売れ残った商品は9割安で売る。いずれも新品未使用」と、なっている。しかし、ラストセールのサイト(https://lastsale.shop/ )を見る限り、6月23日時点で品揃えはほぼ100%が「靴」で、報道されているような国内アパレル(衣料)は一つもない。
記事を書いた長崎新聞社の記者は、「日本の衣類廃棄量は年約100万トンで、半数以上は焼却処分され、温室効果ガス排出量増の原因の一つといわれる。国内アパレル企業が抱える在庫を一括買い取りすることで、在庫商品のキャッシュ化と衣類廃棄の削減につなげる」と、業界の課題や事業参入の背景にも触れている。だが、現状では品揃えと記事の文脈がシンクロしないわけだから、衣料廃棄に貢献したい企業姿勢もオフプライスストアの目的もかすんでしまう。
ピンチヒッターに問い合わせると、スタッフの名前入りで「現在はシューズと腕時計を掲載しておりますが、今後は衣類品も掲載してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」との回答が返ってきたが、それ以外の説明はなかった。ローカル紙が地元企業をクローズアップしたい気持ちはわかる。でも、記事内容があまりに先走りでは、「飛ばし」と言われかねない。取材した記者はせめてアパレルを販売するだいたいの時期くらいは、同社から聞き出して書くべきではなかったかと思う。
どのアパレルから、何を引き取るか
今後、LAST SALEにはどんなブランドが品揃えされるかだが、アパレルの「仕入れ」はそう簡単ではない。欧米のラグジュアリーブランドは、プロパー、セール、アウトレットとバーチカルに消化して、残ったものはブランドイメージを毀損しないように焼却処分される。海外卸しを経由した一部が二次流通に出回るケースはなくはないが、商品自体が「ニセ物」であったり、インボイスが偽造されていることもある。買い付けノウハウが6〜7年程度では、真贋を確かめて仕入れるのは難しいだろう。


ピンチヒッターのHPによると、スポーツ用品や自転車、工具、ゲーム、楽器などのメーカーや問屋に対し、まとまった余剰在庫を一括で買い取る旨が記されている。アパレルについてもこの基本スタイルを貫くなら、メーカーが依頼するのは、やはりシーズンや型、サイズ、色がごちゃ混ぜになったパッキン単位が多くなるのではないか。これらを引き取るなら価格は安いだろうが、それが売れるかどうかは別の話だ。
さらに細かく言えば、百貨店系ブランドは最近は製造調達を抑えているため、まとまった在庫が手に入れることはできない。SPAの放出品は色やサイズが揃うが、他社も続々と参入していること考えると、在庫が十分にあって引き取ることができるかどうか。他は量販店ルートの売れ残りやスポーツブランドなどがあるが、どこまで中身が充実(再販に堪えうるかどうか)しているかはわからない。

ショッピングサイトでは、靴については男性、女性、子どもごとの種類別に分けられ、サイズ別でもしっかりグルーピングされている。トップページでは「全商品1点モノ」「『下記、サイズから探す』からの商品検索をおススメしております」とある。試着にせずにネットで靴を買うのなら、そうせざるを得ないからか。ただ、アパレルは引き取りの形態を考えると、価値のあるブランドでない限り、1点ものというわけにはいかない。
引き取ったパッキン単位の中身を、男性、女性、子どもはもちろん、ブランドやシーズン別で仕分けするには相当の手間がかかり、その分のコストは某大になる。仮にマニュアルに添ってパートアルバイトが作業するにしても、シーズンやテイストまで分けるには、ある程度の商品知識やファッションセンスが要求される。そうしたノウハウを修得するには、かなりの時間を要するだろう。メディア発表されたにも関わらず、サイトにアパレルが一つもないのは、そうした理由もあるのかと、逆に勘ぐってしまう。
作業は仕分けだけに止まらない。サイトに商品をアップする「ささげ業務」がある。パッキン単位の引き取りなら、自社で撮影からアイテム名、スペック、詳細説明の記載までの作業をしなければならない。すでに靴ではしっかり写真や情報がアップされているので、ノウハウはもっているだろうが、ファッションアイテムはイメージも重要だから、置撮りだけでなくモデル撮影まで行うとさらに手間やコストがかかる。
売れるにはブランドの顔ぶれがカギ
オンラインショップの現状を考えると、単に「安い」だけでは買い上げ率を高めるのは難しいと思う。売れるには「ブランドの顔ぶれ」がカギを握るし、サイトのビジュアルや商品説明も重要だ。ECは試着ができないので、FAQ以外の問い合わせ対応、返品受付ときめ細かなサービスが顧客の信頼を生む。検索エンジンの上位にランキングされるためのSEO投資はもちろんだ。一つ一つクリアしていかなければならない。
すでに実店舗ではワールドの「アンドブリッジ」、ドンキホーテの「オフプラ」、GEOクリアの「ラックラック・クリアランスマーケット」などが参入し、多店舗化を視野に入れて展開中だ。ただ、ワールドが関わっている店舗でも、ハンギングを主体のローコストオペレーションだ。商品が未使用品というだけで、VMDや陳列方法は中古品を売る2nd Streetとほとんど変わらない。
某大な仕分け作業が発生するため、商品のピックアップも試着もセルフ化するなど運営コストを抑制しなければ、利益が出ないのだ。それでも、実店舗のみならECサイトのようなささげ業務は無くなる。逆にオンラインショップは仕分け作業の他にこの作業が必要で売価が安いと、利益は薄い。損益分岐点との格闘が待っているわけだ。ラストセールは最終的には90%オフで売り切るというが、完全消化はそれほど容易ではない。それを考えると、他の引き取り商品も含めて、第三国への三次流通まで視野に入れているのかもしれない。
2018年のデータでは、日本では年間に供給されるアパレルは29億点を超える。それに対し、総消費数量はプロパー、セール、古着をすべて合算しても13億5200万点ほど。つまり、半分以上が売れ残っているわけだ。世界的なSDGs意識の高まりや焼却処分によるCO2排出の抑制からも、オフプライス業態は注目されている。ビジネス、社会性の両面から参入する企業があるのは良い傾向である。
さらに新型コロナウイルスの感染拡大で、東京一極集中のリスクが顕在化した。すでにビジネスの仕組みを変えようという動きがあり、都市構造が変化すればローカル企業にもチャンスの芽が出て来る。ラストセールにアパレルが品揃えされるのを期待しながら、オフプライスショップのオンライン版を注視して見ていきたい。