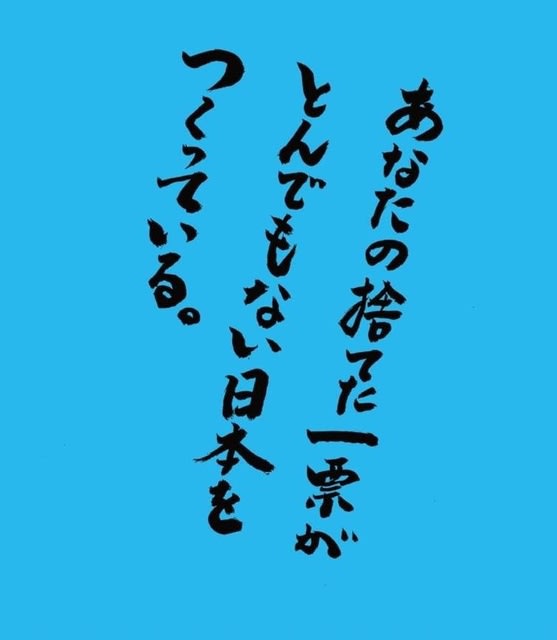2023.4.25
雨が降っていましたが、友人とひろしま美術館のピカソ展へ行ってきました。
2023.4.27
広島県手話通訳問題研究会の「通信」に次の文を投稿しました。
「ヤングケアラーの支援強化で親の通訳を子どもたちが担っている外国人家族への支援を国が4月から予算化する・・」との新聞記事を読んで随分前に家庭裁判所へ手話通訳に行った時のことを思い出した。
聞こえないお母ちゃんが問題を起こした子どもの審判に呼び出され、下の子たちを連れて裁判所へやってきたのだ。
「この母親、子どもたちの教育のことを真剣に考えてないんですよね。呼び出すといつも子どもを連れてくる、学校を休ませて・・・」
家裁の調査官には、なんでお母ちゃんが子どもを連れて裁判所へ来るのか分からなかったのだ。聞こえないお母ちゃんは子どもを連れていくことで家裁の調査官や裁判官の質問になんとか答えていたのだが。
同じような経験は僕自身にもある。児童相談所のワーカー時代、中学1年生の女の子が「好きな音楽グループはX」といった。その時はふーんと答えたのだが、Xなんて人の名前なのかグループの名前なのかも知らなかった。その後、紙屋町の紀伊國屋へ行ってみるとYOSHIKIの写真集などが何冊も並べてある。空いた時間があると書店へよくいっていたが、X(その後のX JAPAN)の本など全然目に入っていなかった。人は関心を持って初めて目に入ってくることも多いのだ。
これまでも親の通院などに通訳を子どもが担っていることについて、その子の成長についてマイナスの影響を与えることがコミュニティ通訳や心理学を学ぶ人たちには随分前っから指摘されてきた。親の病気を子どもが受け入れることでも大変なのに、病状などについて通訳もしなければならないしんどさ・・・。手話を学び手話通訳をになっている広通研の会員には容易に想像してもらえるだろう。
今、出入国管理法の改訂について国会での議論も十分にされないまま決められようとしている。全国で反対運動が起こり、私も二回ほど八丁堀福屋前のスタンディングに参加した。7・8人の静かなそして小さなスタンディングだった。
読んだ記事には、「新事業は、通訳を必要とする家庭が自治体の担当窓口などに相談し、生活状況を踏まえた上で支援するか判断する」とあったが、手話通訳も当初は本人からの申請だけであった。でも考えてみると通訳を必要としているのは家庭側だけではない。患者と医療関係者双方にとって必要なのだ。
国の新しい制度がヤングケアラー対策としてではなく、この国に住むすべての人の言葉の権利を守るための施策として進められることを願う。そして手話を学ぶ私たちも言語的マジョリティの権利を獲得する取り組みの一つとして考えていきたいと願っている。

中国新聞の記事は(2023.2.20)
「親の通訳 専門職同行へ 厚労省などヤングケアラー支援強化」の見出しで記事にしとるんやけど、これはヤングケアラー支援ではなく 言語的マジョリティの人たちの暮らしを守る行政の仕事やと思う。