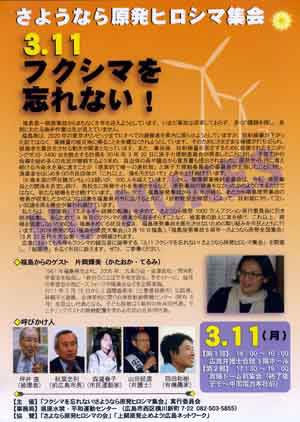3月28日 福岡県地域生活定着支援センターの 「罪を犯した人たちを地域で支えるためにはーこれからの触法障がい者・高齢者支援について考えるシンポジウムー福岡県地域生活定着支援センターの活動を通して」に参加してきました。
3月28日 福岡県地域生活定着支援センターの 「罪を犯した人たちを地域で支えるためにはーこれからの触法障がい者・高齢者支援について考えるシンポジウムー福岡県地域生活定着支援センターの活動を通して」に参加してきました。
センター長の小畑さんの事業報告、福岡県福祉労働部保護・援護課長の挨拶のあと基調講演は龍谷大学法学部教授の浜井浩一さん
テーマは「わが国における犯罪の実態と諸外国の動向ー今求められる再犯防止対策とは―」
2015年の世論調査では、犯罪が異常に少なくなってきているのに人々の意識は「犯罪が増えている」「犯罪は悪質化している」と考えている糸人がとても多い。他の国でも少年犯罪は減少している、これには子どもの貧困率が下がってきていることもあるのだろうが、スマホなどSNSなどのネット社会が若者たちのライフスタイルを大きく変化させてきていることも関係があるのかもしれない。矯正施設や少年院などの閉鎖が続いている。スマホはいつでもどこでも、自宅に引きこもっていても、同じような趣味を持つ人と気軽につながることができる。わざわざ怖い思いをして不良集団につながる必要もない。
日本の犯罪が少ないのは、非行のピークが欧米より3歳―5歳早く青年の犯罪が少ない、ほとんどの非行少年が初犯どまりで累犯化が少ないことなどがある。また年齢別の殺人を見てみても非常に少なくなってきている。殺人事件も少なくなってきている。オウムによるサリン事件以来厳罰が進められてきたが、この影響を受けたのは無職・家族がいない、いわば縁を持たないひとたち
高齢者犯罪が増えてきてはいるがその中心は万引きや自転車盗であり、その背景には生活困窮や社会的孤立が見えてくる。私は過失犯以外で事件を起こす前は幸福だったという人を見たことがない。
受刑者の中には高齢者とともに、知的障害者など、障害や病気を抱えている人も多い。受刑者のIQ相当値を見ると4人に一人はIQが70未満。そして厚生労働科学研究によると明らかに知的障害が疑われる人のうち、福祉サービスを受けていたことを示す療育手帳の所持者はわずか6%であった。刑務所にいる知的障害者の多くは、副牛的な支援を受けることなく社会の中で孤立困窮して万引きや無銭飲食の微罪を繰り返すことで刑務所に送り込まれてきた。 社会的弱者が実刑になりやすく、累犯者になりやすい。
刑罰は遠山の金さん、落とし前をつけるだけでその人の更生には役にたたない。
「それは俺の仕事じゃない」これは専門家の合言葉と言ってもいいくらいで司法の専門家ほど犯罪を犯した人のその後に無関心である。日本の刑事司法には、刑罰の逆進性を補正し、負のスパイラルを止めるための福祉などとの連携が決定的に不足している。 これは日本とイタリアなどとの大きな違い。縁が弱くなった人が刑罰によってさらに縁を失くしてしまっている。
イタリアの憲法は27条で「刑罰は更生を目的とする」と明記しており矯正処分監督裁判所や社会内刑執行事務所が設置されている。つまり逃げない福祉を持つ社会には高齢犯罪者や高齢受刑者はほとんどいないのだ。
再犯防止は社会防衛のために犯罪リスクを少なくしようとするもの。犯罪当事者は再犯リスクそのものである。立ち直りは支援対象者本人が立ち直りの主体である。いま、福祉の司法化と丸投げが行われているが丸投げはせずに司法と福祉は異文化であることを自覚したうえで人の更生を支援していく事が望まれる。人は縁によって救われる。
基調講演のあとはシンポジウム。(ここは省略)
話しては平和通り法律事務所の小林由美弁護士 福岡保護観察所の坂本歩統括保護観察官 福岡県福祉労働部福祉総務課の野上明倫課長 前田忠秋福岡県福祉労働部保護援護課長 コーディネーターは奥田知志理事長でした。





















 (これはクレンドのHPから)
(これはクレンドのHPから)