21日(火)。日テレの「リバーサルオーケストラ」の最終回を見損なって残念に思っていたら、reilaさんが「TVer で無料で見られます」とコメントして下さったので、さっそくパソコンでTVerを検索して観ました 相変わらずの強引なストーリー展開には苦笑しましたが、エンタメなので許せるかな、と思い直しました
相変わらずの強引なストーリー展開には苦笑しましたが、エンタメなので許せるかな、と思い直しました 音楽はほとんどオープニング・テーマのチャイコフスキー「交響曲第5番」に特化していましたが、この曲は素晴らしいですね
音楽はほとんどオープニング・テーマのチャイコフスキー「交響曲第5番」に特化していましたが、この曲は素晴らしいですね まったく同じテーマのメロディーが第1楽章では暗く沈んだ音楽として現れ、第4楽章では勝利の音楽として登場するのですから
まったく同じテーマのメロディーが第1楽章では暗く沈んだ音楽として現れ、第4楽章では勝利の音楽として登場するのですから こういうところにチャイコフスキーの天才を感じます
こういうところにチャイコフスキーの天才を感じます 超面白い内容だけに10回だけでは短かすぎたと思いますが、この放送によって一人でも多くの人がクラシック音楽に馴染んで、コンサートを聴きに来てくれるようになればいいな、と思います
超面白い内容だけに10回だけでは短かすぎたと思いますが、この放送によって一人でも多くの人がクラシック音楽に馴染んで、コンサートを聴きに来てくれるようになればいいな、と思います
ということで、わが家に来てから今日で2989日目を迎え、高市早苗経済保障担当相は20日午後の参院予算委員会で、放送法の行政文書をめぐる質疑で野党議員に「信用できないならもう質問しないで」などとした発言を撤回した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

この人 発言は撤回したけど 謝罪はしていない 表向きだけで 反省していないようだ





昨日、夕食に「エビの肉巻き」「生野菜サラダ」「ジャガイモの味噌汁」を作りました 「海老の肉巻き」を作るのは2度目ですが、今回も美味しく出来ました
「海老の肉巻き」を作るのは2度目ですが、今回も美味しく出来ました






エルバート・ハバード & アンドリュー・S・ローワン「ガルシアへの手紙」(角川文庫)を読み終わりました
エルバート・ハバードは1856年生まれ、アメリカの思想家・作家・教育者。1915年に乗船中のイギリス客船がドイツの潜水艦Uボートに撃沈され死亡。アンドリュー・S・ローワンは1857年生まれ。アメリカの軍人。1898年の米西戦争の英雄。1943年没 
「ガルシアへの手紙」は著者のエルバート・ハバードが「1時間で書き上げた」という話もあるくらいの短い物語です 文庫本にしてたったの13ページしかありません
文庫本にしてたったの13ページしかありません

物語は「アメリカースペイン戦争」が起きた1898年頃の出来事が基になっています アメリカの目と鼻の先にキューバがありますが、当時はスペイン領でした。そんな時キューバでスペインからの独立運動が起きます
アメリカの目と鼻の先にキューバがありますが、当時はスペイン領でした。そんな時キューバでスペインからの独立運動が起きます 当然、アメリカはそれを全面的にサポートすることになり、これがスペインとの戦争へと発展していくことになります
当然、アメリカはそれを全面的にサポートすることになり、これがスペインとの戦争へと発展していくことになります 当時のアメリカ大統領・マッキンレーは、キューバの独立運動のリーダーであるガルシア将軍とどうしてもコンタクトを取りたかった
当時のアメリカ大統領・マッキンレーは、キューバの独立運動のリーダーであるガルシア将軍とどうしてもコンタクトを取りたかった しかし、今から120年も前には当然、ケータイやスマホなどの通信機器に頼ることが出来なかった
しかし、今から120年も前には当然、ケータイやスマホなどの通信機器に頼ることが出来なかった そもそもガルシアがどこにいるのかさえ、誰も知らなかったのだ
そもそもガルシアがどこにいるのかさえ、誰も知らなかったのだ その時、ある人物が「ローワンという男なら、ガルシアへ大統領の書簡を届けることが出来るだろう
その時、ある人物が「ローワンという男なら、ガルシアへ大統領の書簡を届けることが出来るだろう 」と大統領に推薦します。これを受け、ローワンが呼ばれることになりました
」と大統領に推薦します。これを受け、ローワンが呼ばれることになりました ローワンは大統領からの書簡を受け取ると、そのままボートに乗り、キューバに赴き、敵陣に潜入し、4週間後には任務を全うし無事生還したのです
ローワンは大統領からの書簡を受け取ると、そのままボートに乗り、キューバに赴き、敵陣に潜入し、4週間後には任務を全うし無事生還したのです
物語はこれだけのことです しかし、ハバードがあえてこの物語を書こうと思ったのは、「ガルシアへの手紙」の内容ではなく、敵国キューバに乗り込んで どこにいるのかも分からないガルシアを自ら探し出してその手紙を手渡したばかりでなく、無事に大統領の元に帰ってきた「自主性」と「行動力」に感銘を受けたからです
しかし、ハバードがあえてこの物語を書こうと思ったのは、「ガルシアへの手紙」の内容ではなく、敵国キューバに乗り込んで どこにいるのかも分からないガルシアを自ら探し出してその手紙を手渡したばかりでなく、無事に大統領の元に帰ってきた「自主性」と「行動力」に感銘を受けたからです ローワンは命がけの任務であるにも関わらず、指令に対して「ムリ!無理!ムリ!」と拒否したり、「ガルシアはどんな人物で、キューバのどの辺にいるのか?」とか質問することもなく、すぐに目的を達成するための行動に移ったのです
ローワンは命がけの任務であるにも関わらず、指令に対して「ムリ!無理!ムリ!」と拒否したり、「ガルシアはどんな人物で、キューバのどの辺にいるのか?」とか質問することもなく、すぐに目的を達成するための行動に移ったのです
この物語は世界中の多くの人たちの共感を得て、100年以上にわたり読み継がれ、これまでに1億人以上の人々が読んだと言われています
気になるのは「ローワンは いったいどうやってガルシア将軍を見つけ出し、どのように生還したのか」ということです これについてはローワンの手記「ガルシアへの手紙を、いかに届けたか」に具体的に書かれています
これについてはローワンの手記「ガルシアへの手紙を、いかに届けたか」に具体的に書かれています
上記を含めて、本書は次のような構成になっています
第1章『ガルシアへの手紙』:エルバート・ハバード
第2章「解説『ガルシアへの手紙』から学べること」:三浦広
第3章「ローワンの手記『ガルシアへの手紙を、いかに届けたか』」:アンドリュー・S・ローワン
第4章「解説 ローワンの手記から学ぶべきこと」:三浦広
三浦広氏は第2章「解説『ガルシアへの手紙』から学べること」の中で「成功する人の条件は次の3点だ」と書いています
①気概と熱意がある
②明るく、前向きに生きるという覚悟がある
③他人への思いやりと感謝がある
また、「できる人」のさらなる条件は次のようなものだ、と書いています
①会社の方向、組織の目指しているところをよく知っている
②自分の位置、役割をはずさない
③自分に厳しく、自分をコントロールできる
④反省できる
⑤素直である
他方、仕事のできない人は、先の3原則が守れない人であり、次のようなタイプの人である、と書いています
①言われない限り、自分の仕事を作らない
②言い訳ばかりする
③相手によって態度を変える
④他人の目ばかり気にしている
⑤他人に「ありがとう」と言えない
⑥他人を好きになれない
⑦新しいことに対して拒否反応を起こす
⑧平気で人を利用する
上記を踏まえて、三浦氏は「(著者のエルバート・ハバードは)一人でも多くの人に、ローワンのようにできる人になってもらいたいとの願いを込めて、この教訓を本にしたのだ」とコメントしています
日本でも「自己啓発セミナー」が流行った時期がありましたが、そんなものに大金をかけるよりも、800円(税別)で角川文庫の本書を買って読む方が、よほど安価で役に立つと思います サラリーマン、経営者、自営業など職種を問わず、広くお薦めします
サラリーマン、経営者、自営業など職種を問わず、広くお薦めします














 プログラムは①シュポア「ヴァイオリン協奏曲第8番 イ短調 作品47 ”劇唱の形式で” 」、②ベートーヴェン「交響曲第1番 ハ長調 作品21」、③メンデルスゾーン「弦楽のための交響曲第8番 ニ長調」(管弦楽版)です
プログラムは①シュポア「ヴァイオリン協奏曲第8番 イ短調 作品47 ”劇唱の形式で” 」、②ベートーヴェン「交響曲第1番 ハ長調 作品21」、③メンデルスゾーン「弦楽のための交響曲第8番 ニ長調」(管弦楽版)です

 躍動感あふれる素晴らしい演奏でした
躍動感あふれる素晴らしい演奏でした
 第3楽章のメヌエットはベートーヴェンと同じように高速演奏による溌溂とした演奏が繰り広げられましたが、トリオの部分では木管楽器群の演奏が素晴らしかった
第3楽章のメヌエットはベートーヴェンと同じように高速演奏による溌溂とした演奏が繰り広げられましたが、トリオの部分では木管楽器群の演奏が素晴らしかった 第4楽章は快速テンポにより愉悦感に満ちた音楽が展開、今月末で退団する大野雄太のナチュラルホルンの素晴らしい演奏もあり、爽快なフィナーレを飾りました
第4楽章は快速テンポにより愉悦感に満ちた音楽が展開、今月末で退団する大野雄太のナチュラルホルンの素晴らしい演奏もあり、爽快なフィナーレを飾りました 」ということです
」ということです

 来シーズンは同じセンターブロックの右方向の席に移ります
来シーズンは同じセンターブロックの右方向の席に移ります 」と語りました。この曲はショスタコーヴィチが作曲した全15曲の交響曲の中で最長の作品で、演奏時間にして約80分かかる大曲です
」と語りました。この曲はショスタコーヴィチが作曲した全15曲の交響曲の中で最長の作品で、演奏時間にして約80分かかる大曲です
 現在、ベルリン芸術大学でJ=P.マインツ氏に師事しています
現在、ベルリン芸術大学でJ=P.マインツ氏に師事しています
 このテーマのリレーの間、重低音で奏でられるコントラバスの演奏が不気味です
このテーマのリレーの間、重低音で奏でられるコントラバスの演奏が不気味です 高関は、一番最初にフルート首席の竹山愛を立たせて健闘を讃え、彼女のシティ・フィルにおけるラストステージに華を添えました
高関は、一番最初にフルート首席の竹山愛を立たせて健闘を讃え、彼女のシティ・フィルにおけるラストステージに華を添えました



 小曽根はアンコールにオリジナル曲「Reborn」を鮮やかに演奏、再び大きな喝さいを浴びました
小曽根はアンコールにオリジナル曲「Reborn」を鮮やかに演奏、再び大きな喝さいを浴びました






 これで指揮ができるのか?と一瞬心配になりました
これで指揮ができるのか?と一瞬心配になりました
 お会いするのは35年ぶりくらいです
お会いするのは35年ぶりくらいです ご参加の皆さん、お話しできて楽しかったです
ご参加の皆さん、お話しできて楽しかったです









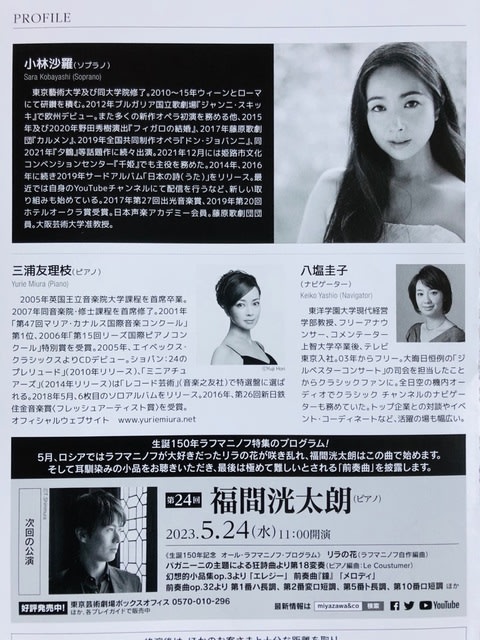


 ところが、向かいの家に引っ越してきた陽気な女性マリソル・パルバネ(マリアナ・トレビーニョ)とその家族が、メキシコ料理を持ってきたり、車のバック駐車や病院への送迎、娘たちの子守など、何かと頼み事を持ちかけてきて、死のうと思ってもなかなか死ぬことができない
ところが、向かいの家に引っ越してきた陽気な女性マリソル・パルバネ(マリアナ・トレビーニョ)とその家族が、メキシコ料理を持ってきたり、車のバック駐車や病院への送迎、娘たちの子守など、何かと頼み事を持ちかけてきて、死のうと思ってもなかなか死ぬことができない

 まるで、亡き妻が過去の思い出を思い起こさせ、オットーに「強く生きるのよ
まるで、亡き妻が過去の思い出を思い起こさせ、オットーに「強く生きるのよ
 」と思うのは映画館(とくに大手映画グループのシネコン)でのコマーシャルや予告編が多いことです
」と思うのは映画館(とくに大手映画グループのシネコン)でのコマーシャルや予告編が多いことです






 おそらく弦楽器とオルガンの音のバランスを確かめていたのだと思います
おそらく弦楽器とオルガンの音のバランスを確かめていたのだと思います テクノロジーの発達には良い面もあります。パイプオルガンの代わりに電子オルガンが使用されるようになったのもその一つです
テクノロジーの発達には良い面もあります。パイプオルガンの代わりに電子オルガンが使用されるようになったのもその一つです




