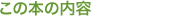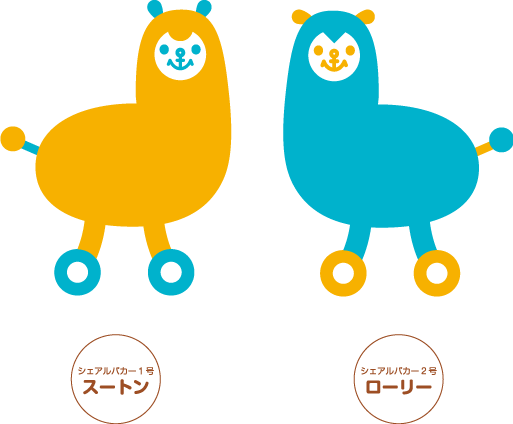書名感染症の近代史
監修・編集・著者名内海孝 著
対岸の火事のようでもあった新型肺炎が、日本でもじわじわ広がり始めた。これからどうなっていくのか。本書『感染症の近代史』(山川出版社)は江戸後期から明治にかけて、日本で流行した感染症とその対策についてまとめたものだ。「日本史リブレット」シリーズの一冊。ページは薄いが、中身は濃い。
著者の内海孝さんは1949年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。専攻は日本近代史。東京外国語大学名誉教授。
榎本武揚を思い出す
幕末から明治へ――その劇的な政権交代と社会の変化は通常、政治史、社会史として扱われる。本書はそれを医療史、とりわけ「感染症」という視点から見直したものだ。先行書をもとに、多彩なエピソード、データを積み重ねながら、「攘夷」を叫んでいた幕末の日本がなぜ開国・欧化へと舵を切ったか、その伏流を明かしている。
同じような問題意識が感じられた本に、BOOKウォッチで紹介した『近代日本一五〇年』(岩波新書)がある。著者の山本義隆氏はペリーたちの一行が1854年、二度目に来日したとき、幕府への献上品が「蒸気機関車の模型」と「有線電信の装置一式」だったことに注目していた。「それは当時の最先端ハイテク機器であり、ほかでもない西欧近代におけるエネルギー革命の直接的な産物であった」と指摘していた。黒船によって科学技術や産業文明に関する鎖国もこじ開けられ、一気に「近代化」が始まったのだというわけだ。
関連して榎本武揚のことを思い出した。戊辰戦争の最終局面、箱館・五稜郭の戦いでは幕府側の頭目だったのに、いつのまにか明治政府の重臣として大出世した。幕府と新政府の「二君に仕えた」要領のいい男というイメージが流布されているが、BOOKウォッチで紹介した『榎本武揚と明治維新』(岩波ジュニア新書)によれば、別の大きな理由があった。
榎本は長崎海軍伝習所を経て1862年から67年までオランダに留学。英語やオランダ語、ドイツ語、ロシア語など多数の言語に習熟したほか、造船、蒸気機関学、砲術、機械工学、冶金、鉱物学、化学、理学、情報通信など明治の殖産興業の基盤となる科学技術全般の最新知識をものにしていた。当時の留学経験者の中で傑出した存在だった。国際法にも明るかった。その圧倒的な知識量を知っていた新政府が改めて彼を登用したというのだ。
明治維新とは結局のところ、「鎖国」の日本に「近代」が押し寄せて社会を変えた革命だった。
「コレラ」が「攘夷」の一因?
前置きが長くなったが本書は以下の構成。
1.近代先進国の産業革命と貿易活動
2.欧州「検疫」体制と西洋医学の受容
3.転換期の西洋医学と日本人の「不潔」
4.新政府発足後の西洋経験と医療行政の設計
5.衛生政策と外来伝染病のコレラ情報
6.コレラ「衛生の警鐘」と伝染病対策
7.改正条約の実施と伝染病の国際関係
冒頭に「花火」と「手洗い」の話が紹介されている。本書の表紙にもなっている「両国の花火」。現在は隅田川の花火大会として知られる。これは1732年、疫病の流行で数万人が亡くなり、慰霊と悪病退散を祈願する目的で翌年から始まったものだという。「手洗い」は明治になってからの習慣らしい。来日した外国人が、日本の衛生状態の低さを心配し、日本人に働きかけたものだという。手洗いを奨励する外国人の姿が「絵」で残っている。日本人に「衛生観念」を教えたのは外国人だったというわけだ。
本書によると、日本では古くから痘瘡(疱瘡)が何度も流行した。6世紀に仏教とともに伝わったらしい。いわゆる天然痘だ。コレラは日本では1822年、初めて流行、多数の犠牲者を出した。オランダ船から長崎に流入したとみられている。
著者は「コレラ」に関連して記す。「その原因は日本を外国に『開放』したからと当時の日本人は考え、外国人を敵視するようになった」。いわゆる「攘夷」の一因というわけだ。未開社会がしばしば文明人との接触を拒否し、近寄ってくる文明人を殺したりした話があるが、同じような文脈を感じる。
親王に種痘をほどこした
天然痘については18世紀末にジェンナーが種痘を開発、対処法が変わっていた。日本でも19世紀半ばに伝わり、その劇的な効果が知られるようになった。次第に蘭方を学びたいという人が増えてくる。幕府は1857年、オランダの軍医ポンペを招いて長崎に西洋式の医学伝習所、医学校を開校した。ポンペは61年、西洋式病院「養生所」を開院する。さらに開港されたばかりの横浜には病院が次々とでき始めた。64年6月にフランス海軍病院、9月にイギリス海軍の「疱瘡病院」、オランダ海軍も66年に続く。幕末に「医療の文明開化」が先行して進んでいた。
アメリカの宣教師フルベッキは63年に書き残している。「西洋医学による病気治療は評判がよく、旧式(漢方)医師や迷信を信じる民衆の反対があったにもかかわらず、非常に好意をもたれています。漢方医に対し、西洋医学の決定的な勝利は明らかに予知されています」。
それを象徴する出来事が宮中であった。孝明天皇は1866年12月11日(旧暦)から発熱。親王も見舞ったが、17日に疱瘡と確認されると、天皇は感染を心配し、完治の日まで来てはいけないと命じる。そこで、親王の生母の父、中山忠能は、蘭方医に密か命じて親王に種痘をほどこした。著者は記す。
「西洋医学の優位性が宮中の世界でも、確実に認知されはじめていたことがわかる」
「時勢は親王が種痘をほどこされたように、新しい方向に傾斜していた」
孝明天皇は種痘を受けていなかった。容体は24日急変し、25日死去。67年1月9日、親王が践祚。ほどなく明治維新、明治天皇となる。
伝染病から感染症へ
開国を進めるにつれ、国内ではさまざまな感染症のリスクも高まっていく。横浜の居留地などに滞在する外国人が読む英字新聞には「水が不潔」という一文も掲載されていた。彼らからすれば、「未開地」に来たようなもので、自分たちが感染病に冒される不安があったのだろう。日本人は彼らが持ち込む新種の感染症を怖がり、外国人は日本の不衛生におびえる。まさに「文明の衝突」だ。
日本政府による医療体制の構築は、1871年の岩倉使節団がきっかけだ。米欧を回り、先進的な医学教育を見聞、「西欧文明の輸入」に腐心する。医療もその一つ。新政府は医療政策の機軸を漢方から西洋医学に転換した。75年段階で西洋医(洋医)が医師全体の21.9%、5097人にまで増えている。米欧には国民の健康をつかさどる行政機関があることから、日本でも75年、中央官庁の新しい部局として「衛生局」が誕生した。中国の『荘子』のなかで、生命を安らかに守る方法のことを「衛生」と称していることから採ったという。
1880年にはコレラ、赤痢、痘瘡などが法定伝染病に指定された。97年には「伝染病予防法」が公布。衛生状態や医療体制の向上で一時は感染症の封じ込めに成功したかに見えたが、1980年ごろから、新種が次々と出現、いずれ克服されるとみられていた結核、マラリア、デング熱が息を吹き返していることが最近の新しい動きだ。ちなみにかつて伝染病や疫病といわれていたものは現在では感染症という名前に統一され、1999年には感染症法が成立している。
日本人と感染症の長い闘いを振り返って、著者は本書の最後に、「大砲と重さくらべて衛生の いと軽きかな近代を問う――詠み人知らず」という戯れ歌を載せている。
安倍首相は最近、共産党を暴力革命政党だと称して物議を醸した。しかし、本当に恐れるべきは「感染症による暴力革命」かもしれない。対応に失敗すると、政権が危うくなり、国家の土台が揺らぐ。厚労省のHPによると、二類感染症(SARSなどが含まれる)に対応した指定医療機関は国内に351あるが、合計1758床。新型肺炎の拡大状況を考えると、やや心もとない気もする。