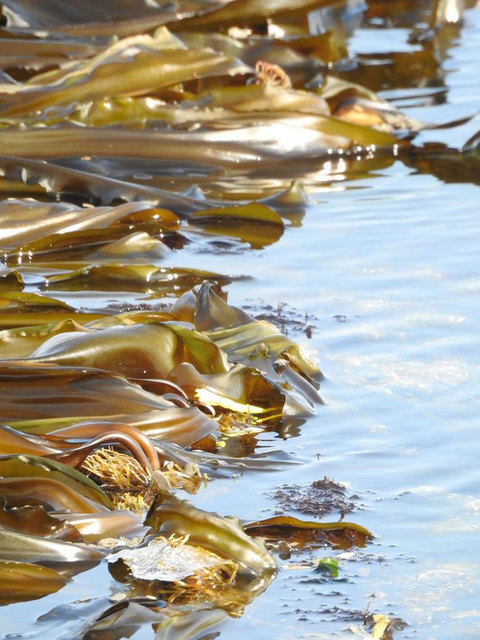アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼのこの三大消化酵素が独特のうまみを作り、細胞を活性化させるのでエイジングケアや疲労回復などに効果があります。砂糖やみりんを使用しなくてもまろやかに仕上がるので、ダイエットにもお勧め。作り方(市販の麹(200g)一袋を袋の上からもんで細かくし、ボールに入れてさらに手でこすり合わせるようによくすり合わせ細かくします。消毒した保存容器に入れ、醤油200〜450ccを注いで混ぜる(1対1の割合でも良いのですが、麹や醤油の濃度によって水分が足りない時があります。ある程度加えたら様子を見て好みの加減に足して下さい)常温で1〜2週間くらい1日1回ふるか混ぜるかしてトロミがでたら出来上がりです。発酵メーカーがあれば60度で一晩で出来ます。自家製の調味料は好みの味にでき、熟成期間で変わる味の変化やとろみなどを含めて育てる楽しみがありますね。
生姜焼なども醤油麹だけでパパッと美味しい、私はオールインワン調味料呼んでいます。

バニラビーンズの種子をこそげた後のサヤも捨てません。

ついでに糠漬けもいかがですか?
ギャバが多い発酵食の糠つけは、ギャバが多く血圧の上昇を抑え、ストレスの緩和も期待できます。
ナチュラルな甘みで軽く酸味があるので、疲れた時などにお勧めです。


薬膳で眼精疲労に効くのは菊花。
目のかすみ、ドライアイなど主に目のトラブルの解消に使用され、クコの実を加えたお茶は飲む目薬と言われる漢方薬の「紀菊治黄丸」です。
私はいつものお茶に白や黄色の菊花茶(乾燥)、クコやナツメを加えてブレンドしています。
酒毒緩和作用が期待できるので、中国では強いお酒をいただく時にも飲まれています。
店頭で見かけ始めた黄色や紫の国産食養菊はまた少し効能が異なりますが、独特の風味がよいものですね。
アクとエグミをとり、色を保つ為に熱湯に酢を加えてさっと茹で、冷水にとってギュッと絞って調理します。
甘酢漬けや、お浸し、椀もの、お刺身のツマなどに添えると、美しいアクセントに。
山形で食べた紫菊は「もってのほか」と言うインパクトのある名前、由来は御紋の花を食べるとは(もってのほか)だからだそうです、本名は「延命役」素敵な香りとシャキシャキした食感が特徴です。

冬野菜の白菜は大根・豆腐と並んで「養生三宝・ようじょうさんぽう」の一つ、冬の風邪予防や免疫力向上に効果的なので特に食べたい野菜です。
95%以上が水分ですが、バランスよくビタミンやミネラル類を含み食物繊維が豊富。
疲れた胃をケアし、美肌効果もあります。
我が家の「ジャムで作る、みずみずしい白菜の浅漬けサラダ」。
ジャムは甘みをつけるのではなく、旨味とまるみをつける為です、フルーツのフレーバーもほんのり香る。
ジャムは柑橘系がよく合います、日向夏のマーマレードもよく合いますし、白菜が美味しい季節に実るりんご、みかん、柚子はお勧めです。
私は季節のジャムやコンポートを作るので、組み合わせが特に楽しく、手作りされている方はぜひ。
春のキャベツとグレープフルーツ、夏のキュウリとレモンなど季節のメドレーでサラダをたっぷりいただきます。
寒い頃にはスープがお勧めです、漬け汁は旨味があるのでスープに加えるとグッと美味しくなります。
朝のスープは目覚めをよくし、昼のスープはリラックスし、夜のスープは滋養がとれると良いことづくめ。
汁物は簡単で、栄養素を効率よく吸収できます。

初めて食べたのは港近くの定食屋さん、近所の市場でも沢山売られていました。
フライで頂きましたが、身が柔らかで骨まで食べられる白身が美味。
傷みやすいという事で、当時は東京ではあまり見かけませんでしたが、今ではスーパーでも見かけるようになりました。
サイズも小ぶりで10cm前後、下処理もあまり無いので調理もしやすい。
先日も、市場でふくよかなメヒカリを見つけたからと、わざわざ一夜干しにし、天麩羅にしてくれた友人がいました。
庭の酢橘をもいできて、さっと搾る。
粗塩で熱々をいただくと白身の香りもたって美味、柔らかな身がホロリとほどけます。
脂がのっているので干物にしたら炙るだけで美味しい、カルシウムたっぷりです。
本名はアオメエソ。
あだ名の由来は、緑色の目がキラリと光るから目光。

じゃが芋は、とても生命力が強く保存もきくので世界中で栽培されています。
豊富なビタミンCは、デンプンに守られているので比較的熱に強く、クセがないのでどんなジャンルもすんなり受け入れてくれる頼もしい野菜。
胃腸を活性化し便秘改善などの薬効もあり、ドイツではじゃが芋をすりおろした汁やスープは胃腸症に良いとされる民間療法です。
余分な水分や塩分を排出してくれるカリウムが多く、むくみ改善にも有効です。
じゃが芋の芽を見つけたら取り除きます、ソラニンと言う有害物質なのでそこだけ気をつけて。
茹でる時は3つまみの塩を加え、皮ごと水から低温でゆっくり火を入れると酵素が働いて甘くて美味しい。
北海道で始めてインカのめざめを口にした時は、その栗のような色とほっこりした甘みにじゃが芋の観念が変わったのでした。
固めに下茹でし、皮ごと太めのくし切りにして片栗粉をまぶしてカラリと揚げると最高です。
栄養もあり、お腹を満たすアレンジ自在なじゃが芋、フランスでは「大地のりんご」と呼ばれています。

芹の由来は競い合うように成長するので「せり」の名前がついたとか。
ビタミン、カルシュウム、鉄分、食物繊維を含み、便秘、貧血などに効能があり免疫力を高めます。
芹は根の部分をよくあらい4cm幅に切り、めんつゆ程度の味付けで煮て、多めの卵でとじると美味。
根の部分は秋田県ではきりたんぽ鍋などには欠かせないそうで、栄養価も高いようです。
香りのもとになっている精油成分には発汗作用があり冷え性にも有効、肌も保湿します。
干したものを刻んで布袋などに入れ、入浴剤にすると体が温まるので神経痛や肩こりにきく民間療法は有名です。

芹の由来は競い合うように成長するので「せり」の名前がついたとか。
ビタミン、カルシュウム、鉄分、食物繊維を含み、便秘、貧血などに効能があり免疫力を高めます。
芹は根の部分をよくあらい4cm幅に切り、めんつゆ程度の味付けで煮て、多めの卵でとじると美味。
根の部分は秋田県ではきりたんぽ鍋などには欠かせないそうで、栄養価も高いようです。
香りのもとになっている精油成分には発汗作用があり冷え性にも有効、肌も保湿します。
干したものを刻んで布袋などに入れ、入浴剤にすると体が温まるので神経痛や肩こりにきく民間療法は有名です。

みその中でも特に赤みそに多い「メラノイジン」は、糖分の吸収スピードを抑えるので、食後に血糖値が急激に上がりません。
おみそ汁はもとより、酢みそ噌などにすると更に効果が上がりますね「酢も血糖値の上昇をゆるやかにする為)。
糖尿病の方にもお勧めです。
気になるみその塩分ですが、みそに含まれる大豆ペプチドには血圧を下げて緩和する効果があり、そちらの方がメリットがあり大きいそう。
じゃが芋、さと芋、ほうれん草、春菊、大豆、納豆、ひじき、エリンギ、アボガドなどはカリウムを多く含み、体内の塩分を排出します。
気になる方は、みそと合わせてとるとよいですね。
赤みそは約2年以上と熟成期間が長く、独特の香りと深い旨みが体にじんわり染み入ります。
今の季節はゼラチン質が多いツルツルのナメコと合わせるのが私は最高だと思います。
赤みそ作りで有名な、愛知県の碧南で蔵巡りを楽しみました。
写真は昔ながらの美味しい赤みそを作る(南蔵)さん。
いい乳酸菌の香りで充満していました。

ボウルに卵黄1個、粒マスタード小さじ1、酢小さじ1〜2、きび砂糖とこしょう各少々、粗塩小さじ半を合わせて、泡立て器でよく混ぜる。
オリーブオイル(菜種油、ピーナッツオイルなどでも)60ccを少しずつ垂らしながら混ぜ続けるとマヨネーズができます。
粒マスタードは練りからしやホースラディッシュ(西洋わさび)でもOK。
今日は酢の代わりに、庭で実る酢橘とまだ青いみかん果汁をミックスして絞って入れてみました。
爽やかな酸味と香り、ナチュラルな甘みで、マヨネーズが素晴らしく美味しくなります。
皮もほんの少し削って加えるのもいい。
柑橘の香りには気の巡りを良くする効能や美肌効果が見込めます。
この自家製マヨネーズは、蒸したり茹でたりしたじゃがいもやさつまいもにからめると最高ですよ。
充分美味しいですが、コクをもう少し足したい時は、クリームチーズを加えても。

ペルーは美食の国として知られています。
代表的な料理はセビーチェ(パクチー、唐辛子、柑橘果汁、シーフードをマリネしたもの)やコルデロ(仔羊の煮込み料理)。
他にもスパイスたっぷりの肉料理、やさしいお味の芋料理、トマト料理など本当に多様。
ペルーはスペインの植民地だったこともあり、アフリカやアジア移民の文化が織り交ざり、沢山の国の食文化が取り入れられています。
主食は日本と同じお米ですが、トウモロコシやじゃが芋、トマト、唐辛子などの原産地でもあるので、伝統食に多く取り入れられています。
日本とも結びつきがあるのでお醤油を使う料理もあるそう、日本人の味覚に合うわけですね。
そのうち、トウモロコシで作られる発酵酒「チチャ」やブドウで作られる「ピスコ」にトライしたいと思っています(いつかマチュピチュにも行ってみたい)。