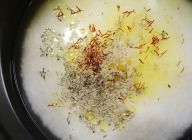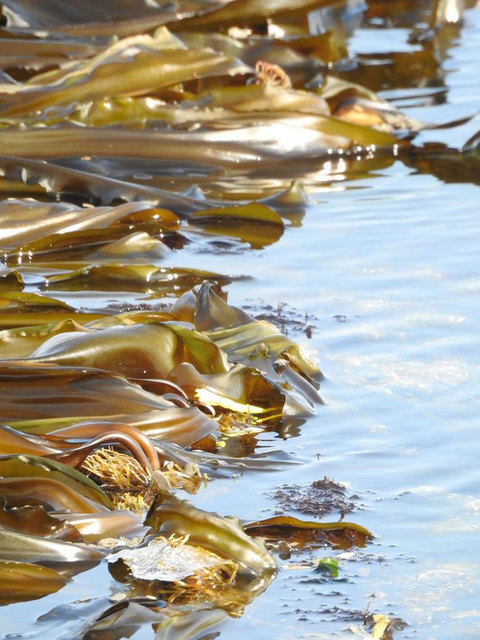© PRESIDENT Online ※写真はイメージです。(写真=iStock.com/Al Gonzalez)
© PRESIDENT Online ※写真はイメージです。(写真=iStock.com/Al Gonzalez)
訪日外国人の約7割が、日本食を楽しみしている。なぜ日本食が人気なのか。食文化史研究家の永山久夫氏は、「日本食の伝統技術は世界に類を見ない。教養として知っておいて損はない」と説く――。
※本稿は、永山久夫監修『ビジネスエリートが知っておきたい 教養としての日本食』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
訪日外国人の7割が「日本食を食べたい」
観光庁が実施した「平成28年度訪日外国人の消費動向」によると、「訪日前に期待していたこと」というアンケートに、約7割の訪日外国人が「日本食を食べること」と答えています。なぜ、外国人は日本食に魅せられるのでしょうか。理由は、おいしさ、ヘルシーさ、見た目の美しさなど、複合的でしょうが、それを支えているのは世界に類を見ない日本食の伝統技術です。
外国人にも人気の高い日本の代表料理のひとつに、刺身があります。世界の食文化史を見ても、魚を生で食べるという発想そのものが極めてユニークであり、刺身を食べるということは、日本の食文化の特異さを端的に体験することなのです。
皿に複数の種類の刺身が盛りつけられている「お造り」は、赤や白など見た目も華やかで、視覚的な美しさも楽しめる料理です。じつはこの盛り付けは、見栄えだけでなく、料理の作法としてのルールや意味があります。
刺身はおいしく食べられる順に並べられている
刺身の盛り付けは基本的に、器の左手前に淡白な白身の魚やイカ、右手前に貝類などの黄色い魚介、奥にマグロなどの赤身魚となっています。これは淡白な白身魚から、味の濃いものへと順に食べてそれぞれの味をしっかり楽しめるように並べられているのです。
この刺身の盛り付けには「山水盛り」と呼ばれる決まった型があります。山水盛りとは、三つの山を作るように七、五、三の比重で刺身を盛ったもので、先ほど紹介した順番で並べられます。さらに、その間にけんやつま、かいしき(飾り葉)が置かれ、さらに辛味が添えられます。
日本で巻物料理が発展した3つの理由
海苔巻にはじまり、伊達巻、昆布巻、紫蘇巻、鳴門巻、餡巻など、日本には世界でも珍しいほど多彩な巻物料理が存在しています。近年は恵方巻が節分の料理として定着しました。日本でこれほど巻物料理が発展した背景には、3つの理由が考えられます。
第一の理由は、巻物にすることで異なる食材を一体化させることができるからです。たとえば、昆布巻なら昆布の出汁とニシンの旨味が合わさって、おいしさを作り出します。異なる味の食材を一体化させることによって、食材を個別に食べるよりも複雑で深い味わいが演出できるのです。
第二の理由としては、見た目の美しさが挙げられます。巻物のそれぞれの食材は、互いに引き立て合って断面を彩り、美しい渦巻き模様を作り出します。渦巻き模様はどこかユーモラスに感じます。料理店ではもちろん、家庭で巻物を作るときも、作り手は断面の美しさを考えて食材を配置しています。重箱や皿に盛り付けるときも、その断面がよく見えるように工夫します。料理のおいしさをアピールするには、視覚的効果も大切なのです。
高温多湿の悪条件が食の安全意識を高めた
第三の理由は、食材を巻くことによって保存性が高まるからです。巻物を作るときは、巻簾で食材を巻き込み、力をこめてギュッと締めつけます。昆布や植物の葉、竹の皮などを用いる巻物もありますが、いずれも堅く締めつける点は共通しています。これによって形が崩れにくくなるのですが、それだけではありません。食品は酸素に触れると酸化し、腐敗しやすくなりますが、全体を締めると酸素に触れる部分が少なくなって酸化を防げるのです。
日本人は、高温多湿の気候の中で食物の保存に苦労してきましたから、巻物は理に適っているのです。味の調和と見た目の美しさと保存性、この3つに配慮した巻物料理は日本人の食文化を豊かにしてきました。
高温多湿という食品にとっての悪条件は、日本人の食の安全への意識を高めました。先人が安全への意識を徹底していなければ、刺身や寿司が食文化として定着することはなかったでしょう。
「食べられるカビ」麴菌
2006年に日本醸造学会によって日本を代表する菌が選定されました。それが麴菌です。
麹菌には、A.オリゼー(黄麴菌)、A.ソーエ(醤油麴菌)、A.リュウキュウエンシス(黒麴菌)、A.カワチ(白麴菌)などいくつかの種類があります。味噌や醤油、日本酒を作るのに使われているのは、A.オリゼーです。味噌や醤油、日本酒などの発酵食品を作るときに欠かせないもので、麴菌はカビではあるけれど、食べられるカビというのが特徴です。
これらの発酵食品に用いる麴とは、蒸した米などの穀物や豆類に、麴菌を繁殖させたものを言います。和食に欠かせない味噌や醤油といった調味料や日本酒を作るために使う麴菌は、たしかにその働きだけで日本を代表する菌と言えそうです。それに加え、麴菌が国菌となった背景にはもうひとつの理由があります。
A.オリゼーは地球上で日本にしかない
それは、A.オリゼーは、日本にしかない菌だからです。2005年にA.オリゼーのゲノム解析が完了した結果、A.オリゼーはもともと自然界に存在していた菌ではないことがわかりました。日本人が発酵食品を作るために長い時間をかけて、より発酵に適した株を選び、それらを育てて現在の菌になったと考えられるのです。
その根拠は、A.オリゼーにはカビ毒を生成する機能がなくなっていること、一般的なカビは1個の胞子に1個の核を持つのに対して、1個の胞子に複数の核があること、またそのことにより形質が安定していること、発芽が早いこと、酵素を作り出す力が大きいことなどが挙げられます。こうした特徴は、発酵食品を作るためにはとても都合がよく、ここまでの特徴を備えるには、人の手が加わらなければできないと推察できます。
A.オリゼーは、食文化を磨き抜いてきた日本人の叡智の結晶といっても過言ではないでしょう。日本食の伝統技術を語ることは、日本人そのものを語ることになるのです。
トンカツはもともとフランス料理だった
日本人は、海外の文化を取り入れ、自分たち流にアレンジすることが得意です。トンカツのルーツは「コートレット」というフランス料理で、もともとは骨付きの背肉を表す言葉でした。コートレットは英語ではカットレットと発音するので、これが日本語のカツレツになりました。ビーフカツレツ、チキンカツレツなどの料理もありますが、最も親しまれたポークカツレツには、いつしか豚を表す「とん」という音が当てられて「トンカツ」となったのです。
明治初期に日本に伝えられたコートレットのレシピは、現在のトンカツとはまったくの別物でした。1872(明治5)年に刊行された仮名垣魯文(かながきろぶん)の『西洋料理通』で紹介されているのは、鍋で溶かしたバターに豚のあばら肉と刻んだネギを入れて揚げ、小麦粉や塩、胡椒、酢などを加えてじっくりと煮るというものです。また、1895(明治28)年に銀座にオープンしたレストラン「煉瓦亭」で出されていたコートレットは、薄切りの仔牛肉をひたひたの油で半焼きにしてからオーブンに入れ、バターで仕上げた料理でした。
「あっさり」させて大評判になった
ところが、これはとても脂っこく胸焼けがすると日本人の客には受け入れられませんでした。そこで、煉瓦亭のシェフが改良を加えたのが、豚肉に軽く塩と胡椒をふって、小麦粉、溶き卵、パン粉をつけて油で揚げるポークカツレツです。
コートレットと比べるとあっさりとしたポークカツレツは、大評判になりました。そして、昭和に入るとあちこちの飲食店でトンカツが供され、ついには専門店も登場。白いご飯と味噌汁、口の中をさっぱりさせるたっぷりの千切りキャベツとパセリという定食で出す店が増えました。こうしてトンカツは庶民に愛される料理になっていったのです。
永山 久夫(ながやま・ひさお)
食文化史研究家、長寿食研究所所長
1932年、福島県生まれ。平成30年度文化庁長官表彰受賞。和食を中心に長寿食を研究し、各地の長寿者の食事やライフスタイルを取材。日本の古代から明治時代までの食事の研究に長年携わる、食事復元研究の第一人者でもある。