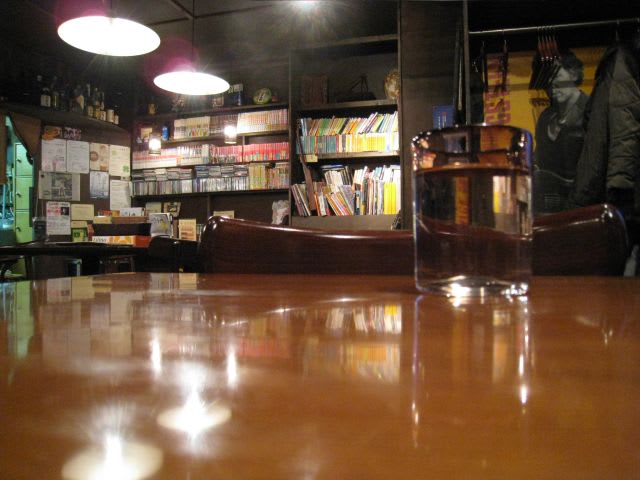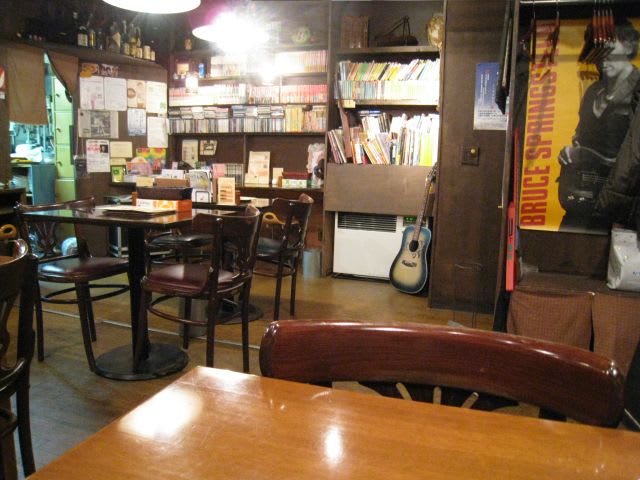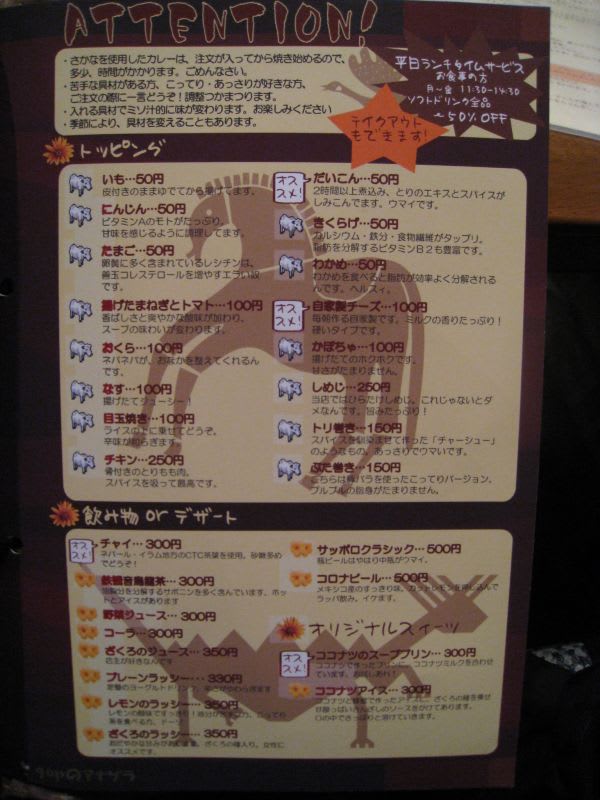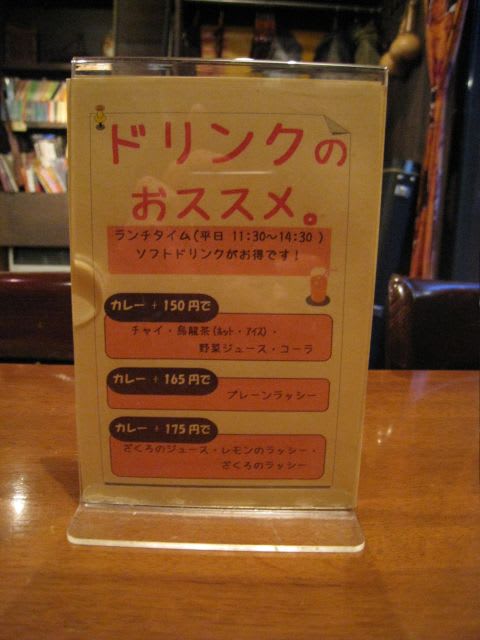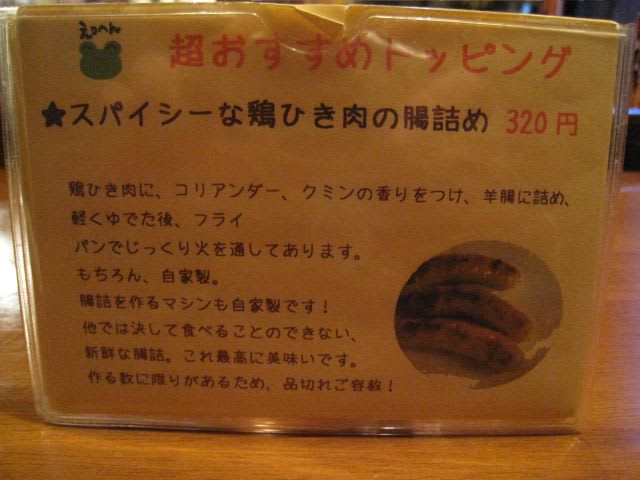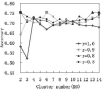落ちこぼれをなくす楽しいピアノ・レッスン, 新井千音美, 音楽之友社 ON BOOKS 57, 1985年
・著者自身のピアノ教師としての体験をもとに、そのレッスンのノウハウをまとめた本。生徒との会話など、具体的な記述が豊富です。
・私自身、大学の後輩などにバイオリンを教えることがありますが、それまでの経験をもとに自分なりの工夫も取り入れたりしています。一つは、『カルテ』と称するメモを私が取りながらの進行。メモ(A4チラシの裏)には日時からはじまり、弾いた曲、注意点、宿題等々を書き込みます。定期的に教えることが出来ず、数ヶ月も経ってしまうと、教える方も習う方も何をやっていたかすっかり忘れてしまうことから生じた習慣です。もう一つはデジカメの活用。「肘が低い」だの「弓の動きがぶれている」だの口で言うよりも、デジカメで静止画または動画で撮って本人に見せると納得度が全然違います。ついでに録音もいいかも。しかし、そんな道具の話よりも大事なのは、本書でも再三指摘されているように、いかに楽器への興味を維持するかが問題です。これについては正直お手上げ。今のところ、「辞めたかったら辞めなさい」という態度です。「こりゃすげぇ~!! 自分もあんな風に弾けるようになりたいなぁ~」と思わせるだけの力量があればよいのですが。。。
・著者(男性)は昭和初期生まれにもかかわらず、ずいぶんハイカラなお名前。
・「教え始めの頃は、「やる気のない子に、ピアノを習わせることはない」と "しかめっ面" をしたり、「おけいこしてこない子は、レッスンに来なくていいよ」と追い返したり、「親の見栄で嫌がる子を、無理に連れてこないでください」と言ったりしたものでした。 しかし、末娘にピアノを教えようとした時から、私のピアノ・レッスンについての考え方が、がらりと変わってきました。いや "変わらざるを得なかった" ということになってしまったのです。」p.3
・「初めて、ピアノを習いに来た時の、あの期待に満ちた子供たちの瞳を、さらに希望に溢れたものにしてやりたいと祈って。」p.5
・「私たちは、新しく物事を始める時や、何か素敵な体験をした時など、それに夢中になったり、感動しすぎたりするものです。」p.10
・「ここで、一応 "落ちこぼれの関門" を整理してみますと、次のようになります。
●落ちこぼれの関門
第一の関門 習い始めて、三~四ヶ月の頃
第二の関門 小学校へ入学した頃
第三の関門 小学校五~六年の頃(思春期前期)
第四の関門 中学生になった時
第五の関門 高校へ進んだ時期」」p.22
・「そういう子ども達のピアノを習おうという意欲を、意識の不足している生活環境と、画一的で研究不足の指導が失わせていったのだと思います。」p.28
・「《大人は皆、子どもの時を忘れている》という本がありますが、本当にそうですね。」p.32
・「よく、「何歳になったから、もうピアノのレッスンを始めてもよいのでは……」と言われますが、 "何歳か?" というより、"どんなことができるか?" ということのほうが判断の基準になります。(中略)①話が、聞ける(社会性)。 ②指先が、しっかりしている(身体的条件、反射神経と器用さ)。 ③区別ができる(理解力・判断力)。 ④身の周りのことができる(自立性・自主性)。 ということがある程度できるように育っていれば、レッスンを受けさせてもいいでしょう。」p.35
・「私たちは、子どもにピアノを教えるプロであると同時に、子どもを "音楽好き" にするプロでなければならないのですから、楽しく分るように指導したいものです。」p.38
・「学校の教育は、"知的な教育" を柱にしていますが、私たちの教育は "感動の教育" と考えられます。」p.44
・「仲良しになれば、子どもがついてきます。子どもに敬遠されるようでは、指導になりません。」p.53
・「"鉄は、熱いうちに。子どももお母さんも、意欲と関心のあるうちに" 細心の注意を払って導いてやるようにしたいものです。」p.59
・「"しつけ" の中で、一番きちんとやらせたいのは "おじぎ" と挨拶です。挨拶 "おねがいします" がしっかり言え、おじぎをきちんとさせると、幼児でも「これから勉強だな、しっかりやろう」という気持になります。」p.62
・「足がブランブランよりは、ついていたほうがいいに決まっています。特に、脱力のコツがつかめない子には、足がつき、腰が安定するように、いつも台を置いてやるようにしてあげてください。」p.66
・「ブラームスは、絶対にピアノのふたを閉めさせなかったそうです。それは、いつ楽想が湧いてくるか分からない、だから、いつでもピアノにさわれるように……だそうです。」p.68
・「お母さんに分からないと、家での勉強を見てくれる協力者になってくれませんから、協力者・補助教師としてのお母さんも育てることも忘れてはいけません。」p.77
・「教育という語は、"教える" という字と "育てる" という字からできています。『教えるだけでなく、育てることも教育ですよ』と言っているのですね。でも、とかく私達は、教えることだけに夢中になり、育てることも指導であるということを忘れているかも知れません。この生徒が、こうあってくれればいいなあという "好ましい状態に育つように、教え導くことが教育" だということを、もう一度はっきり頭の中へ入れておきましょう。」p.86
・「"おさらい会などで、よく弾いているから" といって、どのぐらい分かっているか? ということは、分かりません。弾いていることと、分かっていることとは、いつも同じとは言えないからです。」p.98
・「仮りに、 「私は、もっと勉強したのに!!」とか 「こんな曲なんか、二~三週間であげちゃったのに。この子はどうして!?」などと思うようになったとしたら、それだけで "あなたは、お年寄り" ですよ。」p.106
・「そのような生徒は、 「三時間も、四時間も、机に向かいっきりで、テスト勉強するわけでもないでしょ。勉強の間を見て、指の練習ぐらいはしたほうが、テスト勉強の能率があがるわよ。指を動かすことは、脳細胞を程よく刺激して、頭の働きをよくするの、あなたも知ってるでしょ……。(中略)」 と話してやります。」p.110
・「しかし、せっかくの名曲も、"楽譜を見なければ弾けない" というのでは情けないと思います。」p.137
・「人を指導するという立場で、注意するタイプを、大きく分けますと、"誉める" "叱かる" "怒る" の三つに分けられると思います。」p.143
・「演劇の世界に、"大根役者" という言葉があります。"大根役者" というのは "台本役者" という言葉が訛ってできたのだそうです。」p.186
・「東京学芸大の品川不二雄教授が、NHK・TVの母親学級で「自主性を育てるもの」と題する講演をなさったことがありました。(中略)"自主性を育てるもの" について、独立心・自立心・創造性・意欲・積極性・自信の六項目に分けて話され、最後に『"育てる" とは、"引っぱり出す" ということです』と結んでおられました。」p.198
・「子どもにとって一番身近な音楽――今、弾いている曲――を、より美しいものにしようとさせるには、「子ども自身に、自分の指で弾いているピアノを、よく聞かせる」ことから始めなければならないでしょう。」p.200
・「勉強や部活が忙しくても、その間をみて、気分転換の一つの方策としてでもピアノを取り入れながら、レッスンも続けている生徒もいることを思えば、教師たるもの「どうして、この子が、そんなにあっさりレッスンを止めていくのか?」反省してみる余地はないでしょうか?」p.209
・「先日、テレビで、有名な合唱指導者が「合唱指導で、一番大切なことは?」とのアナウンサーの質問に答えて「練習に参加して本当によかった。また、ぜひ練習にこよう」という欲求と、「ほんの少しでよいから、練習してくることを与えて帰す」ことだと答えていました。 レッスンも、「レッスンを受けて本当によかった。また、ぜひレッスンにこよう」という意欲を持たせて帰したいものですね。」p.210
・「この五年間に、この前の発表会から今までに、何を教えてきたのか? やはり記録をしたほうがいいと思います。」p.213
・著者自身のピアノ教師としての体験をもとに、そのレッスンのノウハウをまとめた本。生徒との会話など、具体的な記述が豊富です。
・私自身、大学の後輩などにバイオリンを教えることがありますが、それまでの経験をもとに自分なりの工夫も取り入れたりしています。一つは、『カルテ』と称するメモを私が取りながらの進行。メモ(A4チラシの裏)には日時からはじまり、弾いた曲、注意点、宿題等々を書き込みます。定期的に教えることが出来ず、数ヶ月も経ってしまうと、教える方も習う方も何をやっていたかすっかり忘れてしまうことから生じた習慣です。もう一つはデジカメの活用。「肘が低い」だの「弓の動きがぶれている」だの口で言うよりも、デジカメで静止画または動画で撮って本人に見せると納得度が全然違います。ついでに録音もいいかも。しかし、そんな道具の話よりも大事なのは、本書でも再三指摘されているように、いかに楽器への興味を維持するかが問題です。これについては正直お手上げ。今のところ、「辞めたかったら辞めなさい」という態度です。「こりゃすげぇ~!! 自分もあんな風に弾けるようになりたいなぁ~」と思わせるだけの力量があればよいのですが。。。
・著者(男性)は昭和初期生まれにもかかわらず、ずいぶんハイカラなお名前。
・「教え始めの頃は、「やる気のない子に、ピアノを習わせることはない」と "しかめっ面" をしたり、「おけいこしてこない子は、レッスンに来なくていいよ」と追い返したり、「親の見栄で嫌がる子を、無理に連れてこないでください」と言ったりしたものでした。 しかし、末娘にピアノを教えようとした時から、私のピアノ・レッスンについての考え方が、がらりと変わってきました。いや "変わらざるを得なかった" ということになってしまったのです。」p.3
・「初めて、ピアノを習いに来た時の、あの期待に満ちた子供たちの瞳を、さらに希望に溢れたものにしてやりたいと祈って。」p.5
・「私たちは、新しく物事を始める時や、何か素敵な体験をした時など、それに夢中になったり、感動しすぎたりするものです。」p.10
・「ここで、一応 "落ちこぼれの関門" を整理してみますと、次のようになります。
●落ちこぼれの関門
第一の関門 習い始めて、三~四ヶ月の頃
第二の関門 小学校へ入学した頃
第三の関門 小学校五~六年の頃(思春期前期)
第四の関門 中学生になった時
第五の関門 高校へ進んだ時期」」p.22
・「そういう子ども達のピアノを習おうという意欲を、意識の不足している生活環境と、画一的で研究不足の指導が失わせていったのだと思います。」p.28
・「《大人は皆、子どもの時を忘れている》という本がありますが、本当にそうですね。」p.32
・「よく、「何歳になったから、もうピアノのレッスンを始めてもよいのでは……」と言われますが、 "何歳か?" というより、"どんなことができるか?" ということのほうが判断の基準になります。(中略)①話が、聞ける(社会性)。 ②指先が、しっかりしている(身体的条件、反射神経と器用さ)。 ③区別ができる(理解力・判断力)。 ④身の周りのことができる(自立性・自主性)。 ということがある程度できるように育っていれば、レッスンを受けさせてもいいでしょう。」p.35
・「私たちは、子どもにピアノを教えるプロであると同時に、子どもを "音楽好き" にするプロでなければならないのですから、楽しく分るように指導したいものです。」p.38
・「学校の教育は、"知的な教育" を柱にしていますが、私たちの教育は "感動の教育" と考えられます。」p.44
・「仲良しになれば、子どもがついてきます。子どもに敬遠されるようでは、指導になりません。」p.53
・「"鉄は、熱いうちに。子どももお母さんも、意欲と関心のあるうちに" 細心の注意を払って導いてやるようにしたいものです。」p.59
・「"しつけ" の中で、一番きちんとやらせたいのは "おじぎ" と挨拶です。挨拶 "おねがいします" がしっかり言え、おじぎをきちんとさせると、幼児でも「これから勉強だな、しっかりやろう」という気持になります。」p.62
・「足がブランブランよりは、ついていたほうがいいに決まっています。特に、脱力のコツがつかめない子には、足がつき、腰が安定するように、いつも台を置いてやるようにしてあげてください。」p.66
・「ブラームスは、絶対にピアノのふたを閉めさせなかったそうです。それは、いつ楽想が湧いてくるか分からない、だから、いつでもピアノにさわれるように……だそうです。」p.68
・「お母さんに分からないと、家での勉強を見てくれる協力者になってくれませんから、協力者・補助教師としてのお母さんも育てることも忘れてはいけません。」p.77
・「教育という語は、"教える" という字と "育てる" という字からできています。『教えるだけでなく、育てることも教育ですよ』と言っているのですね。でも、とかく私達は、教えることだけに夢中になり、育てることも指導であるということを忘れているかも知れません。この生徒が、こうあってくれればいいなあという "好ましい状態に育つように、教え導くことが教育" だということを、もう一度はっきり頭の中へ入れておきましょう。」p.86
・「"おさらい会などで、よく弾いているから" といって、どのぐらい分かっているか? ということは、分かりません。弾いていることと、分かっていることとは、いつも同じとは言えないからです。」p.98
・「仮りに、 「私は、もっと勉強したのに!!」とか 「こんな曲なんか、二~三週間であげちゃったのに。この子はどうして!?」などと思うようになったとしたら、それだけで "あなたは、お年寄り" ですよ。」p.106
・「そのような生徒は、 「三時間も、四時間も、机に向かいっきりで、テスト勉強するわけでもないでしょ。勉強の間を見て、指の練習ぐらいはしたほうが、テスト勉強の能率があがるわよ。指を動かすことは、脳細胞を程よく刺激して、頭の働きをよくするの、あなたも知ってるでしょ……。(中略)」 と話してやります。」p.110
・「しかし、せっかくの名曲も、"楽譜を見なければ弾けない" というのでは情けないと思います。」p.137
・「人を指導するという立場で、注意するタイプを、大きく分けますと、"誉める" "叱かる" "怒る" の三つに分けられると思います。」p.143
・「演劇の世界に、"大根役者" という言葉があります。"大根役者" というのは "台本役者" という言葉が訛ってできたのだそうです。」p.186
・「東京学芸大の品川不二雄教授が、NHK・TVの母親学級で「自主性を育てるもの」と題する講演をなさったことがありました。(中略)"自主性を育てるもの" について、独立心・自立心・創造性・意欲・積極性・自信の六項目に分けて話され、最後に『"育てる" とは、"引っぱり出す" ということです』と結んでおられました。」p.198
・「子どもにとって一番身近な音楽――今、弾いている曲――を、より美しいものにしようとさせるには、「子ども自身に、自分の指で弾いているピアノを、よく聞かせる」ことから始めなければならないでしょう。」p.200
・「勉強や部活が忙しくても、その間をみて、気分転換の一つの方策としてでもピアノを取り入れながら、レッスンも続けている生徒もいることを思えば、教師たるもの「どうして、この子が、そんなにあっさりレッスンを止めていくのか?」反省してみる余地はないでしょうか?」p.209
・「先日、テレビで、有名な合唱指導者が「合唱指導で、一番大切なことは?」とのアナウンサーの質問に答えて「練習に参加して本当によかった。また、ぜひ練習にこよう」という欲求と、「ほんの少しでよいから、練習してくることを与えて帰す」ことだと答えていました。 レッスンも、「レッスンを受けて本当によかった。また、ぜひレッスンにこよう」という意欲を持たせて帰したいものですね。」p.210
・「この五年間に、この前の発表会から今までに、何を教えてきたのか? やはり記録をしたほうがいいと思います。」p.213