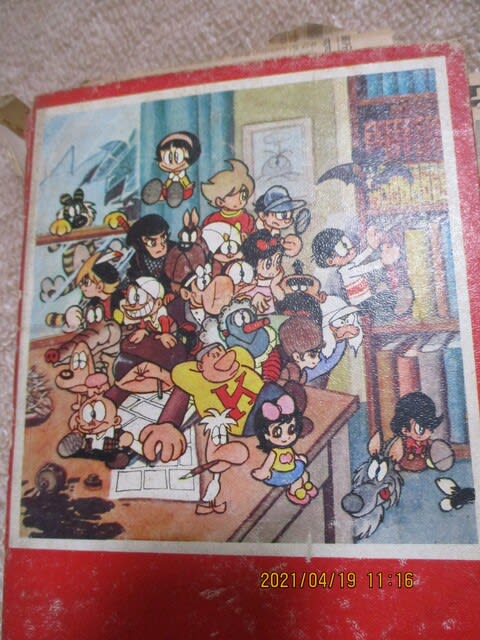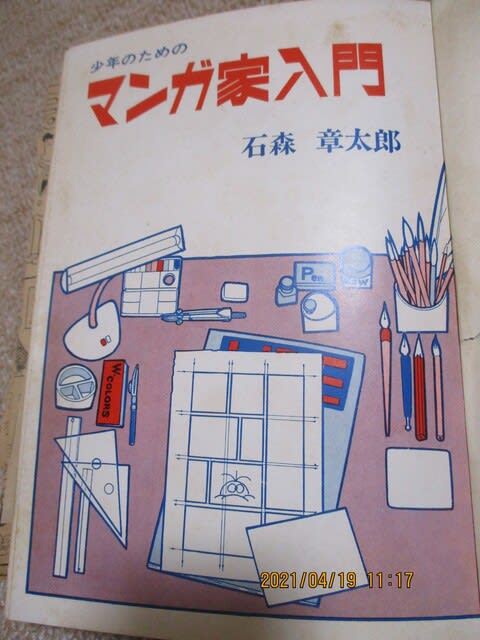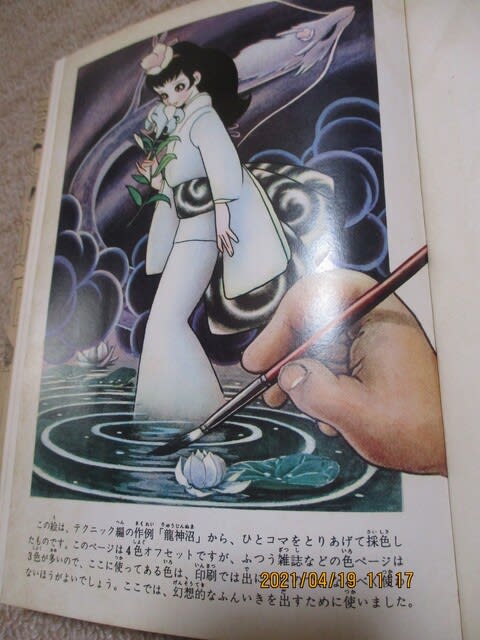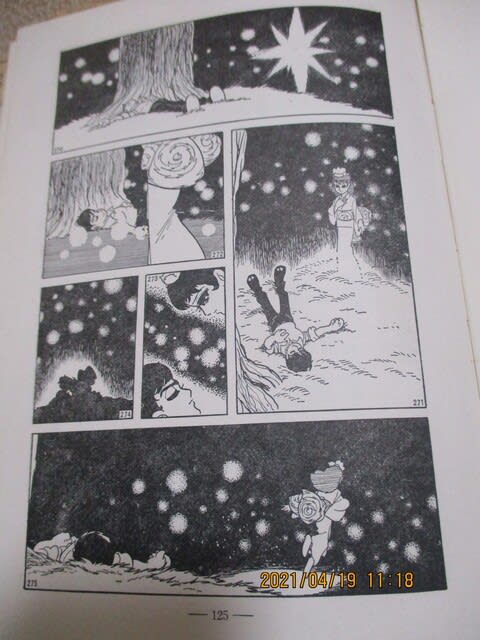本と映像の森(第3) 26 田中芳樹『銀河英雄伝説 (全10巻) ー 書き下し長編スペース・オペラ ー』<TOKUMA NOVELS>、徳間書店、1982~1987年 20210711
浜松市立城北図書館で借りて、10冊目をいまやっと読み終わりました。
「原稿用紙5300枚…212万字」(第10巻、p239「あとがき」より)
戦闘シーンは現在の陸上戦闘で1人の兵士が、「銀英伝」では1隻の宇宙船と思えばいいと思う。未来の戦闘の姿に叙述があってはいないと思う。
長い物語なのとても1回では語れない。いわゆる「スペース・オペラ」と称していて、実際「スペース・オペラ」なのだけれど、ぼくの関心は、やはり戦闘などではなく、戦争戦略・戦争戦術にあります。
それと個人がいかに組織に結合・結晶するか、ということ。
そして、おそらく一方の主人公たちの拠点イズアローンはアシモフの『銀河帝国シリーズ』の「ファウンデーション」的な未開の惑星的役割をもっている。
帝国・自由惑星同盟・フェザーン経済圏・地球教の3つどもえ・4つどっもえもアシモフの『銀河帝国シリーズ』を思わせるところがおもしろい。
そしてラブロマンス。
ぼくがいちばん好きなのは、もちろん男性ではヤン・ウェンリーとユリアン・ミンツ、女性ではフレデリカ・グリーンヒルとカーテローゼ(カリン)・フォン・クロイツェルだ。
残念なのはユリアンとカリンの熱烈なラブシーンが、ついになしに終わってしまったこと。第11巻か第12巻があればいいな。ぼくの妄想では、ヤンの後をつぎたがらず逃げまくるユリアンをひっぱたいて覚醒させる役割はカリンでなければならないのですが。
あとは「外伝」を読むこと、そしてまた「本編全10巻」をよみかえす時間があれば、「銀河英雄伝説 未来年表」を作ることになると思います。
浜松市立城北図書館で借りて、10冊目をいまやっと読み終わりました。
「原稿用紙5300枚…212万字」(第10巻、p239「あとがき」より)
戦闘シーンは現在の陸上戦闘で1人の兵士が、「銀英伝」では1隻の宇宙船と思えばいいと思う。未来の戦闘の姿に叙述があってはいないと思う。
長い物語なのとても1回では語れない。いわゆる「スペース・オペラ」と称していて、実際「スペース・オペラ」なのだけれど、ぼくの関心は、やはり戦闘などではなく、戦争戦略・戦争戦術にあります。
それと個人がいかに組織に結合・結晶するか、ということ。
そして、おそらく一方の主人公たちの拠点イズアローンはアシモフの『銀河帝国シリーズ』の「ファウンデーション」的な未開の惑星的役割をもっている。
帝国・自由惑星同盟・フェザーン経済圏・地球教の3つどもえ・4つどっもえもアシモフの『銀河帝国シリーズ』を思わせるところがおもしろい。
そしてラブロマンス。
ぼくがいちばん好きなのは、もちろん男性ではヤン・ウェンリーとユリアン・ミンツ、女性ではフレデリカ・グリーンヒルとカーテローゼ(カリン)・フォン・クロイツェルだ。
残念なのはユリアンとカリンの熱烈なラブシーンが、ついになしに終わってしまったこと。第11巻か第12巻があればいいな。ぼくの妄想では、ヤンの後をつぎたがらず逃げまくるユリアンをひっぱたいて覚醒させる役割はカリンでなければならないのですが。
あとは「外伝」を読むこと、そしてまた「本編全10巻」をよみかえす時間があれば、「銀河英雄伝説 未来年表」を作ることになると思います。