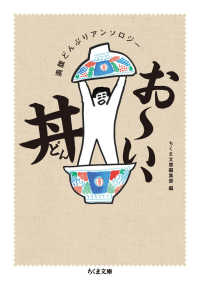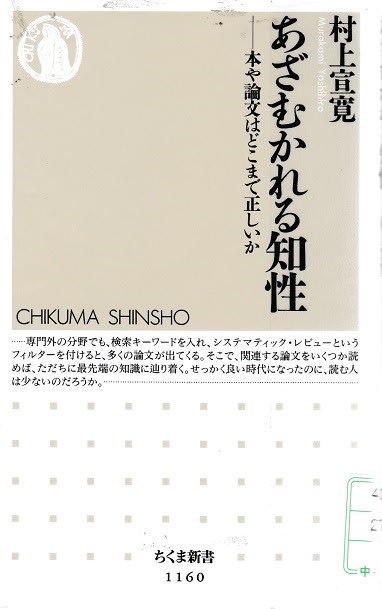鶴舞中央図書館で借りた本。
「まずいラーメン屋はどこへ消えた?」というタイトルだけで借りてしまいました。その昔、そう、私が大学生の時、それはそれは、大変「まずい定食屋」がありました。正式な名前はあったはずですが、私と友人たちは「水屋」と呼んでいました。命名フラ夫。理由は、「その定食屋で最も安心して口に入れることができるのがお冷(=水)だから」というもの。
「何故、こんなにまずい料理を出すことができるんだ?」というくらいの味。まあ、学生相手なので、確か、ご飯の大盛無料とかはあったと思うのですが、如何せん、「味付け」やら「食材」なんかがいただけない。
「まずいなら、そんなところ行かなければいいじゃん!」という方もいるかもしれませんが、入っていたクラブの部員が結構いたので、みんなで一緒に食事をするとなると、「絶対席が空いている」=「水屋」でないといけない訳で・・・
「水屋」の店頭には「犬」が繋がれていました・・・テーブルに炊飯器が置いてあって、ご飯食べ放題のトンカツ屋が満席、駅の飲食街にある和食の店も満席・・・仕方なく、私たちは「水屋」を選択するしか道が残されていませんでした。その日、「水屋の犬」は犬小屋のみで、その存在が消し去られていました。そして、、、その日の「水屋」のおすすめは「焼肉定食」でした・・・頭の中で、私たち全員、「水屋の犬」を心配してしまいました。無論、その日のおすすめを注文する仲間はいなかったのですが。
さて、話は戻って「まずいラーメン屋はどこへ消えた」のでしょう?私は、基本的に「ラーメンが大好き」なのですが、求めるレベルが高いので、巷のラーメン屋は、概ね、まずいラーメン屋となってしまいます。というか、「ラーメン通」を名乗っている人々で、中国や台湾に行って、そして、そこの路地裏で提供されているラーメンまで食している人々がどれくらいいるでしょう?
日本の有名店だけで満足し、それで「ラーメン通」を名乗ることは、もし「研究」に例えるなら、ちやほやされている分野の研究だけやって「専門家」を名乗っているのとあまり変わらないのでは・・・と思ってしまいます。ただ単に「ラーメン好き」の範囲内なら、ネットで上位の有名店だけを漁っていれば十分ですが、「ラーメン通」や「ラーメン専門家」を名乗るなら、まだまだ奥は深いわけで。私には、それができないから、ラーメンから撤収してしまいました。
それほど麺は奥が深い・・・私が到達した結論です。今から毎日ラーメンを食べたとしても、残り30年の人生だとすると、30年×365日×3食=約3万3千食べか食べることができません。
日本だけで、ラーメン店は3万2千店あるそうです。あるいは、中華料理店等合算すると約20万店との話もあります。まあ、1日3食ではなく、5食とか10食食べればその数はもっと増えるかもしれませんが、日本ですら食べきれないわけですから、世界中のラーメンを食べつくすことは不可能です。
人生をかけて食べれる回数は決まっています。だからこそ、我々は「おいしいラーメン屋」を探して、極力「まずいラーメン屋」には行きたくないのです。しかし、昔は、それを効果的に行うことができなかった。もし、仮に「スマホ」も「タブレット」も「PC」もない状況で、「ラーメン小平」という店があったとすれば、そこが「美味しい」か「不味い」か判断できます?一度、食べてみないとわからないという結論に陥ると思います。
ネットが普及する前は、まさにその状況でした。ゆえに、どれほどまずくても、一見客の需要等があったわけです。だが、ここまでネットが発展すると、事前に口コミ情報をネットで検索するため、偶発的に来ていた一見客までいなくなってしまい、まずいラーメン屋は淘汰されてしまったのです。
本当、便利な時代と思えますが、私には、逆に恐ろしい時代としか見えません。いうなれば、「ネット至上主義」。どんなに繁盛していても、ネットで叩かれると、一気にアウトになってしまう時代。先ほど述べた「ラーメン通」ぶっている人にさえ、それなりの応対をしておかないと、「あること、ないこと」書かれて、一気に炎上してしまいます。
だからこそ、ネットの検索にものってこない、肝炎のリスクを冒してまで食べた、中国上海の路地裏ラーメンの記憶が貴重だと感じています。そう、信じることができるのは、己の舌と、インスピレーションのみですから。