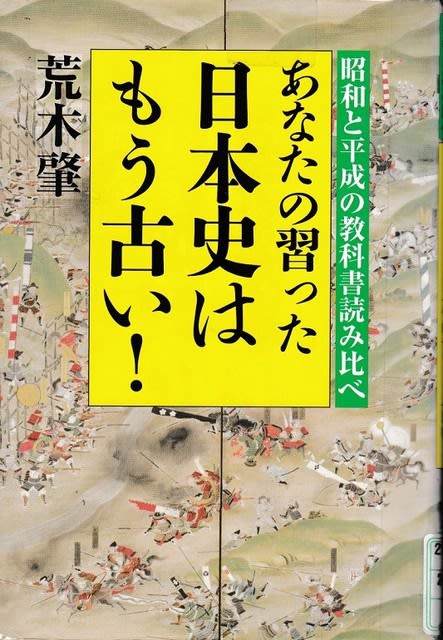鶴舞中央図書館で借りた本。
「しまむら」と「ヤオコー」ともに、「埼玉県比企郡小川町」が発祥の地だそうです。特に、「ふたつの会社の、最初の店舗所在地は、小川町の通りを挟んで、500mの範囲の中にあった」(P.8)そうです。
「しまむら」は全国47都道府県に出店しているのでご存知の方も多いでしょうが「ヤオコー」は関東を中心に出店しており、関東以外では知らない人も多いかもしれません。しかし、155店舗中85店舗を埼玉県内で出店しており、食品スーパーにおける埼玉の雄と言っていいでしょう。東京には8店舗しかありませんが、私の住んでいる小平市にもありますし、五日市街道沿いの立川市にもあります。イトーヨーカドーに行くついでに、東大和市のヤオコーにも訪れることがあり、その店舗内の美しさに魅かれます。
私にとって、比企郡といえば「吉見百穴」の吉見町なのですが、小川町も侮れませんね。その昔、埼玉県民をやっていた時もあるのですが、小川町と言えば、東武線の終点のイメージで非常に遠隔地という思いがあります。そんな町から、このような有名企業が2つも出てくるとはすごいと思った次第です。
「しまむら」と「ヤオコー」ともに、「埼玉県比企郡小川町」が発祥の地だそうです。特に、「ふたつの会社の、最初の店舗所在地は、小川町の通りを挟んで、500mの範囲の中にあった」(P.8)そうです。
「しまむら」は全国47都道府県に出店しているのでご存知の方も多いでしょうが「ヤオコー」は関東を中心に出店しており、関東以外では知らない人も多いかもしれません。しかし、155店舗中85店舗を埼玉県内で出店しており、食品スーパーにおける埼玉の雄と言っていいでしょう。東京には8店舗しかありませんが、私の住んでいる小平市にもありますし、五日市街道沿いの立川市にもあります。イトーヨーカドーに行くついでに、東大和市のヤオコーにも訪れることがあり、その店舗内の美しさに魅かれます。
私にとって、比企郡といえば「吉見百穴」の吉見町なのですが、小川町も侮れませんね。その昔、埼玉県民をやっていた時もあるのですが、小川町と言えば、東武線の終点のイメージで非常に遠隔地という思いがあります。そんな町から、このような有名企業が2つも出てくるとはすごいと思った次第です。