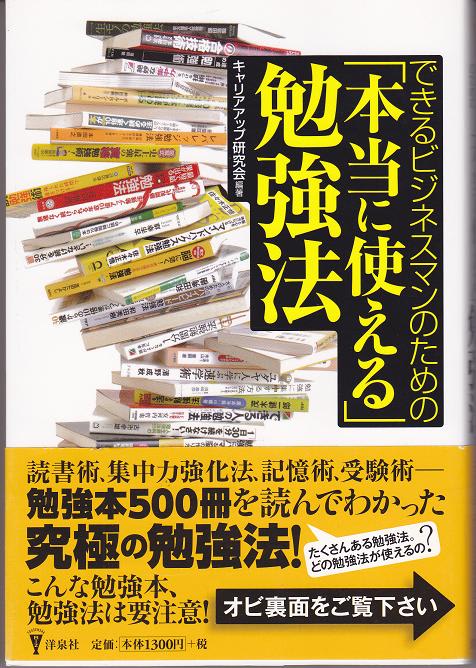本を読んでいて見つけたフレーズ。
「好きなことには誰でも120%の力が出せる。いくら仕事で疲れていても、好きなことなら苦にならない。」と書かれている。まあ、理解できないことではないし、納得感がある一文である。
ふと、思ったことは、「私の好きなこと」は何なのだろうという点。正直、自分自身、好きなことをが何かはっきりしていない。「生涯学習が趣味」とは、常々言っていることだが、その趣味は何かと聞かれると困ってしまう。
「勉強が好き」と見られがちだが、勉強するより昼寝が大好き。思い返すと「好きなことなら苦にならない。」というものは、それほどない。自分から窮地に追い込むことで学業を続けている。それが、本当に「好きなこと」といえるだろうか?
おかげさまで、「強制的学習法」を実践してきた結果、他者と比較して120%の力を発揮できる分野は多数築いてきたと思っている。しかし、自分を基準にして120%も力を出せる分野ってあるのだろうか。正直、何もせず、ゴロゴロしている方が大好きなのだから。
何かしら、120%の力を発揮できる分野を見つけたいものである。
「好きなことには誰でも120%の力が出せる。いくら仕事で疲れていても、好きなことなら苦にならない。」と書かれている。まあ、理解できないことではないし、納得感がある一文である。
ふと、思ったことは、「私の好きなこと」は何なのだろうという点。正直、自分自身、好きなことをが何かはっきりしていない。「生涯学習が趣味」とは、常々言っていることだが、その趣味は何かと聞かれると困ってしまう。
「勉強が好き」と見られがちだが、勉強するより昼寝が大好き。思い返すと「好きなことなら苦にならない。」というものは、それほどない。自分から窮地に追い込むことで学業を続けている。それが、本当に「好きなこと」といえるだろうか?
おかげさまで、「強制的学習法」を実践してきた結果、他者と比較して120%の力を発揮できる分野は多数築いてきたと思っている。しかし、自分を基準にして120%も力を出せる分野ってあるのだろうか。正直、何もせず、ゴロゴロしている方が大好きなのだから。
何かしら、120%の力を発揮できる分野を見つけたいものである。