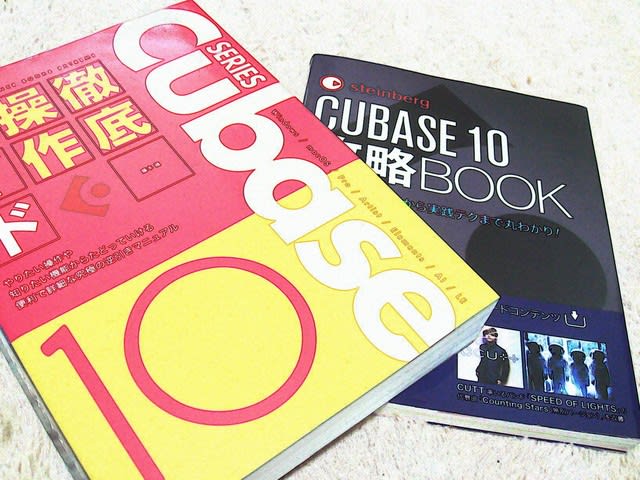またまたベースのネタで恐縮だが・・・
本日は一日中ベースを弾いていたのだ
弾いていたというよりはマルチ内のエフェクトを確認していたのだ
欲しい音を即座に作り出せるようにしておくことは音楽制作では重要なのだ
”鉄は熱いうちに打て・・・”
頭の中に浮かんだイメージを具現化できる準備が大事だと思う
今回はこんな組み合わせ

リズムマシンなどは無いが宅録には十分な性能を持っている
何よりこの小さな筐体に惹かれる
今回はサンズアンプのピック弾きをイメージしてみた
今後、ロック系の曲でも頻繁に使うことになると思う

極太弦だけにギターのそれとはピッキングが異なる

最近はベースに詳しくなってきた
ジャズベースに大別して2種類あることを知った
60年代のモデルと70年代のモデル
まったく仕様やコンセプトが異なるらしい
ちなみに私のベースは70年代の再現モデル

ストラトなどでもこのタイプのロッドを用いたモデルがある
ヘッドの書体も年代でかなり異なるのだ

本日はピックアップの高さ(前後バランス)調整なども詰めていた
ギターにもいえるが・・・
微妙に音が気に入らない場合などにピックアップの高さを
調整することであっけなく解決することも多い
不満→ピックアップ交換は早計なのだ
廉価の楽器の場合、ピックアップも含めて設計されているのだ
コスト面などで鳴りが悪い材使うことも多い
それを補うのがパワフルなピックアップの採用
良くあるパターンなのだ
この手の楽器に非力で繊細なピックアップを積んでも意味がない
ピックアップなどの断線や破損などの場合には交換も有り得るが・・・
そうではない場合にはデフォルトで何とかするのが最近の定番
そもそも交換用のピックアップなどを取り扱わない楽器店も増えた
ピックアップの交換というニーズが減ったのだ

最近はようやくベースの鳴らし方が少し分かってきた
ピックアップの前後の音量バランスなども積極的に弄ることが多い
もちろん、トーンも状況に合わせて微調整する
フルテンで使っていた頃と比較すれば自分なりの大きな成長だと思う😉