二子玉川駅(DT07、OM15)に、こんな写真が貼られていました。

かつては東急東横線の主力、今は東急大井町線の主力の9000系の赤帯復活というものです。このように宣伝されていることが、9000系の引退も近い時期にあるということを意味しています。
二子玉川駅(DT07、OM15)に、こんな写真が貼られていました。

かつては東急東横線の主力、今は東急大井町線の主力の9000系の赤帯復活というものです。このように宣伝されていることが、9000系の引退も近い時期にあるということを意味しています。
ブログについて、何処に移転しようかと考えながら、しばらくはgooで頑張っていきます。今回は、東急田園都市線の2代目SDGs TRAIN、2020系2150Fの側面です。

西は阪急阪神ホールディングス(阪急電鉄、阪神電気鉄道)、東は東急電鉄でSDGs TRAINが走っています。実物を見たのは東急電鉄の田園都市線(2020系2150F)および目黒線(3020系3122F)だけですが、東横線および世田谷線でも運行されています。

田園都市線、目黒線、東横線、および世田谷線の、それぞれ1編成だけがSDGs TRAINとなっていますので、見たり乗ったりする機会は意外に少ないかもしれません。

世間的には、鉄道と軌道は同じものと思われています。しかし、法律の世界においても鉄道と軌道は別物です。鉄道については鉄道事業法や鉄道営業法などがあるのに対し、軌道については軌道法があります。他にも鉄道と軌道の違いはいくつかありますが、最もわかりやすいのは、鉄道は原則として道路の上を走ってはならないのに対し、軌道は原則として道路の上を走らなければならない、というところでしょう。この「道路の上」という言葉の意味は広く、英語の前置詞を使えばon、つまり道路に敷いた線路の上を電車が走る場合を指すばかりでなく、同じく英語の前置詞を使えばover、つまり道路の真上に設置した高架橋の上を電車が走る場合も指します。onの例が路面電車、overの例がモノレールや新交通システムなのです。実のところ、overについての経緯は複雑であったりするのですが、その点は脇に置いておきましょう。
今回は、onの話です。東京都にある路面電車としての軌道は、都電荒川線および東急世田谷線です。ただ、世田谷線のほとんどは専用軌道であり、路面電車としての面影は若林駅のそばの踏切(環状7号線のほうです)くらいしかありません。それに対し、都電荒川線のほうはといえば、王子駅前電停から滝野川一丁目電停までの区間に道路の真上を走る部分がありますし、早稲田電停から面影橋電停の先の高戸橋交差点付近など、道路の真ん中に線路が敷かれた所があります。路面電車らしさだけで言えば都電荒川線のほうが濃いと言えます。
そこで、今回は、都電荒川線にあって東急世田谷線にないものを紹介します。

まずは早稲田電停の東側にあるホームです。都電荒川線は基本的に複線なのですが、この部分は単線で、車両の両側にホームがあります。左側が降車専用、右側が乗車専用です。これから荒川車庫前行きの8800形8803が発車していきます。

次の面影橋電停に向けて8803が走って行くのですが、右側に同じ8800形が停まっています。

右側に電車が停まっているのは、降車専用ホームに到着して乗客を降ろしたからです。実は、このホームは1枚目の写真にある左側のホームとつながっています。
複線部分にあるホームは、常時使用されている訳ではありません。右側の電車が到着した時には1枚目の写真の電車が出発を待っていたために、このホームの場所に停車して乗客を降ろした訳です。メインのホームの場所に電車が停まっていなければ、電車はそのまま単線部分に入ってきます。
このように、降車専用ホームが長く、乗車部分は単線部分にしかないという形態は、都電荒川線の三ノ輪橋電停など、路面電車の起終点では時々見かけるものですが、東急世田谷線にはありません。

荒川車庫前行きの8803が発車してから少し後に、降車専用ホームから電車が発車し、メインのホームに向かいます。この電車も8800形で、2009年から10両が荒川線で運用されています。

8802でした。行先表示が「早稲田」のままですが、果たして三ノ輪橋行きなのか荒川車庫前行きなのか回送なのかがわかりません。実は、この電車、比較的短い停車時間が過ぎてから、「早稲田」の表示のまま、面影橋電停に向けて発車しました。
東急9000系の9005Fが営業運転から離脱したという話を聞きました。次はどの編成かと思うのですが、かつての2000系である9020系も、今後数年間に大井町線から離脱することが決まっています。どの編成が最初に離脱するでしょうか。

高津駅(DT09)2番線(ホームなし)を大井町線G各停溝の口行きの東急9020系9023Fが通過していきます。かつての2000系2003Fで、田園都市線の輸送増強用として登場した2000系で唯一、1993年に8両編成で東横線に投入された編成です。程なく田園都市線に移り、活躍してきましたが、他の2000系の編成と同じく、半蔵門線の押上延伸および東武伊勢崎線・日光線への乗り入れが始まってから、長らく恵まれない境遇にあったと言えます。そして、この9023F、かつての2003Fが、2000系で最初に田園都市線の運用から離脱したのでした。

2025年3月のダイヤ改正で、東京メトロ千代田線から小田急小田原線を経由して小田急多摩線への直通運転が復活しました。「そうなると、16000系が直通運転をするのかな」などと思いながら撮影しました。各駅停車綾瀬行きの16133Fです。

年に数回、東急大井町線の尾山台駅を利用します。理由は、基本的に「再掲載:東急大井町線途中下車(3)尾山台駅(その1)」「再掲載:東急大井町線途中下車(3)尾山台駅(その2)」および「再掲載:東急大井町線途中下車(3)尾山台駅(その3)」に記したところと同じです(但し、現在乗っているのは、結局8年近く持っていた5代目ゴルフGLiではなく、T-CROSSです)。また、尾山台の商店街を歩くことを好んでいることもあります。
3月某日、尾山台に用事があったので、大井町線を利用しました。うちに帰るために駅の1番線で各駅停車を待ちます。その際に、いつものごとく、iPhone15 Proで撮影しました。

急行溝の口行きの東急6000系6102Fが通過していきます。尾山台駅に急行は止まりません。ただ、急行とは言っても大井町線での速度はあまり高くありません。大井町駅から溝の口駅までに限れば、最も速いのは二子玉川駅から溝の口駅までの区間でしょう。
6000系は7両編成6本で、このうち6101Fおよび6102Fの3号車はQ-Seat車となっています。

2番線からG各停大井町行きの東急9020系9022Fが発車し、次の九品仏駅(OM11)に向かうところです。元は田園都市線・半蔵門線用の2000系として1992年に登場した2002Fですが、2018年の秋頃に田園都市線・半蔵門線での運用から外され、10両編成から5両編成に改められた上で9020系9022Fとして大井町線各駅停車用となりました。田園都市線・半蔵門線で運用されていた時代には見ることも乗ることもなかなか難しい編成でしたが、大井町線用となってから見る機会が多くなったような気もします。果たして、いつまで大井町線を走るでしょうか。
現在も東京メトロ半蔵門線、東急田園都市線、さらに東武伊勢崎線・日光線で運用されている東京メトロ8000系は、以前にも記したように、今や東京メトロの車両で最古参の系列です。徐々に18000系への交代が行われてはいるのですが、まだまだ多くが残されているようですし、少なくとも半蔵門線および田園都市線の沿線住民であれば、見たり乗ったりする機会は多いでしょう。

高津駅(DT09)1番線を、東京メトロ8000系8106Fが準急中央林間行きとして通過していきます。8000系は、半蔵門線・田園都市線に登場してからしばらくの間、各駅停車専用でしたが、1990年代に急行および快速(いずれも半蔵門線内での各駅に停車)としても運行されるようになりました。また、この編成は初期に製造されたものであるため、最初は冷房装置が設けられておらず、8両編成でした。今でも漠然と覚えているのですが、帝都高速度交通営団の各路線や東急新玉川線(現在の田園都市線の渋谷駅から二子玉川駅までの区間)においては、たとえ冷房車であっても地下区間に入るからということで冷房は切られていました。
8106Fにいつから冷房装置が取り付けられたのかはわかりませんが、10両編成化されたのは1990年代に入ってからのことです。

6回目の、南町田グランベリーパーク号の東急2020系2137Fです。

ホームドアのために完全に見えませんが、Grandberry Parkの可愛らしいデザインが施されたヘッドマークが付けられています。2020系に合っています。

ライナスとウッドストックです。ライナスと言えば、安全毛布とカボチャ大王が思い浮かびますが、そうかと思えば哲学的な、あるいは格言的なフレーズを口にします。これが4コマ漫画に独特の味わいと品格を与えています。ただ、聖書からの引用も多いので、我々にはわかりにくい部分もあることは否定できません。
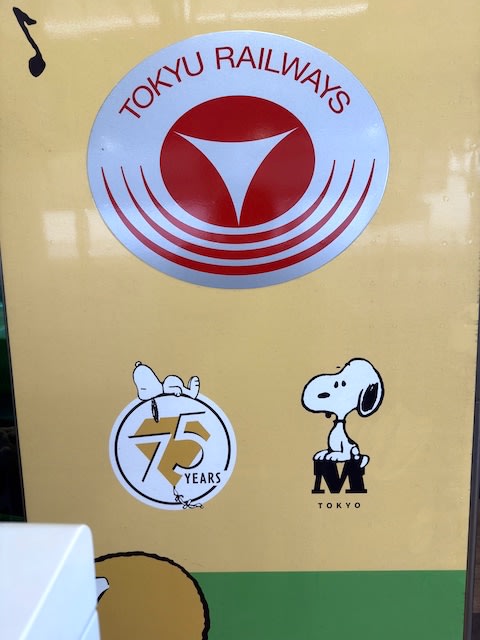
南町田グランベリーパーク号ということからすれば、やはり、この世界一有名なビーグル犬が不可欠です。ちなみに、二子玉川ライズのオープン時からスヌーピータウンがあります。

車内も南町田グランベリーパークの広告だけです。iPhone15 Proで撮影していますが、さすがに空いていないと無理でしょう。結構楽しめます。しかも、2020系にはテレビ画面もあります。次はいつ行こうかな、などと思いながら見ています。
東急線には、1980年代からTOQ BOX号、TOKYU CABLE TV号、BUNKAMURA号、Shibuya HIkarie号などと、ラッピングトレイン、一編成まるごと一社独占広告という列車の伝統があります。8500系8637FがBUNKAMURA号であった時には、乗る度にコンサートや展覧会などの広告を見て「これ、行ってみたいな」などと思っていました。実際に行ったことも何度となくあります。
以前、このブログに「2代目うしでんしゃ 横浜高速鉄道Y000系デハY011+クハY001」を掲載しました。その時は長津田駅の構内または長津田検車区の一角に留置されているところを紹介したのですが、今回は営業運転中の様子です。

長津田駅(KD01、DT22)7番線に「うしでんしゃ」が入線しました。横浜高速鉄道Y000系クハY001+デハY011です。勿論、長津田行きとしてです。撮影日の何時から何時までかはわかりませんが、この編成が長津田駅とこどもの国駅(KD03)とを往復しているのでした。

上のパンタグラフ付きの車両はデハY011です。もうじき停車するところです。
長津田駅において、この7番線のみホームドアが設置されていません。設置の予定もないようです。また、こどもの国線の改札口はこの駅にないので、ここから恩田駅(KD02)またはこどもの国駅まで切符を買わずに乗った場合には着駅で精算することとなります。なお、田園都市線とJR横浜線には自動改札機が設けられています。

この写真ではわかりませんが、到着してすぐに行先表示が「こどもの国」に変わっています。牛の顔が正面の下方に描かれています。初代の「うしでんしゃ」とは少しばかり顔つきが違うようにも見えますが、連結器の真上にある鼻の色が違うだけかもしれません。

別記事でも書きましたが、「うしでんしゃ」は、元々、2018年10月11日から2020年3月31日までの実施が予定されている「こどもの国線楽しモウ」というイベントの一環で運行されていました。期間限定だったのですが、好評であったようで、編成を変えた上で現在まで走り続けています。
こどもの国線には、もう一編成のラッピング電車である「ひつじでんしゃ」があります。クハY002+デハY012の編成ですが、こちらのほうの営業運転をまだ撮影したことがないので、時期を見計らって撮りに行きたいものです。

出発の時間となり、恩田駅およびこどもの国駅に向けて発車しました。すぐに急カーブがあるため、ゆっくりと走って行きます。
動物のラッピングと言えば、世田谷線の「幸福の招き猫」こと300系308Fがあります。「幸福の招き猫」を撮影する人は多く、鉄道ファンでない人々にも世代などを問わず愛されているのですが、この「うしでんしゃ」と「ひつじでんしゃ」を撮影する人はあまりいないようです。路線の違いでしょうか。
都営地下鉄大江戸線、『鉄道要覧』に倣えば都営地下鉄12号線大江戸線は、都庁前駅から東新宿駅、春日駅、両国駅、大門駅、六本木駅、新宿駅を経て都庁前駅へ戻り、中野坂上駅、練馬駅を通って光が丘駅に至る、全長40.7キロメートル、日本最長の地下鉄路線です。ちなみに、2番目に長いとよく言われるのは僅差で横浜市営地下鉄ブルーラインであると言われるのですが、正式には1号線(関内駅〜湘南台駅、19.7キロメートル)および3号線(関内駅〜あざみ野駅、20.7キロメートル)に分かれます。そのため、大江戸線が日本最長の地下鉄路線の座を失うことはないでしょう。
また、大阪メトロ長堀鶴見緑地線に次ぐ鉄輪式リニアモーターカーの地下鉄であるため、都営地下鉄では唯一、他の鉄道会社の路線との相互乗り入れが行われていません(東京メトロの路線を含めても銀座線および丸ノ内線くらいです)。

12−600形の12-871Fです。行先表示が(私が知る限りでは都庁前駅→光が丘駅などを除いて)「◎◎方面」となっているのは、首都圏において大江戸線だけでしょう。勿論、光が丘行きです。また、この「◎◎方面」は数秒ごとに変わります。環状部分では乗り間違えが起こりがちなので、そのようになっているのでしょう。山手線でも同様の案内表示がなされています。もっとも、環状線だから乗り間違えが多くなるとは言い切れませんし、私自身、島式ホームを採用している駅で乗り間違えそうになったのは日比谷線の霞ヶ関駅くらいです。