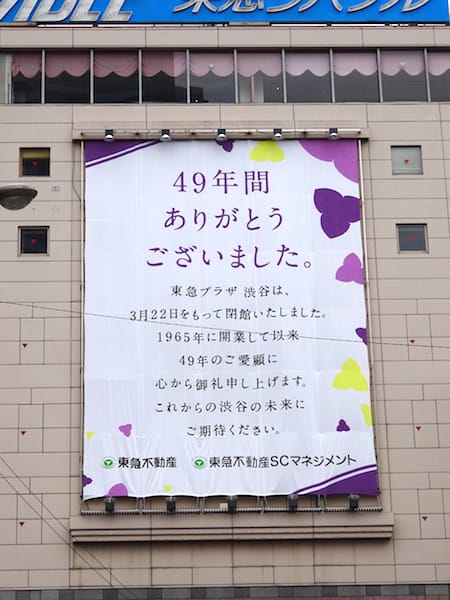2014年10月16日から2015年4月19日まで毎日投稿しましたが、一週間ほど休みました(勿論、仕事はしています)。これからしばらくの間、一週間に一度程度を目処にしようかと考えています。
たまたま、秋田魁新報社のサイトで4月24日付の「社説:赤字の秋田内陸線 路線維持、広範な議論を」(http://www.sakigake.jp/p/akita/editorial.jsp?kc=20150424az)を見つけたので、一週間ぶりに書いてみようと思い立ちました。以前から存続か廃止かが議論されている鉄道路線の一つで、全国のローカル線、とくに第三セクターの路線が抱える問題が改めて浮き彫りにされているためです。
秋田内陸縦貫鉄道は、北秋田市に本社を置く第三セクター会社です。同社の公式サイトによれば、創立は昭和59年10月31日、営業開始は昭和61年11月1日です。上位株主は秋田県、北秋田市、仙北市、秋田銀行、北都銀行、東北電力、社団法人北秋田建設業協会、社団法人秋田県仙北建設業協会、秋田商工会議所、田沢湖高原リフトですが、比率などは全く示されていません。そこで秋田魁新報社説に戻れば、秋田県、北秋田市および仙北市が合わせて80%ほどを出資しているとのことです。
鉄道以外の事業も行っているとのことですが、やはりメインは鉄道で、秋田内陸線という、鷹巣~角館の94.2kmの路線を営業しています。元々、鷹ノ巣(国鉄→JR東日本の駅名表記)~比立内の国鉄阿仁合線、角館~松葉の国鉄角館線を受け継ぎ、鉄建公団が建設していた比立内~松葉を引き継いだ路線です。角館線が第一次特定地方交通線、阿仁合線が第二次特定地方交通線でしたので、利用客が少ないことは当初からわかっていたのでしょう。ただ、鷹巣~角館は大正時代の鉄道敷設法別表第13号に登場する路線であったため、赤字路線であっても建設が進められてきたのでした。この鉄道敷設法という法律こそが全国の赤字ローカル線問題の元凶とも言える点には留意しておく必要があるでしょう。
秋田魁新報の社説によれば、秋田内陸縦貫鉄道の2014年度経常赤字は2億円を超えており、これは3年ぶりのことです。2010年、秋田内陸縦貫鉄道、秋田県、北秋田市および仙北市はいわゆる四者合意を行っており、秋田内陸縦貫鉄道の赤字を補填するために秋田県、北秋田市および仙北市が毎年合計2億円を拠出することとしています。この2億円というラインを超えないことが、秋田内陸縦貫鉄道の経営目標とされているようです。
社説には書かれていませんが、秋田内陸縦貫鉄道については、以前にも存続か廃止かで議論がなされました。2008年には当時の秋田県知事、北秋田市長および仙北市長が、2012年まで存続させることで合意をしています。2012年を迎えて存続が決まったのは、赤字が2億円を下回ったからで、上記の経営目標は一応達成されたと判断されたのです。しかし、これは秋田内陸線を走っていた急行「もりよし」号を2両編成から1両編成に減らしたこと、および、普通列車を減便したことによるものです。
現在の秋田内陸線の状況からして、今後、再び赤字額を減らして存続することは難しいのではないかと考えられます。社説では「そもそも赤字が続くようでは会社は生き残れない。秋田内陸縦貫鉄道はその重みをいま一度かみしめ、一層の経営努力をしてもらいたい」と書かれていますが、それほど簡単な話でもないでしょう。この種のニュースとなると必ず「経営努力」が叫ばれますが、その必要性が認められることは当然としても(例えば、現業従業員の人件費はカットしても、天下りなどの役員の人件費をカットしなかったり、カットしていたとしても不十分であったりしたのでは、お話になりません。従業員の人件費を確保して役員の人件費をカットするほうが、はるかに理にかなっています)、社会情勢を抜きにしては語れません。第三セクターに固有の問題も様々ですが、ここでは議論の対象から外して考えていきます。
まず、秋田内陸線には29の駅がありますが、このうち社員配置駅(有人駅)は3つだけであり(鷹巣駅、阿仁合駅および角館駅)、委託駅が3つある(合川駅、米内沢駅および阿仁前田駅)ほかは全て無人駅です。委託を解除して全て無人にするくらいしかできないでしょう。現在の社員配置駅を見直すということも考えられますが、乗降客数の他、いくつかの要素を考え合わせて決めるしかないはずです。
駅の数を減らすことも検討に値するかもしれません。典型的な例はJR北海道で、函館本線、宗谷本線、石北本線などの路線にある、乗降客数がゼロまたは僅少である駅を廃止しています。逆にこれが上手くいかなかったことの例が、2006年4月に廃止された北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線で、2000年頃に様舞駅および薫別駅を廃止しようとしたところ、地元の反対を受け、結局は廃線時まで存続したのですが、利用客は増えなかったようです。
ダイヤ改正でいっそうの減便を進めるという手もあります。2012年度に赤字額が減少したのもこの方法によるところが大きかったのでした。秋田内陸線の営業区間が長いだけに、経費がかかることは否めませんから、経費削減を目指すのは理解できます。しかし、減便は一時的な効果しか持たないでしょう。利便性も落ちますし、収入を得る機会も減ります。国鉄末期の赤字ローカル線の多くに見られたように、利用したくともできないようなダイヤでは最初から沿線住民などの選択肢に入りません。
他に、青い森鉄道のように上下分離方式を採用する手もあります。問題は秋田県などの財政状況ですが、本気で存続を考えるなら選択肢に入ります。線路施設などを秋田県などが保有すれば、秋田内陸縦貫鉄道は固定資産税などの負担をしなくて済みます(現在の状況についてはよくわかりませんが)。このようにすれば、2億円とまでは行かなくとも、一定の金額を県や市が拠出するのと結果的に同じような効果がもたらされることも考えられます。
しかし、どれほど「経営努力」を行っても、秋田内陸線の存続は難しいものと思われます。残念ながら、今後何年かの間に廃止することも検討せざるをえなくなることでしょう。
そもそも、秋田県全体の人口が減少しています。朝日新聞社が4月25日3時付で「秋田)県人口、戦後初めて103万人割れ」(http://www.asahi.com/articles/ASH4S5F1ZH4SUBUB00V.html)として報じているところによれば、同県の2015年4月1日現在の人口は102万7091人で、2014年4月1日時点の人口より13673人減少しています(率にして1.31%)。2014年6月に104万人台を割り込み、今年になってから103万人台も割り込んだ訳です。同記事に書かれているところによれば、自然動態(出生数から死亡数を引いた数)は−8960人、社会動態(転入数から転出数を引いた数)は-4713人で、今年3月には転出者が6379人、このうち秋田市については1534人でした。あと2年か3年で100万人を下回る可能性も出てくる状況です。
人口が減少すれば、モータリゼイションの進行云々に関わりなく、鉄道の利用者は減少します。秋田内陸線の利用客は、比立内~松葉が完成し、阿仁合線(秋田内陸北線)、角館線(秋田内陸南線)を統合して秋田内陸線として全線開業した1989年度がピークで107万人でした。1年間でこの数字ですから、粗い計算をすると一日あたりの利用客数は約2932人です。その後は一貫して減少し、2013年度には33万人(一日あたりで約904人)となりました。2014年度については4月から12月までの分しかわかりませんが、25万人余であったとのことです。
鉄道事業の収入のうち、特に重要とされるのが定期券利用客数です。大手私鉄も含めて全国的に定期券利用客が減っているとのことですが、中小私鉄(多くの第三セクター鉄道もここに分類されるべきでしょう)では非常に深刻です。モータリゼイションの進化・深化は容易に想定できますので、これを頼りにすることはできないでしょう。そうなると割安な通学定期券利用者に頼るしかないのですが、少子高齢化で高校生(など)の数が減少しています。また、秋田内陸線の場合、かなり曖昧な記憶ですが、或る殺人事件がきっかけとなって小学校などで鉄道利用からスクールバス利用に切り替えられたという話があったはずです。
秋田魁新報社の社説では「観光利用も思うように伸びていない」と書かれていますが、これも当然のことでしょう。首都圏や京阪神地区などであれば別ですが、多くの地方では、せっかくの観光地でも公共交通機関を利用しづらくなっています。私自身、7年間も九州は大分県に住んでいた経験を持っていますから、この点はわかります。自家用車を利用して訪れることが前提となっていますから、遠方より訪れたくとも難しいのです。外国からの観光客など、一定のツアープランを組んで貸し切りバスを利用するなら行きやすいでしょうが、そうでなければ面倒なだけです。公共交通機関が存在しない地域もあるでしょうし、存在するとしても貧弱で、利用しづらいのでは、自家用車利用の日帰り客しか見込めません。
〔ついでに記しておきます。秋田内陸線の時刻表を参照してみると、角館駅からの上り(鷹巣方面)列車は10本で、朝は6時59分発(阿仁合行き)の次が9時23分発(鷹巣行き)となっており、13時58分発(鷹巣行き)の次が16時48分発(鷹巣行き)となっています。また、鷹巣駅からの下り(角館方面)列車も10本で、朝は7時5分発(角館行き)に始まりますが、9時台、11時台、13時台および15時台の列車がありません。〕
既に秋田県、北秋田市および仙北市は、秋田内陸縦貫鉄道の存続に50億円以上という金を費やしています。問題はここからで、多額の「公費」が投じられているからには、それなりの効果が求められることとなります。抽象的にお題目を唱えるだけでは意味がない訳で、具体的な需要がないのであれば、廃止するのが筋である、ということにもなるでしょう。秋田魁新報社の社説によれば、2014年12月に、秋田県議会に設けられた「第三セクター等の経営に関する調査特別委員会」が報告書をまとめており、秋田内陸線については「地元の熱意を見極め」た上で、成果がなければ廃止などを検討すべしと述べているようです。そして、抽象的なお題目の下に「公費」の投入を続けていても秋田県民の理解を得ることができないという趣旨の指摘も行っています。
そして2015年度に、秋田県は沿線住民の3000人に対してアンケート調査を行うことにしています。結果次第では廃止ということにもなるでしょう。ただ、こうなると、公共交通機関空白地帯が出現することも考えられ、地域の荒廃がいっそう進むことにもなりかねません。
他方、これは「炎上」覚悟で申し上げますが、「地元の熱意」をどこまで考慮すべきであるかということについても疑問が残ります。これまでの路線存廃論議でも「地元の熱意」が実を結び、存続が決まったという事例があります。その中には、運営会社、地元住民などの「熱意」や努力によって利用客が増えた路線もあるでしょう。しかし、存続が決まってから「地元の熱意」が急速に冷めることも考えられます。そうなると、路線の危機はいっそう深刻になるばかりで、手も付けられない状況になることでしょう。アンケート調査でどのように「地元の熱意」を汲み取るのか、そもそもどのようにして「地元の熱意」を測るのかが問われます。