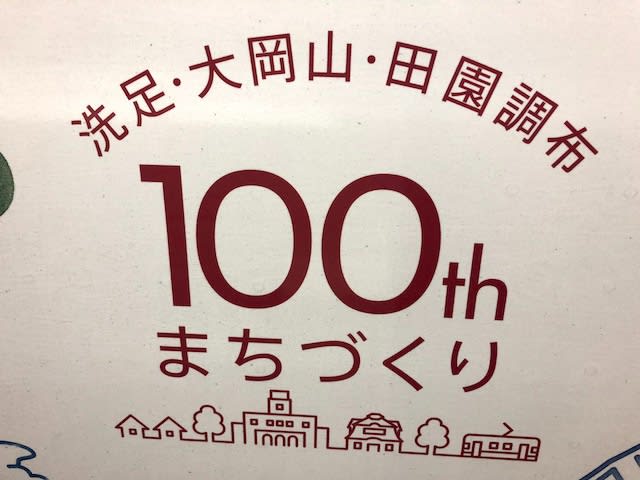今日(2018年10月20日)の朝日新聞朝刊37面14版に小さな記事が載りました。「相続後譲渡 兄弟の権利侵害」です(https://digital.asahi.com/articles/DA3S13731636.html)。
最初に、かなり気になったのは、この記事では一審、二審とも上告人の請求を棄却しており、最高裁判所第二小法廷も上告人の請求を棄却したと書かれていることです。これは誤っているものと考えられます。
同じ判決に関する記事として毎日新聞社の「〈最高裁〉相続分無償譲渡は『贈与』 遺留分請求認める」(2018年10月19日21時46分配信。都合上、次のアドレスを示しておきます。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00000112-mai-soci)がありますが、こちらでは判決の主文が書かれていません。
裁判所ウェブサイトには「平成29(受)1735 遺留分減殺請求事件 平成30年10月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所」として掲載されており(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter[recent]=true)、実際に判決文(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf)をみると「原判決を破棄する。/本件を東京高等裁判所に差し戻す。」と書かれています(/は原文改行箇所)。
つまり、(一審はわかりませんが)二審は上告人の請求を棄却したのに対し、最高裁判所第二小法廷は東京高等裁判所に審理のやり直しを命じた訳です。
さて、この判決の内容です。事案は、おおよそ次の通りです。
上告人X、被上告人Y:いずれもAおよびB(夫婦)の子。
①Bの死亡による相続の際に、AおよびD(Yの妻にしてAおよびBの養子)は、Bの遺産についての遺産分割調停手続において、まだ遺産分割が終わらないうちにYに各々の相続分を譲渡し、遺産分割調停手続から脱退しました。
②その後、Aは生前に、自らが有する全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言をしました。
③それから数ヶ月が経過し、Bの遺産について、X、YおよびC(Bの相続人)の間で遺産分割調停が成立しました。結果として、Xは建物を、Yは土地、建物などの財産を取得しました。
④数年が経過し、Aが死亡しました。その法定相続人はX、Y、CおよびDです。②に示したように、Aの財産は全てYが相続することになっています。
⑤これに対し、XはYに対し、Aの相続に関して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしました。裁判におけるXの請求は、Yが③によって取得した不動産の一部についての遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続などを求めるというものでした。
本件における争点は、①に示した相続分の譲渡が、Aの相続において、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与に該当するかということです。最高裁判所第二小法廷判決が示している関連条文をあげておきます。
民法第903条(見出しは「特別受益者の相続分」)第1項:「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」
同第1044条(見出しは「代襲相続及び相続分の規定の準用」:「第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。」
東京高等裁判所の判決の概要は、最高裁判所第二小法廷判決に示されているところによれば、次の通りです。
「相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから、譲渡人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できない。また、相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず、譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないものである。したがって、本件相続分譲渡は、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらない。」
しかし、最高裁判所第二小法廷判決は、次のように述べて東京高等裁判所判決を破棄します(下線は、裁判所ウェブサイトに掲載されている判決文に引かれているものです)。
「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。」
「そして、相続分の譲渡を受けた共同相続人は、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり、当該遺産分割手続等において、他の共同相続人に対し、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることとなる。」
「このように、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは、以上のように解することの妨げとなるものではない。」
「したがって、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する『贈与』に当たる。」
東京高等裁判所判決の論理は(あくまでも最高裁判所第二小法廷判決の要約に従えば、という前提ですが)やや単純に過ぎると思われます。「最終的に遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになる」という部分がありますが、この「遡及効」に引き摺られたような印象を受けます。付け加えるならば、「相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず、譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないものである」というのですが、遺産分割協議や遺産分割調停を行っていれば、積極財産(プラスの財産)、消極財産(マイナスの財産、借金などの債務)の価額について、厳密とは言えなくともおおよそのところはわかっているはずです。或る程度はわかっているからこそ、遺産分割調停手続が終わらないうちに相続分の譲渡を行うはずである、ということです。調停手続が行われたということは、遺産分割協議が調わなかったからということでしょう。そうであれば、分割協議の際に相続財産の価額はわかっているはずです。仮にわからないとしても、相続分の譲渡・譲受を行った相続人間に共通の理解なり方針なりがあるからこそ、このようなことを行っていると考えるのが自然でしょう。
一方、民法第903条第1項を見直すと、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」とあり、遺産分割調停の最中における相続分の譲渡・譲受が該当するのかという疑問も湧くところです。ただ、相続分の譲渡・譲受が行われたことに変わりはないので、解釈としては最高裁判所第二小法廷判決のほうが妥当であろう、と考えられます。