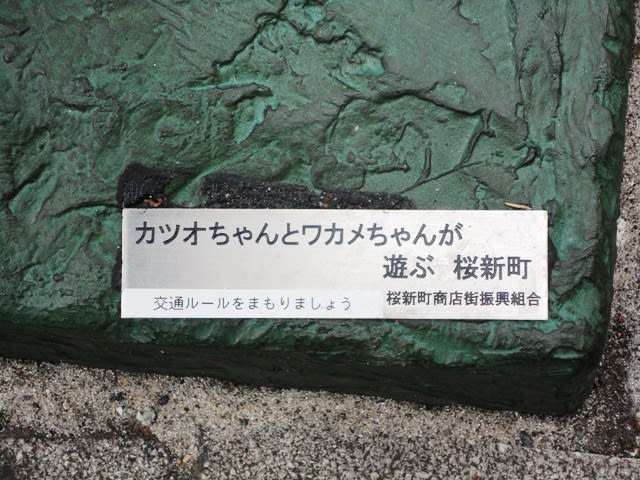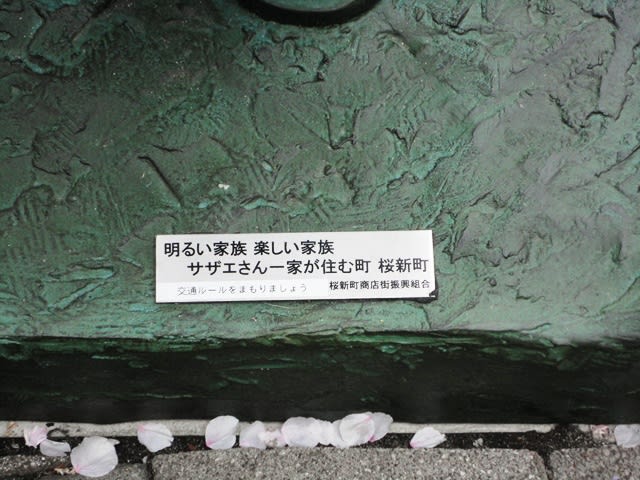今日の日本経済新聞朝刊34面12版に「東京女学館大、16年に閉校 来春募集停止 ブランド力生かせず」という記事が掲載されています。私は大学に勤務する者ですので、目が行きました。
東京女学館というと、渋谷駅から学03系統の都バスに乗って終点の一つ手前にある学校がすぐに思い浮かびます。非常勤で仕事に行く國學院大学の近くにあるからですが、渋谷区広尾にあるのは小学校、中学校、高等学校であり、大学はそこにありません。町田市鶴間にあるとのことで、最寄り駅は田園都市線の南町田です。
この大学は、正直なところ、あまり知名度は高くないと思われます。関東地方以外にお住まいの方であれば、おそらく耳にしたことはないでしょう。高校は比較的に有名だそうで(私は、国学院大学で非常勤の仕事を始める2004年6月まで全く知りませんでしたが)、元をたどると伊藤博文や渋沢栄一の名前もあがる「女子教育奨励会」に至ります。1956年に短期大学が開かれ、2002年に4年制大学となったのですが、その年から11年連続で定員割れとなっていました。上記記事によると、首都圏にある他の女子大よりも学費が高いそうです(定員割れの理由はそれだけでなさそうですが)。
2011年度、日本全国の私立大学の数は572であるそうです(日経の記事によるのですが、4年制大学だけなのでしょう)。そのうちの223校で定員割れが起きており、これはおよそ4割にあたります。2009年度の決算で赤字となった大学も226校あり、4割を超えています。「厳しい時代だ」と、改めて感じます。
悪いことに、こと学校(大学は勿論、高校なども含みます)だけに関して言えば、国公立学校よりも私立学校のほうが、統合再編などを行いにくいという現実があるようです。武蔵工業大学と東横学園女子短期大学が統合して東京都市大学になったという例がすぐにあげられますが、これは同じ学校法人の経営下であったから比較的容易に進んだとも言えます。国公立学校はまさにこの典型で、経営主体が同じところ(国、同一地方公共団体)であれば、統合再編は楽に進められます。県立高校が代表例で、神奈川県立の高校は再編が進んでいます。川崎市内ですと川崎南高校が川崎高校に統合されていますし、柿生高校と柿生西高校が統合して麻生総合高校になっています。こう書いてしまいますとどこからか矢が飛んできそうですが、これまでのところ、再編の対象となっているのは進学実績に乏しく、偏差値の低い学校です。実際に、神奈川県は進学などについて重点的に支援する高校を選定しており、川崎市内では多摩高校だけが選ばれています。
また、国立大学では、2003年10月に東京商船大学と東京水産大学が統合し、東京海洋大学になっています。同時期に統合した国立大学は少なくなく、私が勤務していた大分大学も大分医科大学と統合しています。独立行政法人化されてからは統合再編の例がないようですが、今後もありうるものと思われます。
統合再編と言えば、首都大学東京を忘れてはなりません。東京都立大学などの都立学校が統合されて誕生したのですが、様々な問題が生じ、多くの教員が東京都立大学を離れています。統合時まで東京都立大学が目黒区にあれば、話は違っていたのではないかとも思うのですが、どうなのでしょうか。世間のうわさ話の程度ではありますが、都立大学が都庁移転と同じくらいの費用をかけて目黒区から八王子市へ移転したのが失敗の元である、という話はよく聞かれました(移転でレベルが下がったという話は、他にもたくさんあります)。
私立大学の場合、学校法人の合併・吸収合併ということになります。高校くらいまでであればよくあるのですが、大学ではあまり例がありません。学校法人の性質は財団法人ですので、社団法人のように話が進まないのかもしれません。しかし、今後はそうも言っていられません。学校法人の合併が進まなければならなくなるのでしょう。私もその中に身を置いているだけに、考えておかなければなりません。