3月16日の土曜日、写真展「ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー 二人の写真家」を見るために横浜美術館へ行った。
1936年から37年にかけて二人の写真家が共和国軍側からスペイン内戦を取材した写真の前で、中学生らしい少女にその母親がこれらの写真が撮影された時代の歴史を小声で教えていた。
左派の共和国軍、フランコが率いる右派の反乱軍、共和国軍を支援するソ連、フランコを支援するドイツやイタリア。共産主義勢力とファシスト勢力のぶつかり合い。共和国支援のために編成された外国人義勇兵による国際旅団。ヘミングウェイ、オーウェル、キャパたちによる内戦の報道。代理戦争としてのスペイン内戦。
おそらくは高校か大学の西洋史の先生だろうか。母親は行き届いた説明を娘さんにしていた。幸せな娘さんだ。ジャワハルラル・ネルーが獄中から一人娘のインディラに長い手紙を書いて世界の歴史を教えたように、この母親は娘さんに口うつしで歴史を教えているのだった。
それはさておき、私には1938年キャパが中国に渡り、漢口の中国共産党中央委員会本部で撮影した周恩来の写真が興味深かった。周恩来40歳の時の写真である。
キャパは1954年には日本を訪れ日本の風景写真を撮った。そのあと、東京からインドシナ戦争の現場へ取材に向かい、地雷にふれて死んだ。
キャパが日本で撮影した日本の風景は凡庸である。報道写真が人の心をわしづかみにするのは、写し撮られた絵の向こうにある歴史的事件の訴求力であることをあらためて痛感する。報道写真家にとっての核心は、機材でもなく、撮影術でもなく、時代を象徴する現場にいかにして立ち会うか、その才覚と運である。戦争の現場に立たないキャパの名は時間とともに色あせ始める。だからキャパは第1次インドシナ戦争の現場に跳び込まねばならなかった。
カール・マルクスの肖像のそばに立つ40歳の周恩来の写真が私を釘付けにするのも、このエレガントな壮年の周恩来が、やがて新中国建国達成から1976年の死に至るまで、『周恩来秘録』などに書かれているような毛沢東との危険な関係から生じた権力の暗部で、生き延びるために砂を咬むような思いで苦闘を続けねばならなかった――新中国は周恩来にとって作品であり、その完成に向けてわが身を削ってでも描き続けねばならなかった――その悲劇に思いがいたるからである。
(2013.3.17)











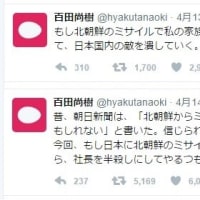













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます