ドイツ、イタリア、日本で、ナチズム・ファシズム・軍国主義が政治権力を握った1930年代に、アメリカ合衆国の政治学者チャールズ・メリアムが『政治権力――その構造と技術』(邦訳は東京大学出版会)を書いた。
メリアムは同書の中で、権威主義的政治権力は2つの基盤に立っていると説明した。「ミランダ」と「クレデンダ」である。
ミランダは国家、国旗、巨大な記念碑・構造物、権力にまつわる神話や荘重な儀式、軍服のような画一的な制服といった、理性を超えた崇拝心をかき立てる装置の事である。ヒトラーが世界に冠たるドイツ民族とその頂点に立つヒトラー自身の優越性を誇示しようとした1936年のベルリン・オリンピック大会がミランダの好例である。
クレデンダは「イデオロギー」のような理論的な(合理的であるかどうかは別にして)装いをまとった信条をいう。軍国主義時代の日本の「八紘一宇」やナチスの「アーリア民族の優越性神話」などがこれにあたる。権威的政治権力はミランダとクレデンダを巧みに使って、国民の崇拝感情をあおり、権力維持に利用してきた。
1930年代には時代を反映した政治理論だったが、現在ではマイナーな理論になっている。というよりも、権力者が用いるシンボル操作のなかの初歩的な技術の1つになっている。
訪米した日本の安倍総理大臣がアメリカのトランプ大統領に、新しい天皇の即位はスーパーボウルの100倍以上の行事だと言ったそうだ。天皇交代、元号変更、トランプ大統領訪日という一連のイベントを日本の首相は「ミランダ」として利用する。
このようにミランダとクレデンダは、政治権力が自らの権力基盤の強化や永続を目的に利用するものであるというのが政治学の通念だが、これとは逆の理論もある。
クリフォード・ギアツというアメリカの文化人類学者が書いた『ヌガラ――19世紀バリの劇場国家』(邦訳、みすず書房)は米国で出版された1980年から日本語訳が出た1990年以降にかけて、大きな話題を呼んだ。この本の第1章に、当時あまりにも有名になった次の言葉がある。
「王と君主が興行主になり、(ヒンドゥーの)僧が監督を務め、農民が脇役・舞台装置係・観客になる劇場国家だった」。19世紀のバリでは島内が多くの小王国(ヌガラ)に分れていた。それぞれのヌガラで外国人の目に異様に映ったのは儀礼と祝祭の多さだった。大掛かりな君主たちの火葬の儀式、ヒンドゥー寺院への奉納などに多くの富が費やされた。しかし、それは政治的な目的のためにおこなわれた行事ではなかった。行事遂行自体が目的だった。そのために国家(ヌガラ)があった。社会的不平等・抑圧もあったが、不満は政治に向けられることはなく、壮麗な祝祭のなかで昇華され、浄化されるのがバリのヌガラ社会のありかただった。「華麗な行事のために権力があった。権力のために行事があったのではない」。ヌガラの仕組みをギアツはそう言い切った。
このような権力の地位にある者が壮麗な国家的儀礼をおこなうことで、結果として、支配者たることができるという仮説は、天皇が三種の神器を代々受け継ぎ、国家の祭礼を取り仕切ってきた日本の天皇制にも当てはまるところがある。
2019年4月から5月にかけての天皇の交代とそれに関連する元号の変更という行事は、権力によるミランダ操作なのだろうか。それとも、天皇が興行主、官僚が舞台装置係、マスメディアが囃子方、大衆が観客になる、現代版日本劇場国家のスペクタクルなのだろうか。
(2019.4.30 花崎泰雄)











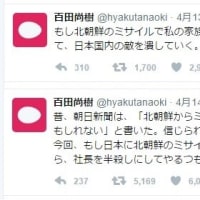













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます