第1次世界大戦が終わりベルサイユ体制のもとで国際連盟がつくられた。ベルサイユ体制構築を主導した当時のウッドロー・ウィルソン米大統領は米国の連盟加盟を主張したがモンロー主義を信奉していた米議会が反対し。結局、米国は国際連盟に加入しなかった。
第2次世界大戦後、米国は発足した国際連合に加盟し、常任理事国となって世界を取り仕切った。朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタン戦争、湾岸戦争、イラク戦争を始めた。モンロー主義など忘れてしまったように見えた。共産主義やイスラムの教義の拡大に恐怖を感じたせいである。ベトナムか共産化すれば、勢いを得た共産主義勢力がタイを脅かし、マレーシアに侵入し、インドネシアが共産圏に入り、やがて共産主義がオーストラリアやニュージーランドに迫る。このアジア版ドミノ理論を米国は世界に向けて喧伝し続けた。振り返ってみれば、アジア版ドミノ理論はいま流行のトランプ言説と同じような根拠の乏しい主張だった。
2000年ほど前のパックス・ロマーナ、150年ほど前のパックス・ブリタニカと並ぶパックス・アメリカーナの時代を我々は見たのだが、世評ではアメリカの覇者としてのエネルギーは枯渇し始めているとされる。超大国はその力を世界に示し続けるために財力を必要とする。第2次世界大戦終結から80年、米国が息切れし始めたとしても不思議ではない。パックス・ロマ―ナは200年、パックス・ブリタニカは100年ほど続いただけである。「この世は舞台、人は役者」とシェークスピアは言った。「世は挙げて黄金を慕い 金銀財宝目もくらむばかり されど砂漠に降れる雪のごとく あえなくも溶けゆくを如何せん」とオマル・ハイヤームはつぶやいた(陳舜臣訳の『ルバイヤート』から)。今の世界にはこのような雰囲気が満ちている。
一方で、1970年代から1990年代にかけの世界には民主化を成し遂げる国が少なからずあった。1974年のポルトガルのカーネーション革命に始まるこの時代を、サミュエル・ハンティントンは「民主化の第三の波」とよんだ。東アジアではこの波にのって、フィリピン、韓国、台湾、インドネシアが強権的な政治体制から民主化の道を進み始めた。
もっとも、民主化は一方通行ではなく、国によっては達成した民主化が揺り戻しにあって権威主義的な政治へと後退する局面もあった。タイでは2014年に軍事クーデターがあった。フィリピンはドゥテルテ大統領の腕力政治ののち、現在はマルコス元大統領の息子が大統領に選ばれている。インドネシアのプラボウォ大統領はスハルト元大統領の娘と結婚していたことがあり、反スハルト運動の活動家らを迫害した疑いで、スハルト退陣後に軍籍をはく奪され、一時期レバノンに移住し事実上の亡命生活をしていた。韓国では最近、現職のユン・ソンニョル大統領が、野党の政治活動に対抗して、さしたる理由もなく戒厳令を出し、現在は当局によって逮捕・拘束されている。
もっとすさまじい例は米国民が選出したトランプ大統領である。①カナダを51番目の米州にしたい②グリーンランドを所有したい③メキシコ湾を「アメリカ湾」と呼べ――記事の中でメキシコ湾と表記したAP通信社は大統領執務室での取材を拒否された④関税を引き上げると近隣諸国を脅す⑤ガザの住民をどこかに移し、ガザを整地して国際的な観光地にするためにガザを所有したい⓺ウクライナとロシアの戦争を停止させるためロシアと交渉を始める、などなど。
民主化の第三の波時代、ロバート・ダール『ポリアーキー』やフアン・リンス『全体主義体制と権威主義体制』といった本が読まれた。民主化の道しるべをさがすためだった。時代が移って21世紀になってから、ヨーロッパの極右勢力の伸長や米国の第1次トランプ政権の登場があって、フアン・リンスが再び読まれるようになった。皮肉なことに読まれている彼の著書のタイトルは『民主主義体制の崩壊』。民主主義体制はいかにしてほころび、むしばまれ、権威主義体制にもどって行くのか。それがテーマである。時代の変化を感じざるをえない。
ハンティントンは著書『第三の波』で、民主化に関係があると思われる要素を挙げている。所得。所得の公平な分配、市場経済、社会の近代化、中間階級の存在、などがそうである。
アメリカ合衆国でドナルド・トランプ氏がなぜ2度も大統領に選出さえたのだろうか。H.D.ラスウェル『権力と人間』は「政治人」のイメージの一つに「政治人は他者から区別される我(エゴ)という意味での自己のためにのみ権力を追求する」を挙げている。そして政治人は「私的動機を公の目的に転位し公共の利益の名において合理化する」と解説する。トランプ氏のねらいはノーベル平和賞受賞の栄誉だと噂されているが、公の目標はウクライナに平和をもたらすためだ、という。だから手っ取り早く、ウクライナの頭越しに米露ボス交渉を呼びかけたのである。
トランプ氏の政治人としての強烈な磁力によって米国の有権者がめくらんだのか、それとも米国社会のタガが外れてそこからトランプ氏が生まれてきたのか。
トランプ氏の無呼吸筋肉政治活動がいつまで続くか不明で、それを見つめる世界の人びとの眼は不安に満ちている。「由良の門を渡る舟人かぢをたえ行へも知らぬ……」という気分なのだ。
(2025.2.20 花崎泰雄)











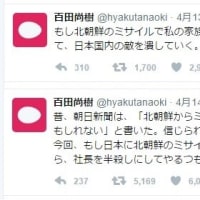

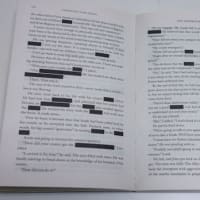
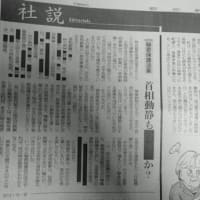










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます