自民党総裁選をまえに、全国10ヵ所で開かれていた自民党のブロック大会が5日終わった。そのブロック大会での安倍晋三、麻生太郎、谷垣禎一3候補の改憲問題に関する発言をまとめた朝日新聞9月6日朝刊は「安倍氏改憲前面に。麻生氏同調、谷垣氏は慎重」と見出しにした。
安倍氏は各ブロック大会冒頭で「新憲法制定を政治スケジュールにのせるリーダーシップを発揮する」と繰り返し、麻生氏も「日本人が作った日本人の憲法が必要だ」とした、という。
安倍氏は総裁選出馬表明にさいして、「美しい国、日本」という政策パンフレットを作った。そのパンフレットの冒頭で、政権の基本的方向として「新たな時代を切り開く日本に相応しい憲法の制定」を掲げている。どうやら安倍氏は右派ナショナリスト政治家として、憲法改正、自由と規律の保守主義路線、教育のあり方の変更を掲げて、「戦後レジーム」からの脱却を売りにしているようである。
安倍氏はそのように変更される日本を「美しい国」と川端康成もどきのキャッチフレーズにした。だが、安倍氏は4年前、早稲田大学での講演で、ICBMを持っても憲法上問題はない、戦術核兵器使用は違憲ではないと語った、とサンデー毎日にスッパ抜かれたことがあった(このエピソードは、最近BBCが自民党総裁有力候補、安倍晋三の紹介記事で使ったので、再び世界中に知れ渡ることになった)。戦前生まれの筆者には、このような粗雑な右派ナショナリストの改憲論者が「美しい日本」などと叫ぶのを聞くと、つい、本居宣長の「敷島のやまとごころを人とわば朝日ににおう山ざくら花」を連想させられる。さらにはこの歌をもとに、神風特攻隊の最初の4部隊が「敷島隊」「大和隊」「朝日隊」「山桜隊」と名付けられた、などといういまわしい記憶もよみがえる。日本の政治文化には、このような美意識によって国家が献身と自己犠牲を強要する、グロテスクな伝統があるので、「美しい国、日本」などという政治家のキャッチフレーズには注意が必要だ。話がそれた。
安倍氏は改憲が「戦後レジーム」からの離脱の象徴になると理解しているようだ。安倍氏のいう「戦後レジーム」がいったい何を意味しているのか、いまひとつはっきりしない。①戦勝国アメリカが日本におしつけた米国製の日本国憲法によって、日本が独立国としての面目を失ってきたことに我慢できかねるという意味なのか。あるいは、②憲法第9条のせいで、安全保障をアメリカに頼りきり、その代償としてさまざまな分野でアメリカの言いなりにならざるをえなかった屈辱の過去の清算なのか。または、③戦後の日本を取り仕切り、「戦後レジーム」そのものであった自民党に代表される保守政治からの離脱を意味しているのか。おいおい、それは小泉純一郎氏が「自民党をぶっ壊す」と叫んだのと同じ自己否定のポーズではないか。それとも、④日本国憲法に盛り込まれた、主権在民、三権分立、国家からの自由、人権、社会権などという「戦後レジーム」の柱になった近代西欧の諸概念が、日本民族を堕落させてしまったとでも言っているのだろうか。
憲法第9条は日本軍国主義に手を焼いたアメリカのおしつけだったにせよ、あの当時の日本にはもう戦争はコリゴリという疲労感と軍隊嫌悪感もあり、9条を抵抗なく受け入れた。朝鮮戦争を機にその9条を変質させたのも、またアメリカである。日本に警察予備隊をつくらせ、武器を与え、保安隊に改名、やがて自衛隊という名のれっきとした三軍をもつ軍事組織になった。すでに海外派兵も行っている。2年ほど前にはアーミテージという名の当時の米国務副長官が、憲法第9条が日米同盟の制約になっているとして、日本に改憲のための努力を求めた。
アメリカは世界の警察官=保安官を自認し、日本に現場へ出て保安官助手を務めるよう要求している。保安官に同行して、すんなりと現場出動できるように第9条を何とかしろよと求めている。このところ高まっている改憲論には、「戦後レジーム」の特徴の1つである対米追従のにおいも漂っている。
(2006.9.6 花崎泰雄)
安倍氏は各ブロック大会冒頭で「新憲法制定を政治スケジュールにのせるリーダーシップを発揮する」と繰り返し、麻生氏も「日本人が作った日本人の憲法が必要だ」とした、という。
安倍氏は総裁選出馬表明にさいして、「美しい国、日本」という政策パンフレットを作った。そのパンフレットの冒頭で、政権の基本的方向として「新たな時代を切り開く日本に相応しい憲法の制定」を掲げている。どうやら安倍氏は右派ナショナリスト政治家として、憲法改正、自由と規律の保守主義路線、教育のあり方の変更を掲げて、「戦後レジーム」からの脱却を売りにしているようである。
安倍氏はそのように変更される日本を「美しい国」と川端康成もどきのキャッチフレーズにした。だが、安倍氏は4年前、早稲田大学での講演で、ICBMを持っても憲法上問題はない、戦術核兵器使用は違憲ではないと語った、とサンデー毎日にスッパ抜かれたことがあった(このエピソードは、最近BBCが自民党総裁有力候補、安倍晋三の紹介記事で使ったので、再び世界中に知れ渡ることになった)。戦前生まれの筆者には、このような粗雑な右派ナショナリストの改憲論者が「美しい日本」などと叫ぶのを聞くと、つい、本居宣長の「敷島のやまとごころを人とわば朝日ににおう山ざくら花」を連想させられる。さらにはこの歌をもとに、神風特攻隊の最初の4部隊が「敷島隊」「大和隊」「朝日隊」「山桜隊」と名付けられた、などといういまわしい記憶もよみがえる。日本の政治文化には、このような美意識によって国家が献身と自己犠牲を強要する、グロテスクな伝統があるので、「美しい国、日本」などという政治家のキャッチフレーズには注意が必要だ。話がそれた。
安倍氏は改憲が「戦後レジーム」からの離脱の象徴になると理解しているようだ。安倍氏のいう「戦後レジーム」がいったい何を意味しているのか、いまひとつはっきりしない。①戦勝国アメリカが日本におしつけた米国製の日本国憲法によって、日本が独立国としての面目を失ってきたことに我慢できかねるという意味なのか。あるいは、②憲法第9条のせいで、安全保障をアメリカに頼りきり、その代償としてさまざまな分野でアメリカの言いなりにならざるをえなかった屈辱の過去の清算なのか。または、③戦後の日本を取り仕切り、「戦後レジーム」そのものであった自民党に代表される保守政治からの離脱を意味しているのか。おいおい、それは小泉純一郎氏が「自民党をぶっ壊す」と叫んだのと同じ自己否定のポーズではないか。それとも、④日本国憲法に盛り込まれた、主権在民、三権分立、国家からの自由、人権、社会権などという「戦後レジーム」の柱になった近代西欧の諸概念が、日本民族を堕落させてしまったとでも言っているのだろうか。
憲法第9条は日本軍国主義に手を焼いたアメリカのおしつけだったにせよ、あの当時の日本にはもう戦争はコリゴリという疲労感と軍隊嫌悪感もあり、9条を抵抗なく受け入れた。朝鮮戦争を機にその9条を変質させたのも、またアメリカである。日本に警察予備隊をつくらせ、武器を与え、保安隊に改名、やがて自衛隊という名のれっきとした三軍をもつ軍事組織になった。すでに海外派兵も行っている。2年ほど前にはアーミテージという名の当時の米国務副長官が、憲法第9条が日米同盟の制約になっているとして、日本に改憲のための努力を求めた。
アメリカは世界の警察官=保安官を自認し、日本に現場へ出て保安官助手を務めるよう要求している。保安官に同行して、すんなりと現場出動できるように第9条を何とかしろよと求めている。このところ高まっている改憲論には、「戦後レジーム」の特徴の1つである対米追従のにおいも漂っている。
(2006.9.6 花崎泰雄)











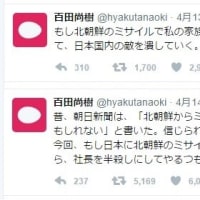

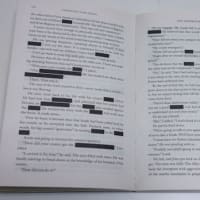
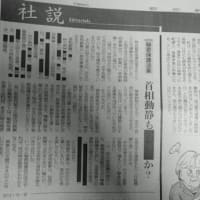










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます