橋下徹・大阪市長が目標の学力水準に達しない小中学生を留年させる制度を提案した。
ジバン、カンバン、カバンを持たない橋下にとって、集票のたよりは人気だけだ。人気者だからこそ永田町の既成政治家にちやほやされる。メディアに取り上げられる頻度も高くなる。この人気を持続させるためには、切れ目なく大衆の視線を集めるパフォーマンスを続ける必要がある。
アメリカの赤狩りで一躍政界の大物にのしあがったジョゼフ・マッカーシーがいい例だ。大衆がそのパフォーマンスを見飽きてしまった時が彼の凋落の始まりだった。落ちるときは一瀉千里だ。
橋下はこれまで教員に国歌を強制する条例、維新塾・船中八策という中身のないかけ声、大阪市の労組に対する不当労働行為、職員のメール検査と、パフォーマンスを演じ続けてきた。
義務教育での留年の実施検討という今度の提案は、どうも世界的な流れと反対の方向だ。
2月23日夜の毎日新聞電子版によると、OECDが学校教育で留年を廃止するよう求める提言をしている。同紙の記事によると、OECDは、「教育の公平性と質――恵まれない生徒や学校に対する支援」と題する報告書で、学校教育での留年について「コストがかかるうえ教育成果の引き上げでも効果的ではない」と結論した。
OECDが、 少なくとも1年留年した経験のある15歳児について39ヵ国を比較したところ、OECD加盟国の平均は留年経験者が13%、留年のためにかかったコストが4.05%。フランスなど7ヵ国では留年経験者が30%を超えた。スペインなど3ヵ国ではコストが10%以上になった。日本、韓国、ノルウェーはいずれも留年ゼロだった。
「留年の欠点はコスト増に加え、学習到達度の生徒間格差の拡大、自尊心への悪影響、問題行動に出る傾向を高めることなどを列挙。留年より効果的な代替策として学習支援や自動的な進級を推奨した」と毎日新聞はOECDの報告書の要旨を伝えている。
NHKによると、森文部科学副大臣が記者会見で、留年については制度上問題がなく、学力を身につけることについて問題提起をすることは、非常に意義があることだ、と橋下留年提案を歓迎する意向を示した。
OECDの国際的な知見に基づく提案などどこ吹く風だ。外国と日本は違うと言わんばかりだ。
とはいうものの、実は、日本でも明治期には初等教育に落第制度「原級留置」が行われていた。学年ごとに一斉試験をし、及第しなかった児童を進級させなかった。国立教育政策研究所の斉藤泰雄の「留年・中途退学問題への取り組み――日本の歴史的経験」(広島大学教育開発国際協力センター『国際教育協力論集』第6巻1号、2003)によると、こうした初等教育での試験進級制度は、ひとつには「文明開化」「富国強兵」をめざす明治政府が欧米の近代技術や知識を国民につめこむ必要にせまられていたからだ。だが、厳格な試験進級制度によって落第児童が全児童の2-3割に達したという。
落第児童が中途退学者になり、社会問題になった。そういうわけで日本は1900年に初等教育での落第制度を廃止し、自動進級制度に切り替えた。以来1世紀以上、初等教育では自動進級制度が続いている。
教育環境や教員の質を向上させることで、標準的な義務教育の達成に落第制度が必要なくなったからだ。
2012年の今日、いまさらに初等教育での留年制をもちだすのなら、その必要性と効果について相応の知見に支えられた論拠を添えて提案すべきであろう。ことは将来の市民をそだてる教育の問題だ。軽々しく人気とりのタネにするには重すぎる問題である。
(2012.2.24 花崎泰雄)











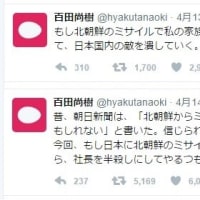

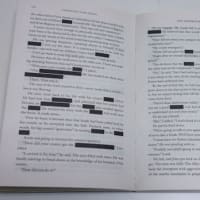
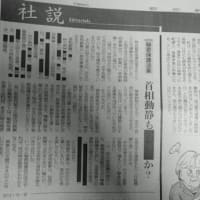










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます