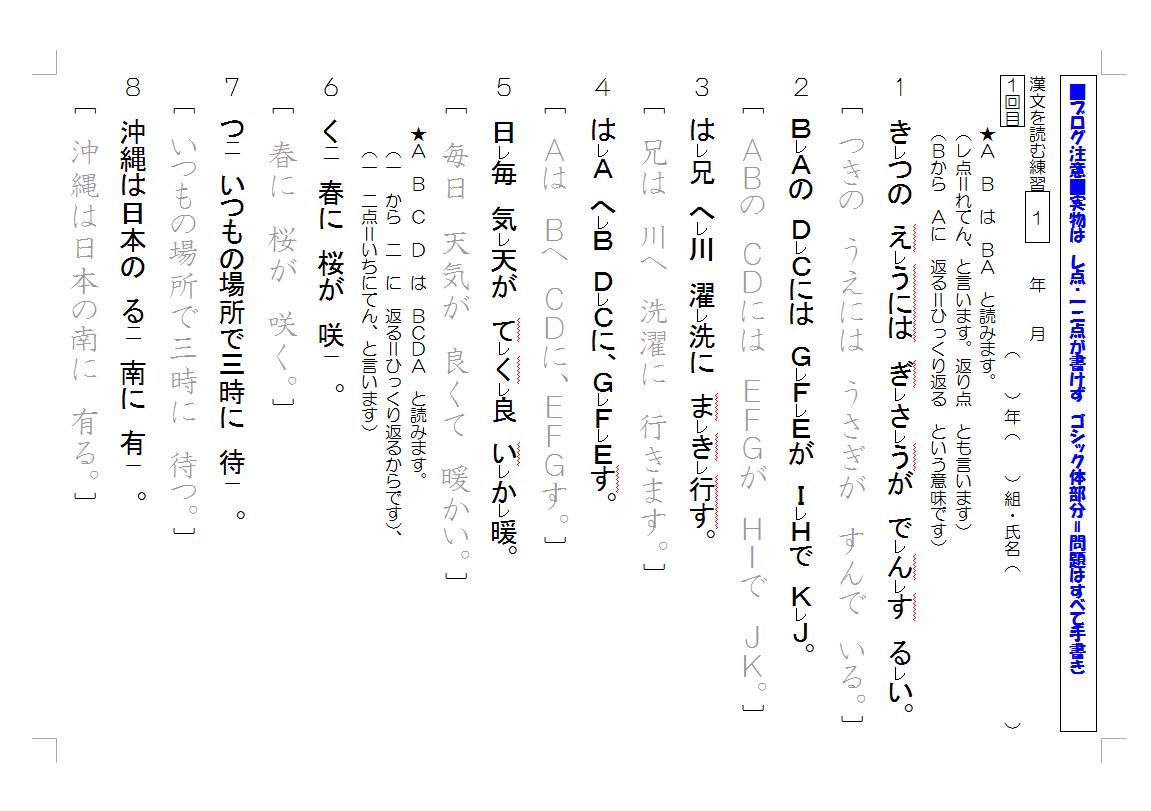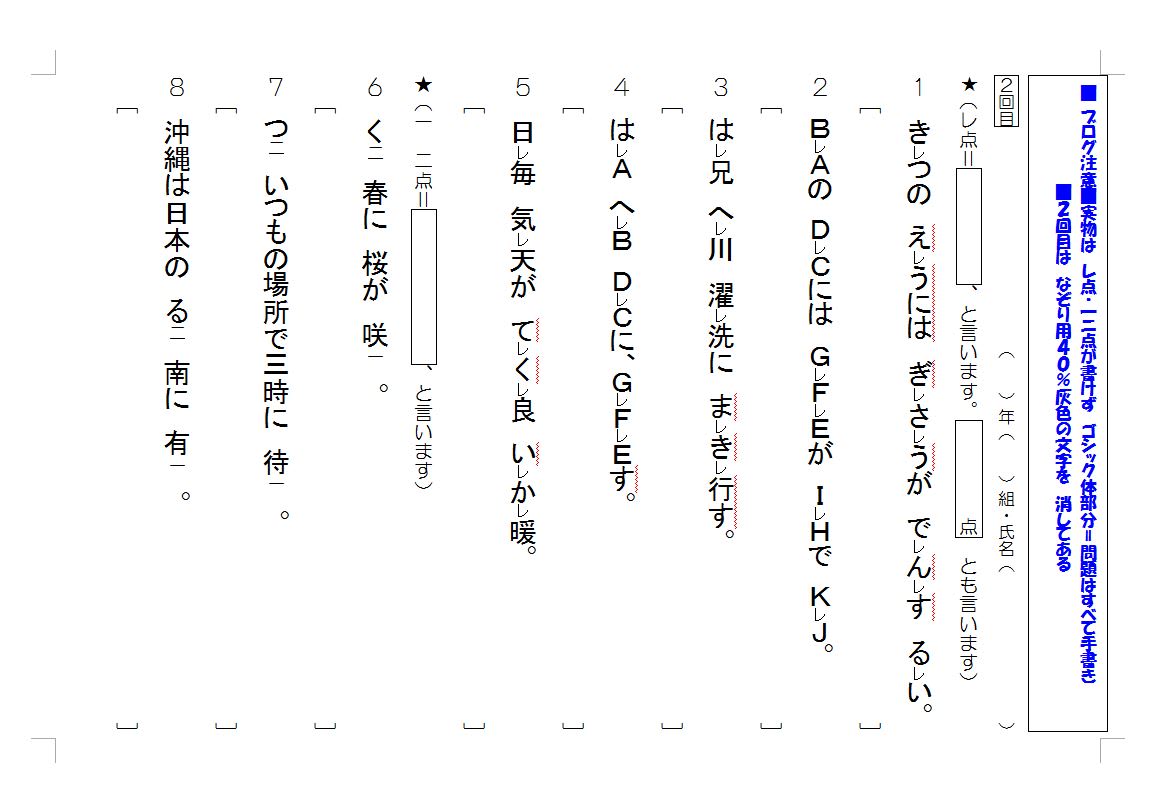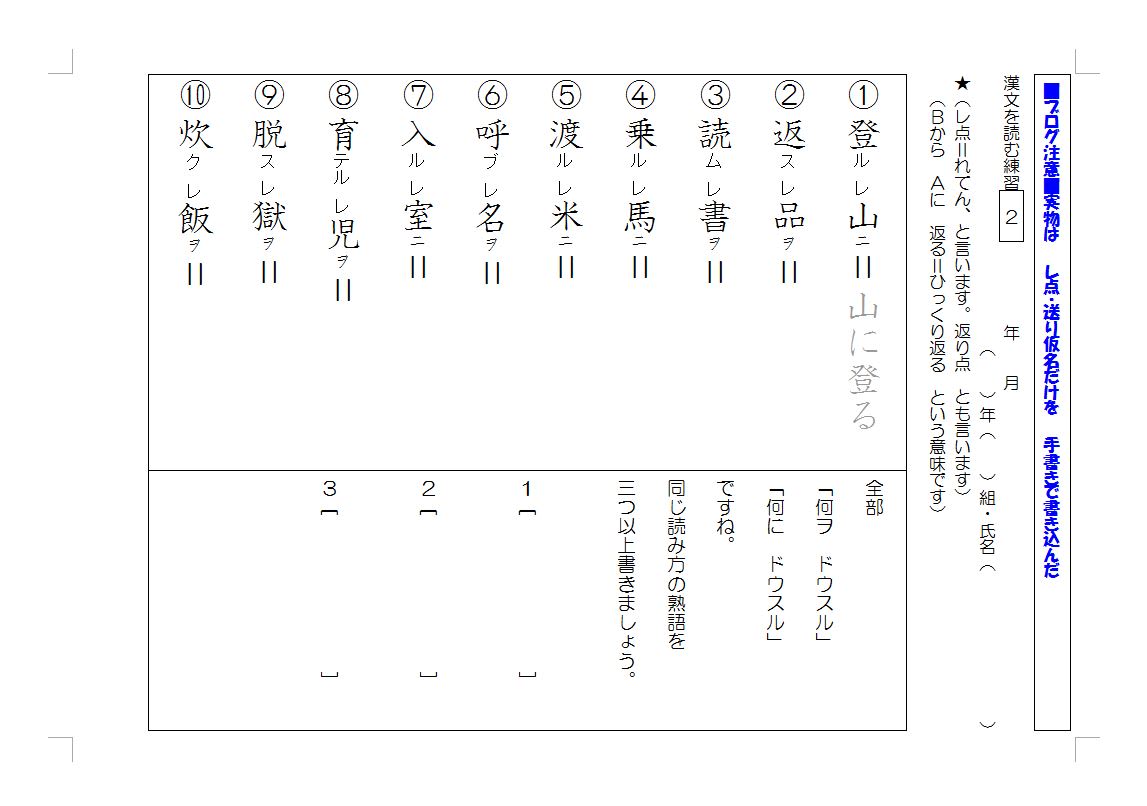カテゴリ別目次 ・ 記事一覧
2015-02-11
マイケルたん4・活動的な授業について考える8項目
参照 マイケルたん・2015-02-09 20:18:42コメント
皆、勝手に解釈しているんです。
『99・9%は仮説思いこみで判断しないための考え方 (光文社新書・700円)』読みましたか?
「死」以外のすべての現象は仮説・解釈です。
指名なし「発表」と「討論」の違い・判別も曖昧です。
だから、質問・意見・反論が生まれて楽しいのです。
コメント返信欄に書いたのですが、
「活動的な授業」のとらえ方は、僕とマイケルたんで、ほぼ一致しているのでは?
※ 前回お断りした通り、読者を意識して脱線しますがご容赦下さい。
①「単元」という言葉に意味があるのでしょうか?
僕は校内研・市内研で、指導案に一度も使ったことがなく、誰も困ったことがありません。
単元、なんて言葉、世の中の誰がわかりますかね?
教員だから答えらえる人がいるとして、生徒の学力に役に立つでしょうか。
「教材」とは違いますか。「次に授業する文章」とは違いますか。
エライヒトは使うでしょうが、現場で意味がありますかね。
②ネットで授業研究
巷で話題の通り、すまほ、以外でネットを使わない人が多いようです。
若い人に多い。
ぼくの同世代の年寄りにも多い。
それでは、授業研究は「絶対に」できません。
パソコンでいくつかのキーワードごとに、数十の記事を検索する。
合わせて、百数十から数百の記事をどんどん開く。
必要な記事をお気に入りに入れる。
お気に入りを読み返し、整理・捨てて、必要な部分をコピーする。
最後に、自分の解釈を書き加える。
すまほ、でできるはずがありません。
マイケルたんもPCネットで、空の箱に来てくださったはずです。
どんな方法で授業研究していますか? 大事なことですね。
なんだか年表みたいのを作る授業でしょうか。
僕もできません。
「範読・感想書き・発表」はおおざっぱではありません。
ひとコマでできるようになるのは、生徒にとって価値があり、教師にとって難しいことです。
「どれだけ、生徒が教科書を読み込んだか」
が大切なのは、そのとおりだと思います。
討論の授業の良い所は、うまくいけばですが、
生徒は穴のあくほど細かい表現を、そして思いもかけない前後の文章の表現を、
論拠として探し出すことです。
「読解力をつける」とは、そういう作業ではないでしょうか。
(1)地味
思考は地味なものです。
見ても分かりにくい。分かる人にしか見えない。
「発表・討論」後、参観教員が
「発言しない生徒がいていいのか」
と訊くことがあります。
いいんです、と答えます。
生徒の発言を聞く生徒の頭はフル回転しています。
討論の直後の
「討論についての作文=見本はちゃんと書く」
を読めば分かります。
一度しか発言しない生徒が、抜群の作文を書くことが度々あります。
発言は多い生徒が、作文には書けないことが多くあります。
それが「討論」のいいところです。
教員は、生徒の「腕の見せどころ」を、いくつも作ってあげなければなりません。
(2)全員できました!
マイケルたんは、冷静な「書きぶり」をします。
ここで初めて、感情あふれる表現をなさいました。
生徒が次々立つ。
つまらないことをひと言だけ言う。
(このひと言を喜ぶ国語教員かどうかが道を分けます)
驚くような、予想を越えたすごいことを言う。
(どんな鈍感な大人も喜ぶ)
二度、三度と立つ。
もっと言いたいと言う。
生徒は普通、はやく授業終わんないかなあ、というものです。
でも、討論のときは違う。
マイケルたん。・・・生徒が全員、自分で立って発表したら感激しますよね。
楽しいだけでは授業として不十分、と前回書きました。
しかし「楽しさ」のレベルはピンキリです。
条件がそろえば、五色百人一首・超楽しいレクより、討論が楽しかったと生徒は言います。
大事なのは、指名なし討論は「道具」の一つにすぎないということです。
授業の目的ではありません。
生徒の学力を向上させるための、一つの道具です。
知的好奇心をかきたて、何度やってもあきず、次第に深く速くなる。
目立たぬ友達が、思わぬ発言をする。
ひと言も言わなかった生徒が、びっくりする作文を書いて選ばれる。
指名なし、でなくてもいいはずです。
でも、討論には、生徒を育てるたくさんの力があります。
けれど、なかなか実現できない。
僕も今年度はできませんでした。
うぶ毛だけの素人傭兵でさえ、わきまえず知ったように書いてしまう。
それが討論の魅力です。
2015-02-11
マイケルたん4・活動的な授業について考える8項目
参照 マイケルたん・2015-02-09 20:18:42コメント
| ▲1▲傭兵さん、 今自分のコメントを読み返して思ったんですが、僕は根本的に 「活動的な授業」 というものを自分の都合で勝手に解釈していたような部分がある気がします。 |
『99・9%は仮説思いこみで判断しないための考え方 (光文社新書・700円)』読みましたか?
「死」以外のすべての現象は仮説・解釈です。
指名なし「発表」と「討論」の違い・判別も曖昧です。
だから、質問・意見・反論が生まれて楽しいのです。
| ▲2▲傭兵さんと、レヴェルの違う意味合いで「活動的な授業」を捉えていたようです。 そういう意味では、嫌な角度からの返答になってしまった気がして、恐縮です。 |
「活動的な授業」のとらえ方は、僕とマイケルたんで、ほぼ一致しているのでは?
| ▲3▲違う話題ですが、今日、次の単元の授業を考えていたんですが、 ネット等で巷の先生方がされている授業の指導案を見て、 あまりに自分が行っている授業と違うことに、自分自身で畏れ慄いてしまいました。 |
①「単元」という言葉に意味があるのでしょうか?
僕は校内研・市内研で、指導案に一度も使ったことがなく、誰も困ったことがありません。
単元、なんて言葉、世の中の誰がわかりますかね?
教員だから答えらえる人がいるとして、生徒の学力に役に立つでしょうか。
「教材」とは違いますか。「次に授業する文章」とは違いますか。
エライヒトは使うでしょうが、現場で意味がありますかね。
②ネットで授業研究
巷で話題の通り、すまほ、以外でネットを使わない人が多いようです。
若い人に多い。
ぼくの同世代の年寄りにも多い。
それでは、授業研究は「絶対に」できません。
パソコンでいくつかのキーワードごとに、数十の記事を検索する。
合わせて、百数十から数百の記事をどんどん開く。
必要な記事をお気に入りに入れる。
お気に入りを読み返し、整理・捨てて、必要な部分をコピーする。
最後に、自分の解釈を書き加える。
すまほ、でできるはずがありません。
マイケルたんもPCネットで、空の箱に来てくださったはずです。
どんな方法で授業研究していますか? 大事なことですね。
| ▲4▲すごいワークシート、人物像や気持ちの移り変わりをまとめる緻密な授業。 そんな授業したこともないし、する自信もないです。 |
僕もできません。
| ▲5▲それに比べると、今日やった授業は、範読し、感想を書かせ、全員指名なし発表。 おおざっぱといえば大雑把ですが、生徒が思考し、力をつけるという意味では、 決して上記のような授業内容に劣っていないと思うのです。 |
ひとコマでできるようになるのは、生徒にとって価値があり、教師にとって難しいことです。
| ▲6▲僕は、国語の授業の目指すところは、一言で言えば、 「どれだけ、生徒が教科書を読み込んだか」 が目安になると考えています。 |
が大切なのは、そのとおりだと思います。
討論の授業の良い所は、うまくいけばですが、
生徒は穴のあくほど細かい表現を、そして思いもかけない前後の文章の表現を、
論拠として探し出すことです。
「読解力をつける」とは、そういう作業ではないでしょうか。
| ▲7▲時間制限をし、全員発表を予告して感想を書かせている間、 生徒は教科書をめくり、何度もくりかえし黙読していました。 地味ですが、こんな作業の中で、生徒は読む力をつけているのだと思います。 (ちなみに、前回は数名の生徒が発表できずに残り、仕方なく最後に立たせて発表しましたが、今回は全員できました・・!) |
思考は地味なものです。
見ても分かりにくい。分かる人にしか見えない。
「発表・討論」後、参観教員が
「発言しない生徒がいていいのか」
と訊くことがあります。
いいんです、と答えます。
生徒の発言を聞く生徒の頭はフル回転しています。
討論の直後の
「討論についての作文=見本はちゃんと書く」
を読めば分かります。
一度しか発言しない生徒が、抜群の作文を書くことが度々あります。
発言は多い生徒が、作文には書けないことが多くあります。
それが「討論」のいいところです。
教員は、生徒の「腕の見せどころ」を、いくつも作ってあげなければなりません。
(2)全員できました!
マイケルたんは、冷静な「書きぶり」をします。
ここで初めて、感情あふれる表現をなさいました。
生徒が次々立つ。
つまらないことをひと言だけ言う。
(このひと言を喜ぶ国語教員かどうかが道を分けます)
驚くような、予想を越えたすごいことを言う。
(どんな鈍感な大人も喜ぶ)
二度、三度と立つ。
もっと言いたいと言う。
生徒は普通、はやく授業終わんないかなあ、というものです。
でも、討論のときは違う。
マイケルたん。・・・生徒が全員、自分で立って発表したら感激しますよね。
| ▲8▲討論の授業も、未経験ですが、おそらく生徒たちはかなり教科書を読み込まないと、実現できないと思います。だからこそそれは、すばらしい実践なのではないかと直観しています。 指名なし発表をはじめたばかりですが、回数を重ねるごとに手ごたえを感じ、 指名なし討論もいずれ実現できるような気がしはじめています。がんばりたいです。 |
しかし「楽しさ」のレベルはピンキリです。
条件がそろえば、五色百人一首・超楽しいレクより、討論が楽しかったと生徒は言います。
大事なのは、指名なし討論は「道具」の一つにすぎないということです。
授業の目的ではありません。
生徒の学力を向上させるための、一つの道具です。
知的好奇心をかきたて、何度やってもあきず、次第に深く速くなる。
目立たぬ友達が、思わぬ発言をする。
ひと言も言わなかった生徒が、びっくりする作文を書いて選ばれる。
指名なし、でなくてもいいはずです。
でも、討論には、生徒を育てるたくさんの力があります。
けれど、なかなか実現できない。
僕も今年度はできませんでした。
うぶ毛だけの素人傭兵でさえ、わきまえず知ったように書いてしまう。
それが討論の魅力です。