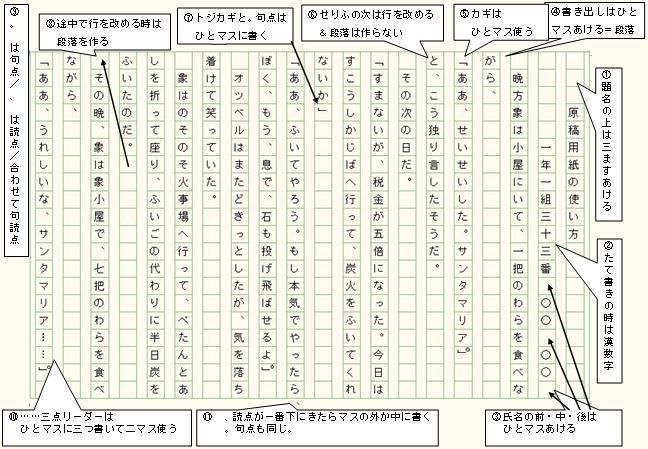カテゴリー別目次
2015-11-12up
これで、各クラス5人以上は、市内トップレベルの主張が出来るようになる。
中学1、2年を5人ずつ連れて行っても、市の中3トップ一人と並ぶ。
2015-11-12up
これで、各クラス5人以上は、市内トップレベルの主張が出来るようになる。
中学1、2年を5人ずつ連れて行っても、市の中3トップ一人と並ぶ。
| 1年X組9月 ◆1コマ 1主張大会日程説明 2宿題主張作文返却 3着席のまま 学年・クラス・番号・氏名を一斉に言わせる 4その見本を見せる 5起立させて一斉に 学年・クラス・番号・氏名を言わせる 6そのまま教室の一番遠くにいる生徒に向かい 同じことを言わせる 7 6と同様に作文学年クラス氏名から本文途中 まで1分半読ませる 8コンビで交代に。7と同様にさせる。 9褒め合い拍手しあわせる 10作文回収・授業感想用紙提出 ◆2コマ 1前日の授業感想を全員分読み聞かせ・そして 「みんな緊張するのだ。 だからよく聞いてあげなさい」 2離席させ教室の壁沿いにグルリと立たせる ①壁に向かわせる。 学年クラス名前本文を読ませる 「やめ! ・聞こえない ・壁の向こうまで ・何言ってるか分からない」 と三回止めてやり直させる ②僕の立つ真ん中に向かわせる。 「真ん中向いて!学年から。ヨーイ・ハイ」 生徒は読み続ける。僕は名前を呼び 「++君口がよく見える」 「++さんよく聞こえる」 と言い続ける。 ③「さん、に、いち。そこまで」 一番口の形が見えた人。男子++。女子++」 3席に戻す。 4班別発表1。四人班を指定する。 ①机を付ける前に、1ミリでもすき間をあけるなと言う。 ②四人の机を付けさせる。6班くらい。 ③各班から付箋を取りに来させる。 ④発表順を決めさせる。 ⑤一人1分ずつ学年から読ませる。 「六人とも。一人目。行くよ。ヨーイハイ」 「さん、に、いち。そこまで」 「付箋書いて渡しなさい【1回目】」 もらった付箋は作文の裏に糊付けさせる。 六人終わってちょうどチャイム。 5作文回収・授業感想用紙提出。 ◆3コマ 1お話 「耳が聞こえて、話せるのはとても有難いことです」 2「見る」練習。 ①黒板にでかい目を左右に三つ書く。 ②2分間、学年番号から言わせ読ませる。 ③十回、黒板の目ん玉を見ろという。 3班別発表2。 ①机付けさせる。 ②付箋持って行かせる。 ③同時に順番決め。 ④「行くよ。学年からヨーイハイ」 1分20秒「やめ。付箋!【2回目】」 6人終えてちょうど時間が来る。 4作文回収・授業感想用紙提出。 ◆4コマ 1評価済み作文返却。 (中2は即日全員評価した) (中1は毎日回収し数人ずつ評価して済み) 2「発表の評価基準読み聞かせ」 作文用紙に書いてあるがしつこく。 3班別発表3。(毎回同じ4人班) ①90秒ずつ。 ②「学年からヨーイハイ」 ③「付箋渡せ【3回目】 次ヨーイハイ」 班内全員済み。 4「主張文を全部読みます。 時間を計ります。 終わったら手を挙げる。 先生が何分何秒というからメモする。 学年クラス番号氏名から。 ヨーイハイ」 5授業感想用紙提出。 ◆5コマ 1クラス発表のやり方をやって見せる。 ①待ち合い椅子に座る。 ②前者が済んだら教卓に立つ。 ③礼。スミを押さえる。 ④学年クラス番号氏名・題名、までは 全員原稿を見ないで言う。 ⑤読み始めて、終わる。 ⑥スミを押さえる。礼。席に戻る。 2教室の最前列6人を前に立たせて、 指示しながら同じようにやらせる。 (これはざわつき過ぎてダメ。 でも生徒はやって良かったと書いていた) 3クラス発表順決め。 4四人班で1分間ずつ発表練習。 (付箋4回目) 5授業感想用紙提出 ◆6コマ 1クラス発表の評価基準読み聞かせ(2回目) くどいが、強調。 2本番の「感想記入用紙」配布 3発表順確認と同時に、順番枠に苗字を書かせる。 4全員起立。 全文音読。計時=終わり座るとき言われた時間をメモ。 5六人班で、付箋渡し5回目。 「付箋最後だから、自信をつけてあげることを書きなさい」 6授業感想用紙提出。 | 2年Y組9月 ■1コマ 1主張大会日程説明 2評価済み作文返却。 3着席のまま 学年・クラス・番号・氏名を一斉に言わせる 4その見本を見せる 5コンビで交代に。着席のまま。 原稿見ないで、 学年・クラス・番号・氏名を一斉に言わせる 3回繰り返す。 6作文回収。授業感想用紙提出。 ■2コマ 1お話 ①夏休み作文の宿題が大変なことだったのをねぎらう。 「嫌だっただろう?」 ②「でも、喋って聞こえるのは有難いこと。 聞こえない人にも分かるような口を開けて発表してください」 2離席させ教室の壁沿いにグルリと立たせる 僕の立つ真ん中に向かわせる。 「真ん中向いて!学年から。ヨーイ・ハイ」 生徒は読み続ける。僕は名前を呼び 「++君口がよく見える」 「++さんよく聞こえる」 と言い続ける。 2分間くらい。 3付箋1回目。 六人班・1人1分・全員済みでチャイム 4授業感想用紙提出 ■3コマ 1お話 ①付箋の内容がとてもよい ②付箋の貼りつけ方を工夫している人がいる 2「見る」練習。 ①黒板にでかい目を左右に三つ書く。 ②2分間、学年番号から言わせ読ませる。 ③十回、黒板の目ん玉を見ろという。 3付箋2回目。 6人班・一人1分20秒。 4全文全員一斉音読計時 座ったまま・学年から作文終わりまで 読み終わりで挙手 傭兵が言う時間をメモ 5授業感想用紙提出。 ■4コマ 1お話 ①感想に 「目を黒板目ん玉に合わせると、どこを読んでいたか分からなくなる」 とあった。 答え 「20回練習したら分かるようになる」 ②別の感想 「みんな一斉に読むやり方は思い切り読めて自分に自身がついて良い感じです」 2採点基準読み聞かせ 3クラス発表のやり方をやって見せる。 ①待ち合い椅子に座る。 ②前者が済んだら教卓に立つ。 ③礼。スミを押さえる。 ④学年クラス番号氏名・題名、までは 全員原稿を見ないで言う。 ⑤読み始めて、終わる。 ⑥スミを押さえる。礼。席に戻る。 4教室の最前列6人を前に立たせて、 指示しながら同じようにやらせる。 (これはざわつき過ぎてダメ。 でも生徒はやって良かったと書いていた) 5付箋3回目 6人班・40秒・学年から 6授業感想用紙提出。 ■5コマ 1お話 「授業感想で、一斉練習ではできても、 班で個人の発表だとそのとおりできない」 とありました。 答えは。スポーツと同じ。 どうせ練習だから80パーと言う人は、本番で半分の力しか出せない。 練習で100パーでやる人は、本番では80しか出せない。 練習で120パー出す人が、ときには本番で100パー出せる。 2クラス発表順決め。 3遠く声と視線を飛ばす練習。 ①座席を四つの班に机を付けさせる。 ②班の上に画用紙のA・B・C・Dを立てる。 ③対角線の記号に向かい、 画用紙を見ながら作文を全文読む。 ④読み終わった人から、 AにいたらBに移動する。 ⑤Bから対角線のDに向かい、 視線を飛ばしながら全文読む。 ※繰り返し。ほぼ全員が4場所で4回読んだ。 4付箋=自分から自分へ自己評価。 付箋はいつも作文用紙の裏に糊付け。 ■6コマ 1発表順確認。 2本番の「感想記入用紙」配布 3発表順確認と同時に、順番枠に苗字を書かせる。 4評価基準読み聞かせ。 5全員起立・全文音読・計時 座ると傭兵が時間を言うのでメモ 6六人班で付箋5回目 |