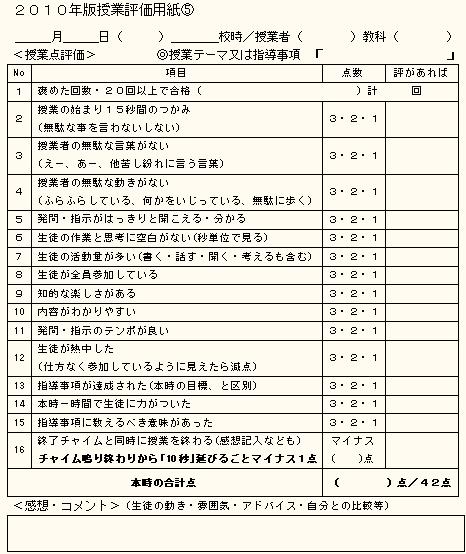| わかる目次 |
| 小学校参観・一人になっても読み続けてえらいね 都内某小学校06年11月23日参観③ |
◆5校時3年2組S先生の国語
・『ちいちゃんのかげおくり』研究授業。
・◎予定の1:40ピッタリ開始。すばらしい。
・◎起立。全文、微音読。終わったら座る。全員ちゃんとやる。立派。
・ADが見つからない。
・○教師も回りながら微音読を続ける。ここまでは良かった。
・×読ませる分量が多すぎる。
・×トップとラストの差が2分以上ある。子どもは充分がんばった。
・×最後の一人は時間で切って座らせた。
それは正しい。
でも、ほめない。
「一人になっても読み続けて、えらいね」
と言ってやればいいのだ。
ぼくは、短文の音読なら、最後の一人も待つ。
他の子はその子の声を聞いてシンと待つ。
「○男。最後までごまかさず読んでエライ!」
こうしとくと、他の子も少しはごまかさなくなる。
○男も恥だとは感じない。
・発問
『最初のかげおくりと、最後のかげおくりの間で、
ちいちゃんから失われたものは何ですか』
指示
『ノートに書きます』
・○小さな無駄言葉をなくせばかなり良い感じ。
・板書
『ちいちゃんのまわりからうしなわれたものは何ですか』
・○「下敷きを使ってる人」(ハイ、と挙手)
児童は写している。
・○「写したら鉛筆を置く」
・×「**くん、急いで下さい」
(まあ、言うよ、俺も。##、早くしろ、ついて来い、とか)
・Q(ます目ノート。良いが、なぜTOSSノートを使わん)
・××「証拠となるところに線を引きながら書いていきます」
(これで終わった。もう、児童は何をしたらいいかわからない)
・○「ひとつ書いたら持っっといで」
・○教師が立つ姿が、スッとしていて良い。
・×窓側の男の子のノートを見る。
二行書いた終わりに「~~からです。」と書いてある。
それを先生に見せてきたのだ。
Sさんはそのノートを見たのだ。
発問は
『何ですか』
である。
・×ひとつ提出した児童は、ほぼ全員次を考えない。
手元で細かく遊んでいる。
完全な思考の空白が続く。続く。続く。
■[代案]■
「先生は、四つ見つけました」
・××
「証拠にも線、引きましたか」
(同時に二つのことを要求しているからダメ。
できるならいいが、思考は止まってる。
・×2:01。
開始21分後。誰も考えていない。
この空気が読めないのか。…読めないよね。なかなかね。
・??なんか、別の教師らしき男性登場。
児童に話しかけんな! 指導すんな! やめろ
・2:03。
「一回鉛筆置きます。」
「一つ以上書けた人」(8人挙手)
・板書
『命』
・発問
『いのち。証拠はどこですか』(どこどこ、と答える子がいる)
・指示
『他に・・・○○さん。』(家)
・板書
『家』
・×児童は「何か」と「証拠」をいっぺんに言おうとする。
そりゃそうだ。そうしろと言ったのだから。
■[代案]■
「失われたものが一つ書けた人。起立」
(端から言わせて座らせる。板書。)
「一つ目。命。命の証拠が書いてあるページを探しなさい」
(サッサと言わせる。「5ページのどこですか」)
「追い読み。~」「~」
「読んだところに線を引いたら手を挙げなさい」
「丸付けコンビで指さしてみせっこしなさい」