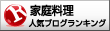先日、蕎麦の等級検査に立ち会わせてもらいました。
場所は、JAしおざわの低温倉庫です
平成25年12月18日撮影
↑ ↓ 1袋25㎏の袋の中から、一定量を取り出す作業から始まります。
↓取り出した玄蕎麦
見比べると、違いがよく分かります。
↑ 容積重の検査。蕎麦粉にしたときの重さは一番大切です。
↓ 容積重の換算表、数字にすると言い逃れはできません
↓ 未熟な玄蕎麦を取り出して数えます。
現在蕎麦の等級は、一等、二等、三等、規格外と四通りに分けられます。
残年ながら、滝之又農産の蕎麦は規格外になっています。食味は、ほとんど区別がつかないと思います。
現在ほとんどの玄蕎麦は規格外です。二等の蕎麦にしても採算が合いません。恐ろしく高い蕎麦になります
等級の一番大きな違いは、見た目です。等級を上げるなら、何度も選別して、見た目をよくすれば上等になります。
現在は、道の駅などの売上がどんどん伸びているようです、消費者が規格品よりも新鮮さや、お得感をさらに重視するようになって来た証だと思います。
生産者と消費者、みんなが、にこにこするような日常が続くといいな。
↓ 平成25年12月11撮影
↑ 先日、ご本家宅に回覧板をもって言ったときのこと、セロリある?とご本家のお母さんから質問されました。
私は、正直に、ないです。と答えました。
それなら、もって行きなさい。と言うことで、いただいたセロリです。
みての通り、保存が利くように、根を付けたまま新聞でくるみ、肥料袋に入っていました。
肥料袋、2袋分いただきました。頂き物の場合、金額に換算してはいけません。数字も大切ですが、手間の方がはるかにありがたく、そして貴重です。
腰の曲がった御本家のお母さんが、丁寧な仕事で、保存しようとしたセロリ、凄く幸せな気分になりました
↑ 早速、きんぴらにして、いただきました。
そういえば10数年前、本家のお母さんからいただいた、タラ大将入りのセロリの漬け物を、うまいと感じてから私のセロリ嫌いは改善されました。
感謝!
今年の秋は、ナメコの大豊作でした。
数年前に流行ったナラ枯れ病、(カシノナガキクイムシが糸状菌Raffaelea quercivora を伝播することによって起きる 病気で、ブナ属を除く日本のブナ科樹木に発生します)が一番の要因だと思います。
↓ 平成25年12月9日撮影
↑ びっしりと生えたナメコ、はしごを使わないと収穫できないほど高いところにも生えています。
↓ 見渡すと、あちこちにナメコが見えます。収穫後の画像です。
↓ 収穫したばかりの天然ナメコ。
収穫時期を過ぎていたため傘が開いていますが、食味はそれほど変わらないと思います。
今年の秋は、家の改装で忙しく、キノコ採集には行けませんでした。
この日は、撮影メインで撮りに来ました
↓ 平成25年9月13日撮影
田んぼの見回りをしていると、きれいな栃の実が落ちていました。
子供の頃、2寸釘で栃の実に穴を開け、中の実を全て出し、笛の代わりにして遊んだ様な記憶があります
現在は、栃の実で思い出すといえば、佐渡の奥方の実家からいただく栃餅です。
今年は佐渡に稲刈りに行けなかった、雪が降る前に行きたいと思っていたが、12月15日現在猛吹雪、玄関先で1メートル近い積雪です。船が欠航しています
今年は、ブナやナラ、クヌギの実(ドングリなど)が、数年ぶりの大豊作、我が家の庭のクヌギも、これまでにないほどたわわに実を付けました。
↑ 自宅の庭のクヌギ、この実を50個ほど、プランターに植えてみました。来年の発芽を楽しみにしてます。
↓ 平成25年11月23日撮影
↑ 雪囲い途中の自宅の庭、中央の広葉樹が、東京都町田市で発芽したクヌギです
なぜ、町田市産かというと、今から20数年、前私の奥方は町田市に住んでおりました。
私が遊びに行ったとき、道路に落ちていた実を、奥方の住むアパートにもって帰りました。それを奥方が観葉植物の鉢に埋めたら、いつの間にか発芽したと言う訳です。
カブトムシやクワガタの、えさ場にもなる可能性もありますし、キノコの菌を植え付ければキノコも楽しめます。
何より根性のあるクヌギ、捨てるには惜しい、というわけで自宅の庭に植えました。