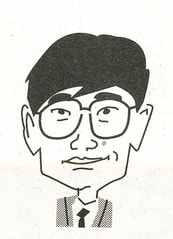美術史上最も女性にモテた西洋の絵描きはモディリアーニ。同じくらいにモテたのは、ラファエロとヴァン・ダイク。そう美術史家の宮下規久朗氏が書いている(「芸術新潮07年5月号」)。
モテ男3人のうち、ラファエロはイタリア・ルネサンス期の巨匠。ラファエルとも表記され、バチカン宮殿の壁画などを手掛け、サン・ピエトロ大聖堂の建築を監督した。1483年にイタリア中部の都市ウルビーノ生まれ。1520年、37歳の若さで亡くなるまで、多くの聖母子像を描いたことでも知られる。
例えば、ルーヴル美術館所蔵の「聖母子と幼児聖ヨハネ」(1507年、縦1㍍22㌢、横80㌢)。「美しき女庭師」とも「緑野の聖母」とも呼ばれる。背景は晴れた空と牧歌的な野山。中央に大きく描かれた聖母は優しげな視線を裸の赤ん坊に注いでいる。心穏やかになる絵だ。
◇
最近、勧める人があって、「大地からの祈り」(高城書房)という本を読んだ。副題は「知覧特攻基地」。薩摩川内市在住の児童文学者、植村紀子さんの著作で、一昨年8月15日付けの発行。擬人化した開聞岳の視線から、戦争の愚かさや特攻隊員の暮らしを描いた。
その一節。出撃直前の特攻隊員が恋人にあてた手紙を取り上げたくだりで、ページをめくる手が止まった。
「観たい画 ラファエル『聖母子像』。(中略)智恵子。会いたい、話したい、無性に」
当時、日本はドイツ、イタリアと3国同盟を結んでいた。だから、特攻隊員にとってイタリアの絵は敵国の文化ではないのだろう。
いや、そんな歴史的な背景分析は意味がない。ただ、見たかったのだ。ラファエロの聖母子像を。恋人と会って話すことと同じくらいに。
「見たい」「会いたい」と恋い焦がれる。そんな人の暮らしの大切さを思う。
鹿児島支局長・馬原浩 2010/11/1 毎日新聞掲載
モテ男3人のうち、ラファエロはイタリア・ルネサンス期の巨匠。ラファエルとも表記され、バチカン宮殿の壁画などを手掛け、サン・ピエトロ大聖堂の建築を監督した。1483年にイタリア中部の都市ウルビーノ生まれ。1520年、37歳の若さで亡くなるまで、多くの聖母子像を描いたことでも知られる。
例えば、ルーヴル美術館所蔵の「聖母子と幼児聖ヨハネ」(1507年、縦1㍍22㌢、横80㌢)。「美しき女庭師」とも「緑野の聖母」とも呼ばれる。背景は晴れた空と牧歌的な野山。中央に大きく描かれた聖母は優しげな視線を裸の赤ん坊に注いでいる。心穏やかになる絵だ。
◇
最近、勧める人があって、「大地からの祈り」(高城書房)という本を読んだ。副題は「知覧特攻基地」。薩摩川内市在住の児童文学者、植村紀子さんの著作で、一昨年8月15日付けの発行。擬人化した開聞岳の視線から、戦争の愚かさや特攻隊員の暮らしを描いた。
その一節。出撃直前の特攻隊員が恋人にあてた手紙を取り上げたくだりで、ページをめくる手が止まった。
「観たい画 ラファエル『聖母子像』。(中略)智恵子。会いたい、話したい、無性に」
当時、日本はドイツ、イタリアと3国同盟を結んでいた。だから、特攻隊員にとってイタリアの絵は敵国の文化ではないのだろう。
いや、そんな歴史的な背景分析は意味がない。ただ、見たかったのだ。ラファエロの聖母子像を。恋人と会って話すことと同じくらいに。
「見たい」「会いたい」と恋い焦がれる。そんな人の暮らしの大切さを思う。
鹿児島支局長・馬原浩 2010/11/1 毎日新聞掲載