
エジンバラからロンドンへ特急列車で4時間半。実際にはもう少しかかったが、日本の新幹線やフランスTGVのない英国では、国の縦断は普通の特急列車での旅となる。延々と続く何の変哲もない風景。というのは、イギリスにはそもそも高い山や渓谷、大河がない。羊の群れや牛の群れ。干し草をくるくる巻いたものが続く。しかし、大河はないが、水の豊かなイングランドの河川に揺れる木々とそこではたらく人の姿。これはコンスタンブルの描いた世界ではないか。川の青と木々の緑と、変化の少ない色彩と情景と。そこには冗長な独白はなく、あるとすれば潔く、静かな自然に見えたほとばしりを告げる短編詩か。ワーズワースとか、バイロンとか、エリオットとか。てんで分からないが、晴れたと思ったら、すぐに雨の降る、気まぐれでそれも大げさではない天候に、それを受け止める起伏の穏やかな大地にこそ、詩人の心を揺るがした風景がそこにはあるのかもしれない。
ロンドンに着いたのは夕方近くであったので、テート・モダンに行ってみた。閉館まであと1時間くらいしかないのに、特別展はソニア・ドローネーとアグネス・マーチン展。うーん、どちらにするか。結局、コンセプチュアルではなく、キュビズム的に分かりやすい?ドローネーを選んだ。
ソニア・ドローネーは夫、ロベール・ドローネーの妻として紹介されることも多いが、ロベールが1941年に亡くなった後も、戦後もフランスのデザイン界で活躍したソニアこそ、その業績を広く、長く紹介されるべきだ。というのは、ウクライナで生まれたロシア人であったソニアは、ロベールと結婚したため、長くフランスに住み、フランス人とも見まがうが、筆者は、そのキュビズム的要素は、革命後のロシアを席巻した構成主義の影響を感じ取ってしまう。ソニアがロベール亡き後、こだわったのは幾何学的枠組みに色彩をあやつる構成主義であり、イタリア未来派の連続性をも取り入れた、ある意味クレー的楽しさに満ちたドローイングであった。
ソニア・ドローネー展をなぜ選んだのか。それは、後述のテート・ブリテンで催されていたバーバラ・ヘップワース展とも相通じるが、そもそも日本では考えられない企画展であるからである。ソニア、いや、ドローネー夫妻でもいいが、キュビズムやイタリア未来派だけにしぼった企画展は考えにくい。しかし、ピカソやブラックが静物をいかに3次元的に動的に表現するかと悩んでいたあとの時代、未来派は動的な対象を「動的に」表そうとした。それは2次元で表現できる限界を伝えようとしたのかもしれない。
ところで、テート・モダンの入口を象徴していたタービン・ホールの巨大なインスタレーション(とにかく大きい「幕」は美術館全体を覆いそうなものであった)は、現在取り外されているが、これは、すぐ隣に建設中の新館の関係であるらしい。もともとテート・モダンは発電所・工場を再利用したもので、ポンピドゥーセンターやMoMAとはコンセプトが違う。この新館で、いかにイギリス風モダン・コンテンポラリーをプレゼンできるか。新館開館は2016年12月という。また、ここに来られるであろうか。(テート・モダンからミレニアム・ブリッジ、セントポール大聖堂を臨む)











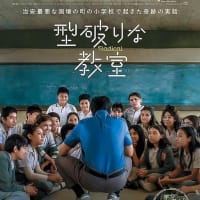













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます