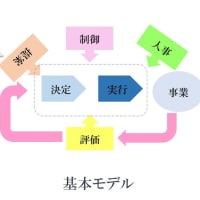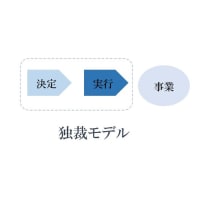秦の始皇帝の名を挙げるまでもなく、古来、不老不死を求める権力者は後を絶たず、今日では、グローバリストの富裕層がこの見果てぬ夢を追っているのかもしれません。古代にあっては、薬草や祈祷などに頼るしかしかなかったのですが、永遠の命を求める現代の権力者は、ITやAIというテクノロジーを手にしています。
こうした身体の機能を機械化する研究につきましては、日本国政府も、2020年にムーンショット計画を打ち上げています。ムーンショット目標1には、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」とあり、2050年も達成目標として、アバターとロボット技術の融合による「誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティック・アバター 基盤」の実現を目指すそうです。同目標では、一人の人が10以上の複数のアバターを捜査して多様な活動に参加できる社会を構想していますが、同目標をも超える技術として探求されているのが、精神転送です。ムーンショット計画の問題については後述するとしまして、本記事では、精神転送の結末について考えてみたいと思います。
精神転送とは、ウィキペディアの説明に依れば「人間の心をコンピュータのような人工物に転送すること」を意味します。ここで注目すべきは、転送されるのは、人間の‘心’である点です。このことは、ある個人の脳とそっくり同じ構造をもつ人工知能、あるいは、ロボットを作ろうと言うことではないことを意味します。後者であれば、クローン技術を用い得ればより容易に実現しますし、一卵性双生児の存在は、同一の遺伝子情報を有し、同一の脳構造を持っていたとしても、全くの別人格となることを示しています。つまり、精神転送とは、この世に一つしかないとされる個人の‘意識’を人工頭脳に移すのですから、遥かにハードルの高いプロジェクトなのです。
これまでのところ、精神転送には、理論的には様々な方法が考案されているらしく、基本的には人間の脳の電気回路を完全に再現するコンピュータを作製した上で、特定の人の意識をそれにアップロードするというもののようです。生きている間に移転する方法も、死後に移転する方法もあるのでしょうが、一つ、重大な点を見落としているように思えます。それは、人体の様々な感覚というものです。
現在において、視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚等の感覚を取り戻すテクノロジーは未だに出現していません。このことは、感覚に関する身体の器官を全て再現できないことには、たとえ意識を移転できたとしても、その人は、暗闇の中で生き続けなければならないことを意味します。見ることも、聞くことも、匂いを感じることも、食べることも、触ってみることもできないのです。永遠の命と引き換えに、ヘレン・ケラー以上に不自由な生活を覚悟しなければならないことでしょう(なお、視覚を失えば、自らの分身であるアバターを見ることもできなくなる・・・)。
また、たとえ人工頭脳によって思考できたとしても、発声器官が脳と繋がっており、言葉をもって他者と意思疎通を行なうこともできません。そもそも、聴力が備わっていなければ、他者の話を聞いて理解することもできないからです。もっとも、人工頭脳が発する電波の自動言語化、並びに、外部音声のデータ化等によってコミュニケーションをとることはできるかもしれません。実際に、今日、Chat GPTのように、AIを用いたチャットボットと音声で会話ができる時代を迎えています。しかしながら、入力された膨大なデータをベースとして反応するAIとは逆に、人工頭脳の基本データは、個人の転送された‘記憶’しかありません。生きている間に獲得した知識や情報に基づいて、人工思考回路を用いて他者と会話をしなければならないのですから、越えるべきハードルは、チャットボットより遥かに高いのです。
そして、何よりも人工頭脳に転送された‘意思’が恐怖するのは、予期せぬ故障が起きたり、トラブルやミスで電源が切れてしまう、あるいは、他者によって切られてしまうことです。永遠の命を求めて機械化したところ、ここでも機械の‘寿命’という問題に直面してしまうのです。また、人為的な場合には、殺人罪が成立するのか、と言う問題も派生します。この問題も、全く同一の後継人工頭脳を作れば良い、というお話にもなるのですが、同一の頭脳が作製できるのであれば、理論上では、いくらでもコピーが作れることとなります。となりますと、一つであるはずの個体の意思が無限に分裂してゆくこととなり、人類は、未知の世界に足を踏み入れることとなりましょう。
電源の供給をはじめ脳波の測定・出力からメンテナンスまで、あらゆる面で外部に全面的に依存し、無防備な状態にある転送された‘意思’は、果たして幸せなのでしょうか。暗闇の中で、毎日、誰かに突然に命を絶たれてしまう恐怖に苛まれるかもしれません。精神の転送とは、永遠の命ではなく、永遠の生き地獄なのではないかと思うのです。