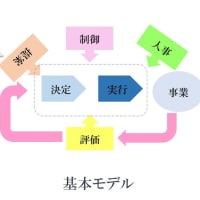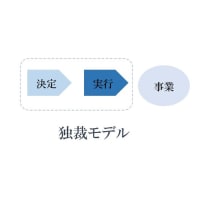日本国政府を始め、各国とも、ここ数年来、LGBTQ運動に踊らされてきました。同運動が掲げる‘大義’は、‘差別をなくそう’という誰もが否定しがたい標語なのですが、その背後に、マネー・パワーを牛耳る世界権力の意図が隠されていることは、これも誰もが薄々と気がついてきていることです。そもそも、世界権力によるグローバルな誘導がなければ、全世界で同一の用語を用いた社会改革運動が起きるはずもないのですから。それでは、LGBTQ運動の先には、どのような世界が待ち構えているのでしょうか。
非合法的な権力とも言える世界権力が目指している究極的な目的が自らによる‘人類支配’であるとしますと、LGBTQ運動も、この文脈にあって理解されるべきこととなります。そこで推測されるのは、ターゲットは、婚姻制度、とりわけ一夫一婦制ではないか、というものです。このように推測する理由は、そもそも奴隷は、奴隷主の所有物であり、その管理の下にある奴隷には、婚姻の自由がない、あるいは、著しく制限されてきた歴史があります。そして、何よりも、一夫一婦制は、夫婦間の相互愛が培われ、子供達が無償の愛を受けて育ち、家族が愛情を絆として助け合う幸せな家庭の基盤でもあるからです(このため、両親、あるいは、父母の一方しかいない子どもたちの場合には、愛情不足を補うために他の周囲の人々が配慮する・・・)。
確かに、キリスト教諸国をはじめとしてLGBTQの人々を罪人とする社会的慣習が根付いてきた諸国にありましては、同運動は、あらゆる理不尽な差別の撲滅という意味において‘正しい主張’のようにも見えます。個人の自己認識に基づくLGBTQが、刑法の適用を受けるような犯罪とは言いがたいからです。その一方で、おそらくLGBTQが社会的に忌避される傾向にあった理由は、一夫一婦制という家族制を健全な家族の基準としますと、この存在は、同規範的なモデルに対する脅威あるいは破壊要因となったからなのでしょう。今日にあっても、‘同性同士の婚姻を認めるべきか否か’という問題が常に議論を呼ぶのは、同家族モデルから逸脱してしまうからなのでしょう。もっとも、同性婚肯定派の人々にあっても、養子であれ、代理母であれ、何であれ、一家族として子を養育する場合には、カップルに両親役を想定しているのは、興味深いところです。それが生物学上の両性ではなくともLGBTQが一夫一婦制の家族像の枠内にあれば、家族制度に対する破壊的な作用としての働きは微弱であるのかも知れません(ただし、LGBTQ夫妻と“親子関係”にある子への影響については、精神医学や心理学におけるデータが不十分である以上、現状では判断できない・・・)。
世界権力のマネー・パワーの後押しでLGBTQに対す差別が解消されるとしますと、次なる差別解消の要求は、一夫一婦制に向かうかも知れません。何故ならば、そもそも、性差が一切考慮されない、あるいは、性差そのものが差別となるのであれば、婚姻という制度も存続できなくなるからです。戸籍等の出生時の登録にあって性別の記載が差別ともなれば、男女の両性の存在を前提とした婚姻という制度そのものも成り立たなくなります。つまり、一夫一婦制という制度そのものが差別的な制度となり、その廃止が主張されるかも知れないのです。馬鹿馬鹿しく聞えるかも知れませんが、パリオリンピック開会式の様子からしますと、世界権力は、そこまで考えているようにも思えてきます。
婚姻制度が消滅した人類社会を想像するのに参考となるのは、動物たちの世界であるのかも知れません。人類に最も近い動物は類人猿なのですが、類人猿では、‘一夫多妻制’が多々見られます。否、一夫多妻制と言うよりは、群れにあって‘主’となるボス猿による雌猿達の独占なのかもしれません。そして、仮に人類にあって同状態を受け入れる、あるいは、歓迎する人々か存在するとすれば、それは、今日の法律では禁じられながら、古来の伝統的な慣習を継承してきたユダヤ人かイスラム教徒といった一夫多妻制を認める人々となりましょう。しかも、飛び抜けて富裕な。何故ならば、経済力があれば、一人だけでも何人でも扶養することが出来るからです。この点からしますと、一夫多妻制の主張は、それが少子化対策の文脈であったとしても、複数の女性や家族を養うことが出来るほどの財力を有する人々、即ち、世界権力のための発言であったとも推測されるのです。
家庭というものが社会にあって私的な空間にして自立的な構成単位であり、かつ、無償の愛が人としての慈しみや思いやり心を育てるとしますと、一夫一婦制の婚姻制度の存在は、世界権力の目指す人類支配の目的にとりましては破壊すべき障害となりましょう。それ故に、LGBTQ運動とは、同目的を達成するための前段階なのではないかと、強く疑うのです(つづく)。