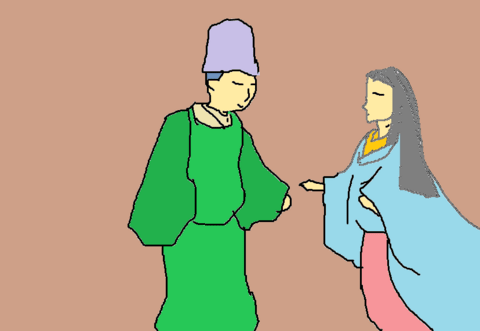
土日に大阪の実家に行っていました。「光る君へ」の最終回は大阪で見ました。母は全く興味ないから、私ひとりでシンミリ見ていました。
道長さんが亡くなるのは1027年と決まっているので、そこを動かすことはできないし、もっと病に苦しんだという話を聞いたことがありますが、ドラマの中では穏やかに倫子さん(黒木華さん)に最期を見送ってもらう形になりました。ちゃんと平安貴族として阿弥陀さまとつながるひもで結んでもらって、僧たちの祈祷もあったけれど、西の方へ向かっていったようでした。特に何かを訴えるとか、自分の人生をふり返るとかはしなかった。すでに道長さんは、引退していたし、オレがと語る場面はありませんでした。必要なかったのかもしれない。望月の歌を詠んだ回で道長時代のピークを語っていたのでしょう。

夫の死を目前にして、正妻の倫子さんは、まひろさん(吉高由里子さん)に枕元でお話をすることを依頼してしまいます。少しでも夫の願いを聞いてあげたい、そんな気持ちだったでしょうか。道長さんが望んだことではなかったかもしれない。とうとう公認の中として認められてしまいます。
史実は、たまたまスカウトした有能な人材で、その彼女が物語なるものを作っただけだったのかもしれません。道長と紫式部が深い仲だったのか、言葉を交わすことがあったのか、それはわかりません。多少の接点はあっただろうけど、幼なじみで恋仲であったのかどうか、それはわかりませんけど、今回の大河はそういう設定で動いていました。だからこそ『源氏物語』が生まれたのだという説得力は持っていた気がします。大河のおかげで女流文学が生まれた時代はこんなにして生まれ、摂関政治の衰えとともにまた消えていった。ほんの二百年程度で、その後の鎌倉、室町、戦国、安土桃山、江戸、どの時代にも女性たちが文学で大活躍する時代がありませんでした。
近代になって、何人も登場し、現代に至っていますが、長く女性の文学者が生まれない暗黒の時代があったのです。平安の一時期だけしかなかったんでしたね。
毎夜まひろさんは道長さん枕元に控えるようになり、連日母一人子一人というサブローの冒険譚をするようなことになります。時には後ろから道長さんを抱えて頭越しに話をする場面も作ってありました。倫子さんはそんなことは絶対にしなかっただろうけど、まひろさんだから、幼なじみだから、思い出話というのか、自分たちが生きてきたことをふり返っていたようでした。
何しろこのドラマは、小さい時の思いをずっと抱えながらそれぞれに生きて、社会に働きかけようとした二人の物語でもあったんでした。
物語とは、平安時代に生まれたものでした。その前の時代は、神話や神霊の話を伝えるものはありましたが、人間がさまざまに生きて、好きになったり、別れたり、悲しんだり、そういう主人公と読者がともに生きていくという形が生まれたんでした。十世紀の初めだったでしょうか。その少し前には、大唐と異国も滅び、よその国ながら、巨大な国であっても、忽然と消えてしまう、という時代背景もあったでしょうか。
誰かに聞いてもらい、誰かを励ますための、人間のための読み物として『枕草子』、『源氏物語』、『栄花物語』などが作られていった。それがたまたま十一世紀の摂関政治の頂点にあった藤原道長という人の生きた時代に提示されていきました。
物語は、誰かに聞いてもらわなくちゃというか、読者がどんな風に受け止めてくれるか、それを期待して自分の中にわき起こる登場人物たちを描いていくことになります。作中の人たちは、もう作者があるラインを作ってあげたら、自然に動き出すのでしょうか。そこまでいくのが大変なんだろうけど、ドラマの中ではお話は控えめな主人公の机の上から生まれていきました。

最終回は、道長さんの死、その後の人々、新たな世界を求めてまひろさんは東国へ向かっていく、そういう形で終わりました。史実では道長さんよりも十年ほど早く亡くなってしまったという話もあるようですが、はっきり決まっているわけではないから、それでまだお話は続くのだ。まひろさんは道長さんと手をつなぎ、宮廷に生きた。そして、時には宮廷の外にも出かけた。越前の国や、大宰府や、東国へも向かった。そんな物語を探す旅人の側面もあったのだよ、という暗示で終わりました。
私は、まひろさんとサブローさんの物語がテレビでは終わって、改めて紫式部さんの声を聴きたいなと、これからも日記と歌集を読んでいきたいと思います。ボンクラの私に感得できるわけはないと思うけど、あとをたどっていきたい、そんな風に思わせてくれた、本当にありがたいドラマだったと思っています。

















