
今日、11日の朝日新聞に「柄谷行人回想録」という連載に、近代文学の終焉というテーマで語っておられるようです。滝沢文那という記者さんがまとめているようなのですが、記者さんが「1992年の中上健次の死を近代文学の終焉の象徴として語ってきました」ね? と問いかけるのです。
記者さんは、それが大きなことのように取り上げたいみたいです。32年前くらいから少しずつ文学の砦は陥落しそうだったけれど、21世紀になってもうすでに廃墟になっているのかもしれない。
70年代の終わりには文学の終わりを意識するようになっていた。それがはっきりしたのが90年代だったんじゃないか。
個々の作家の問題ではない。例えば、テクノロジーの問題がある。近代小説を特徴づけるリアリズムという意味では、文章より映画やテレビの映像のほうが有利だとかいったことです。
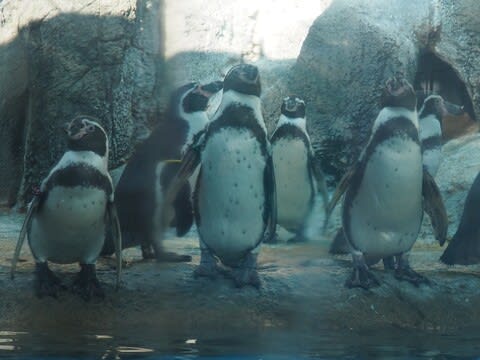
それから30何年、近代文学は人々の生活に入り込んでくるテクノロジーにやられたんだろうか。
そう、かつての人々は文学に希望をもって接していたような気がします。自分は読んでいないけど、誰かが読んでいるし、自分も読んでみたい。そして、門戸は数限りなくあって、何を読むのかというのが大きなテーマになるくらいに文学というのは、大きな希望の世界への入口でした。
他に、希望を見つける道具はなかったんだろうか。どちらかというと、文学以外の世界は、どれを選んだとしても、技術や資格、免許、特殊な世界での特別な知識・技能が要求されました。それらを手に入れたら、社会に出ていく道も見つかるようにはなっていた。
スポーツは希望の一つではあるし、今でもたくさんの若者が希望を抱いてその世界に入ろうとするけれど、そこから実際に生活をしていくためのお金を得られる人は、ほんの一部で、ほとんどすべての人たちは断念して、新たな道を探さなくてはならなくなります。
文学は、そもそもお金にならないし、生活もできないし、何の役にも立たないし、時間が失われてしまうし、いいことなしなのに、どういうわけか、人間たちが生活していくうえで、それを手にすることで希望を得られる、何か心に残るという、きわめて心理的な、お金にならないものしか得られない、とんでもないものでしたが、そこで希望を得る人はいました。
けれども、文学は、自分で若者を巻き込んでいく力を持っていなかった。ただポカンとたくさん存在しているだけで、「いつでもどこでも接することができるから、いつでもおいで」と待っているだけでした。
たまに、映画やアニメ、大ヒットしたものの原作ということで少しだけブームになることはあっただろうけど、そもそも文学は自分から動いたりしなくて、ただ待っている存在でした。
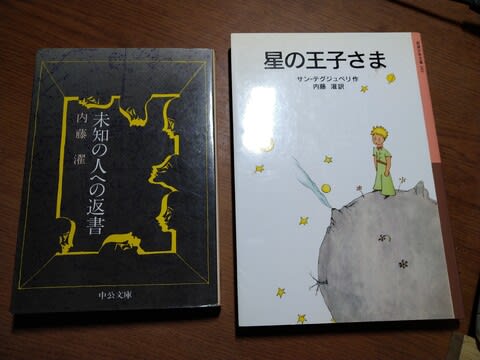
それが、この30年の間に、誰からも呼ばれなくなったというのです。それは確かにあるかもしれない。ベストセラーとして売れる本はあっただろうけど、それらは文学ではなかったのかもしれない。
柄谷さんは、文学というのは、それが生まれた地域の差異から出てきたと言います。
例えば、ゴーゴリ独特のリアリズムは、先進国では失われた濃密な共同体がロシアに残っていたことから生まれた。日本の夏目漱石も、コロンビアのガルシア・マルケスも、それぞれの社会独特の背景から生まれた。当たり前のようだけど、重要です。
90年代から、それぞれの地域や社会には、それなりの特色があったのかもしれないけれど、どこもかしこも経済と豊かさと同じような文明を求めてきて、均質化されつつあるというのは確かですね。
スマホは、たぶんアフリカでも、ロシアでも、ひょっとすると北朝鮮でも普及しつつあるのかもしれない。あの通信機欲しさに世界の人たちは必死になっているし、若者たちは当然のものとして受け入れている。
世界がバラバラに見えていても、豊かさとスマホとさらなる発展を求めていて、地球だけでは物足りなくて、月や火星や木星と、新たなフィールドを求めているし、そこへの先陣争いは今も続いています。

小さくいじけて「文学に希望を探すのだ」なんて、全くナンセンスになりました。「おまえ、ひとりで文学でもひねくっていろ! バカ!」と、誰からも相手をされなくなっています。
近代文学、つまり小説が決定的な意味を持つ時代は終わりました。だけど、それは必ずしも文学は消滅するとか無意味だとかいったことではないんですよ。才能のある作家は常に出てくるとか、文学を読む人は少数でもいなくなるということはない、といった反論がありましたが、それとは別の話です。
これからも新しい才能は出てくるし、小説を読む人はなくならない。けれども、文学が世の中に大きな意味を持った時代はもう終わった、のかもしれない、という柄谷さんのことばです。
続いていくけれど、例えば核戦争を止めるとか、ロシアやイスラエルの暴走を止めるとか、南米から独裁政権やテロがなくなるとか、そんな力はないかもしれない。それでも、ことばを大事にする人が、世の中を変えていってほしい、なんて私は思うのです。



















