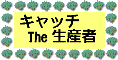2/9~11に開催された「世界グルメサミット」の展示ルームでは、
「ユーハイム」と「虎屋」を中心としたデモンストレーションがありました。
せっかくの機会なので、これはもうぜひ拝見せねば!と、いくつか見て(&食べて)きました。
まず第一弾は、ユーハイムの安藤 明マイスターによるステージで、
「ドイツの伝統菓子バウムクーヘン 日本の食材への挑戦」
安藤マイスターのステージのテーマを事前に知らなかったのですが、
私の愛する「バウムクーヘン」とはラッキー

安藤明氏は1978年にドイツに渡り、その年にドイツの製菓マイスターを取得。
以来、ユーハイムといえば安藤マイスターといわれるほど有名な存在で、特にバウムクーヘンにかける情熱は比類なく、「マイスターの手焼きバウム」というスペシャルなバウムを作っています。
*このバウムについては、以前に紹介しています(2009/1/31)

今回の安藤マイスターのお話は3本立てです。
1.マイスターの手焼きバウム
昔々の時代、ウサギなどの小動物を狩猟し、木の枝に刺して火であぶって食べていたのがバウムクーヘンの元の元です。
古代エジプトでは、水と粉で練った生地を棒に巻きつけて焼いていました。
その後、13世紀、14世紀と上がってくるにつれ、ハチミツ、卵、乳製品などが加わるようになり、だんだんお菓子らしくなってきます。
ドイツでは、ベルリンを中心に、コトブス(ポーランド国境近く)、ドレスデンなどの各地方でそれぞれの特徴(マジパンを多く使う等)を持ったオリジナルのバウムクーヘンがつくられてきました。
安藤マイスターの「マイスターの手焼きバウム」は、ドイツのそれぞれの地方のいいとこどりをして作ったバウムクーヘンで、2008年の姫路博において、内閣総理大臣賞を受賞したとか

バウムを作る際には、生地60、焼き60というくらい、どちらにも気を遣うとのこと。
バウムの材料は、卵、バター、砂糖、粉とシンプルなので、素材を厳選するのはもちろん、テクニックもかなり微妙な加減が必要なようです。
ユーハイムでは、バターはフレッシュバターのみ、粉は水分の吸収率が他より2%多いメーカーのものを使い、季節によっても生地の温度を変え(平均28℃)、窯も独自で開発したものを使っています。
ヨーロッパではグラム売りが基本ですが、日本ではギフト市場も大きいので、きれいに成形したものは必須で、その他にも薪型etc...と、ユーハイムでは色々なバリエーションのものを作っています(私は薪型のデアバウムが好き )
)

ザックリと大胆にカットする安藤マイスター

バウムは、削ぎ切りした時にひとつひとつの層がバラバラ剥がれずに密着していなければならないとのこと。
また、今はやわらかいバウムが人気で、他社で色々出ていますが、安藤マイスターは生地がみっちりと詰まったバウムを基本にしているということで、ああ、やっぱり、ユーハイムのバウムは私好みだわ~と再確認しました。

バウムはどこを切っても「樹」の模様が出てくるということで、たしかに納得!

この形の端っこは初めて見ました!
2.バウムリンデ (=木の皮)
和の食材ということで、小麦粉の代わりに大豆粉(キナコになる前の状態)を使い、あんこ、マジパン、キンカンのコンフィチュールをサンドして重ねています。

バウムリンデの上は寒天に和三盆糖を入れ、豆を散らしています。

全体的にしっとりとした食感で、キンカンのコンフィチュールの甘酸っぱさがとても生かされていると思いました。
3.パステーテ (=詰め物)
小さいバウムに純米酒に和三盆糖を加えたシロップを塗り、中に2種類のあんクリームを詰めています。

底は小豆あん+生クリームのペーストを絞りいれ、その上に5種類の豆(煮豆)を散らし、上に白あん+生クリームのペーストを絞ります。

大豆粉をふりかけ、生クリームを載せ、豆とチョコのチュイールで飾ります。
これはけっこうボリュームがあります!
あんこと生クリームがとてもよく合い、あんこ好きには嬉しいマリアージュ
大きなバウムを自分でデコレーションしてオリジナルのパステーテを作り、デコレーションケーキとしてサーブしたら面白いし、喜ばれるかもしれません。


ゼイタクなバウム3種盛りが試食で配られ、たっぷり味わわせていただきました

「ユーハイム」と「虎屋」を中心としたデモンストレーションがありました。
せっかくの機会なので、これはもうぜひ拝見せねば!と、いくつか見て(&食べて)きました。
まず第一弾は、ユーハイムの安藤 明マイスターによるステージで、
「ドイツの伝統菓子バウムクーヘン 日本の食材への挑戦」

安藤マイスターのステージのテーマを事前に知らなかったのですが、
私の愛する「バウムクーヘン」とはラッキー


安藤明氏は1978年にドイツに渡り、その年にドイツの製菓マイスターを取得。
以来、ユーハイムといえば安藤マイスターといわれるほど有名な存在で、特にバウムクーヘンにかける情熱は比類なく、「マイスターの手焼きバウム」というスペシャルなバウムを作っています。
*このバウムについては、以前に紹介しています(2009/1/31)

今回の安藤マイスターのお話は3本立てです。
1.マイスターの手焼きバウム
昔々の時代、ウサギなどの小動物を狩猟し、木の枝に刺して火であぶって食べていたのがバウムクーヘンの元の元です。
古代エジプトでは、水と粉で練った生地を棒に巻きつけて焼いていました。
その後、13世紀、14世紀と上がってくるにつれ、ハチミツ、卵、乳製品などが加わるようになり、だんだんお菓子らしくなってきます。
ドイツでは、ベルリンを中心に、コトブス(ポーランド国境近く)、ドレスデンなどの各地方でそれぞれの特徴(マジパンを多く使う等)を持ったオリジナルのバウムクーヘンがつくられてきました。
安藤マイスターの「マイスターの手焼きバウム」は、ドイツのそれぞれの地方のいいとこどりをして作ったバウムクーヘンで、2008年の姫路博において、内閣総理大臣賞を受賞したとか


バウムを作る際には、生地60、焼き60というくらい、どちらにも気を遣うとのこと。
バウムの材料は、卵、バター、砂糖、粉とシンプルなので、素材を厳選するのはもちろん、テクニックもかなり微妙な加減が必要なようです。
ユーハイムでは、バターはフレッシュバターのみ、粉は水分の吸収率が他より2%多いメーカーのものを使い、季節によっても生地の温度を変え(平均28℃)、窯も独自で開発したものを使っています。
ヨーロッパではグラム売りが基本ですが、日本ではギフト市場も大きいので、きれいに成形したものは必須で、その他にも薪型etc...と、ユーハイムでは色々なバリエーションのものを作っています(私は薪型のデアバウムが好き
 )
)
ザックリと大胆にカットする安藤マイスター

バウムは、削ぎ切りした時にひとつひとつの層がバラバラ剥がれずに密着していなければならないとのこと。
また、今はやわらかいバウムが人気で、他社で色々出ていますが、安藤マイスターは生地がみっちりと詰まったバウムを基本にしているということで、ああ、やっぱり、ユーハイムのバウムは私好みだわ~と再確認しました。

バウムはどこを切っても「樹」の模様が出てくるということで、たしかに納得!

この形の端っこは初めて見ました!
2.バウムリンデ (=木の皮)
和の食材ということで、小麦粉の代わりに大豆粉(キナコになる前の状態)を使い、あんこ、マジパン、キンカンのコンフィチュールをサンドして重ねています。

バウムリンデの上は寒天に和三盆糖を入れ、豆を散らしています。

全体的にしっとりとした食感で、キンカンのコンフィチュールの甘酸っぱさがとても生かされていると思いました。
3.パステーテ (=詰め物)
小さいバウムに純米酒に和三盆糖を加えたシロップを塗り、中に2種類のあんクリームを詰めています。

底は小豆あん+生クリームのペーストを絞りいれ、その上に5種類の豆(煮豆)を散らし、上に白あん+生クリームのペーストを絞ります。

大豆粉をふりかけ、生クリームを載せ、豆とチョコのチュイールで飾ります。
これはけっこうボリュームがあります!
あんこと生クリームがとてもよく合い、あんこ好きには嬉しいマリアージュ

大きなバウムを自分でデコレーションしてオリジナルのパステーテを作り、デコレーションケーキとしてサーブしたら面白いし、喜ばれるかもしれません。


ゼイタクなバウム3種盛りが試食で配られ、たっぷり味わわせていただきました





































 可能性もあるかも?
可能性もあるかも?





 「ワイン村.jp」 (社団法人日本ソムリエ協会 オープンサイト)(2004年5月~2008年12月終了)に連載していた「キャッチ The 生産者」(生産者インタビュー記事)を、こちらにアップし直しています。
「ワイン村.jp」 (社団法人日本ソムリエ協会 オープンサイト)(2004年5月~2008年12月終了)に連載していた「キャッチ The 生産者」(生産者インタビュー記事)を、こちらにアップし直しています。