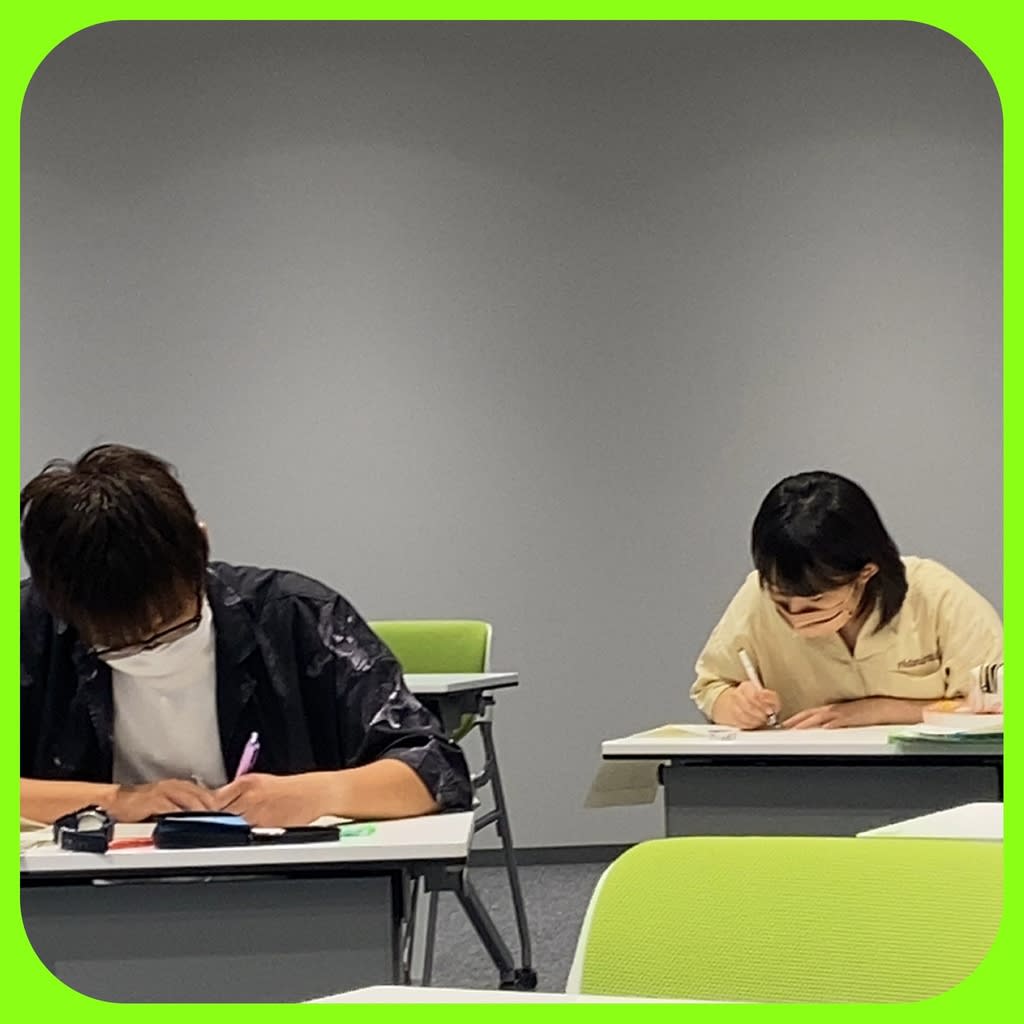
わたしは、大学で教員志望の学生を支援する授業も担当しています。
教員採用試験合格のための指導がおもな仕事ですが、派生して卒業後の生活についても女子学生と話すこともよくあります。
将来像を聞いていると、いったん教職に就くことができたら、できるだけ長く勤めたい。
自分の子どもはもどうしてほしいとは思わない。
このように考えている人は少なくはないというのが、現場の実感です。
さて、就職情報サイトは、2025年3月に卒業予定の大学生・大学院生を対象にしたインターネット調査をしました。
その結果、5人に1人(約19%)が「子どもはほしくない」と答えました。
女子学生は23.5%で、男子学生は12%ほどでした。
これをみる限り、女子学生は、およそ4人に1人が、子どもはほしくないと考えているということです。
続いて男女にその理由を尋ねると、
「うまく育てる自信がない」がいちばん多く、次に「自分の時間がなくなる」と「経済的に不安」という理由でした。
それらの理由が挙がるのには、さまざまな要因があると、わたしは考えます。
学生の自己肯定感の課題、ダイパやコスパを重んじる特性、今直面している物価高など、複合的に子育ての難しい時代を反映しているように思います。
また、同じ調査で、男女で共働きをするのが当然と考える学生が7割にのぼりました。
そうなると、育児休暇を取ることの仕事への影響が不安になることや、育児・家事の分担がアンバランスで女性のウエイトが高いという現状を女性がより強く感じることになります。
女子学生のほうが、男子学生よりも、「子どもをほしいとは思わない」と答える比率が高くなっているのも、納得がいきます。
ただ、一つ言えることは、日本での少子化の流れは今後変わらないのではないかということです。
そうなると、働き手が減り、消費者の絶対数が減少するので、経済は停滞したままになるでしょう。
少子化対策は、待ったなしであり、場当たり的な対策では効果がなく、総合的な対策を断行しないと流れは止まりません。
なぜなら、述べたように少子化は複合的な要因が関連しあっているため、複合的な要因に対しては、総合的な対策が必須になるからです。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます