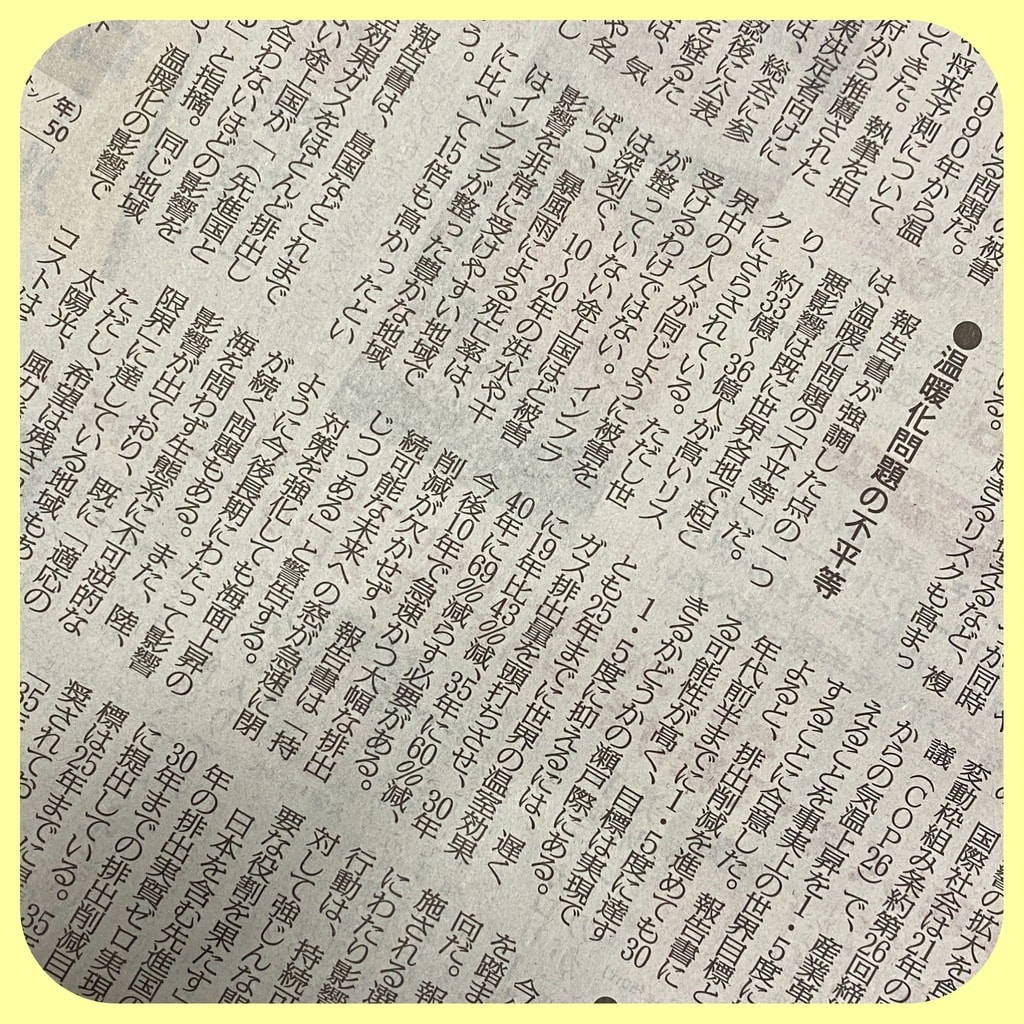
この頃はインターネットをはじめとして、私たちはたくさんの情報に囲まれています。
わたしの子どもの頃は、ものを調べるには図鑑や百科事典を開けるのがふつうでした。
家には2種類の百科事典がありました。
一つは「ジャポニカ」という百科事典であり、他の一つは「万有百科事典」というものでした。
「ア〜エ」などの用語の頭文字で始まる言葉が1冊にまとまっていました。
1冊の厚みは8cmほどでした。
当然、索引で分けていくとア〜ンの全部が揃うと何冊にもなりました。
だから、置いておくにも大きなスペースが必要でした。
ところが、半世紀の間にインターネットの普及で、情報の集積は場所をとらないようになりました。
隔世の感を覚えます。
調べたいことは、スマホ一つでことたります。
洪水のような情報が私たちに押し寄せてきます。
前のように重い本を手に取り、調べなくてもすぐに情報が手に入るようになりました。
ただ、その情報が全部正しいかといえは、けっしてそんなことはありません。
意図的にまわすフエィクニュースがあります。
SNSの書き込みには、悪意のある書き込みや無責任な発言もあふれています。
とくに学術的な記事や文章は、詳しくないと真偽を確かめにくいという困ったことが起きてきます。
いわゆるメディアリテラシーが求められます。
つまり、情報をいろいろな角度から他の人の意見やちがった観点の意見から、根拠をもって考える習慣を身につけたいのです。
その点で、新聞の記事の活字は正しい情報になっていることが多いと思います。
新聞は裏付けをとり、記事の信憑性は高いからです。
ただし、新聞とて記者が「こういう内容にしたい」という思いで、それに都合のいい題材だけを集めていないかというクリティカルな見方で読まなければならないと、わたしは思います。
大切なのは、わりとまっすぐに情報をうけとりやすい子どもたちが、メディアリテラシーの力をつけていくことです。
その教育をしっかりやっておかないと、大学生になったとき、インターネットから情報をとり、それを貼り付けてレポートにしてしまうようなことになります。
また、ニセ情報に振り回されることにもなります。
わたしが驚いたのは、在日外国人をテーマにした学習をするとき、若い教師がインターネットからとってきた情報で教材をつくり、それを知識として教えようとしていたときです。
在日外国人の問題を事実に基づき、客観的に見た立場で作った教材にはほど遠いものでした。
修正を加え添削すると、教材のほとんどを書き直すようなものでした。
児童生徒もですが、教師こそメディアリテラシーを身につけておかないとたいへんなことになると思いました。










いつもバランスの取れた考え方のブログなので、
比較的安心して読まさせていただいて居ます。
今回の内容は少し気になったので〜
私の老いた父親は、大手新聞社で高い地位迄上り詰め、その後,社会系の大学教授になりました。
ですから、マスコミの裏表や限界も聞いています。
民間、つまり利益を上げなければいけない資本主義のマスコミの場合は、どうしてもスポンサーの影響を受けます。
例えば、 電力会社は必要経費を掛ければ掛ける程,利益を出す事が出来る、総額原価方式の経営の為、
宣伝費に多額をつぎ込めます。
すると広告主を失いたくないので必然的に無言の圧力が掛かるという構図になります。
福島の原子力発電所の事故まで、日本の原子力発電所でメルトダウンはおろかメルトスルー迄する事故が起きると考える事が出来る人が、日本人でどれ程居たでしょうか?
あの事故の時、日本のマスコミの現実に、私は絶望感を抱きました。
東大の先生が嘘ばかりつく方ばかりなのにもビックリで、それをそのまま 報道するマスコミ。
危険性を指摘した人々に対する明らかなバッシング等、メディアコントロールを感じました。
(機械設計のプロから原子力発電所の怖さを知り、広島の被爆者の知人がいたので被爆の恐ろしさを知っています。また 阪大原子力学部大学院生が被爆の事を全く理解していない事に愕然としました)
嫌な事ですが、
マスコミの報道は常にどこかの影響を受けていると考える必要があると思います。
お金のつながりはどうなっているでしょうか?
本当のその組織の力関係はどうなっているか?
(例えば IAEAとWHOの力関係)
その会社は誰が作り,若しくは大きくしたか?
きっちり 調べなければ真実は見抜けないと思います。
(例えば、読売新聞を大きくしたのは正力松太郎
彼はアメリカのCIAの意向のままに動く存在であり、日本の原子力法案 第1号を中曽根元首相と一緒に提出した)
確かに 新聞社の方々はよく調べています。
しかし、最近の若い記者は疑うことを知らないのか?
父親は[取材不足や勉強不足だ!]と叱咤激励の手紙をよく後輩に書いています(笑)
音声変換でしたので長くなりました。
失礼致します。