
上野の科博で開催されていた
「医は仁術」* 終了前に滑り込んだ。
奇天烈な展覧会ですごく面白かった。
10年近く
東京医科歯科大学の解剖学教室にいた。
自分にとっては
とても大事な時期をそこで過ごさせていただいた。
許してくれた大学の先生方のおかげだ。
それから絵画の制作中心の生活になって5年ほど経つ。
大学に居た頃とは違った視点で
これらのものを見ることが出来るのは、また楽しいことだ。
解剖図を作るときは、正確さが第一に求められるので
海外の、特にドイツの本を参考にしながら作った。
シャープで正確、がっちりして人体の比率も美しい。
一方
今回「医と仁術」で見た江戸時代の解剖図は
シャープさに欠けた
ぼよーんと丸っこい形
ふんわりとした淡い着色。
日本って、こうなんだよなぁ…
木と水の風土
朽ちることを許す文化
湿気の多いこの時期に思う。
いくら近代化されても日本の風土は残っている。
解剖図を見るというよりも
忘れつつある日本らしさを堪能した。
それは欧米文化より遅れているとは全く思わない。
むしろ誇るべきものだと思う。
舌のあれこれ
限られた絵の具の濃淡で描き分けられている。
上に少し写っている
医療器具が痛そうでやばい(;゜ロ゜)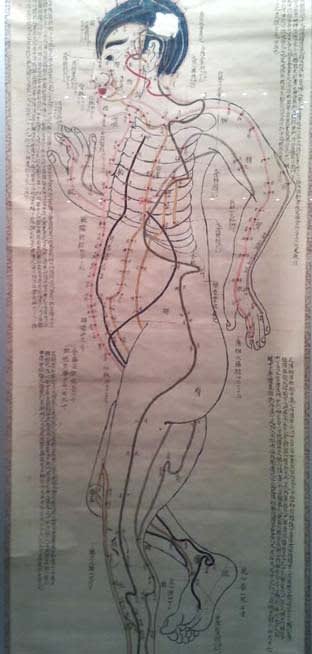
経絡でしょうか。
やはりプロポーションが独特です。
妊婦さんの人形模型
手前にある胎児や骨のパーツは、
母胎の中におさまるんでしょうね。
骨盤の恥骨結合が開いていますし(妙にリアルで気になる)
足が関節になっていてお産の体勢を作ることができそう。
よく出来ています。
医療機器を作る人が見たら
また別の視点があって面白いんでしょうね。
今年は何人かの友人がお産をひかえています。
「おなかの中に魚がいるみたい」
海、ですか?
*国立科学博物館 http://ihajin.jp/

先日、プレス式コーヒーメーカーを買いました。
迷いましたよ。
ボダム、ハリオ、青芳など
値段とデザインを天秤にかけ…
デザインとはつまり、私が割りにくそうなデザインのことで
見た目のかっこよさではありません。
で、結局ハリオ*¹ にいたしました。
ガラス部分は日本製、
分解して洗えること。
取っ手部分はガラスとは別になっていること、
ガラスと一体型だと割りやすい。
底には足がついていて、ガラスがテーブルに直接触れないこと、
その方が冷めにくい。
そして何より値段が手頃なこと
などなど比較してこれになりました。
豆はミルでひきますが
この時、たまらない良い香りがいたします。
3分待って…
青い粒が見ていて飽きない。
「甘み」「きれ」など、コーヒーの宣伝文句には
今まで「どこが?」と思っていたが
本当にあるんだなぁと実感。
これなら牛乳混ぜる派の私でも
ブラックのままいただけます。
ところで
そろそろ検診を受けようと思い
資料を探していたら
そのファイルの中から偶然家族写真が出てきた。
かつて品川パシフィックホテルに
楼蘭*² という中華料理店があった。
記念日にはその店で、家族でよく食事をした
その時の写真だ。
やせ衰えた父の姿が写っているので
父の最後の誕生会(8月)かと思って日付を見たら
なんと最後の父の日だった。
父が亡くなる年は、
それは死が近いのだと
誰が見てもわかるほど激痩せしていたので
その運命に逆らうかのように
たびたび楼蘭で食事をした。
今から思うと、皆むきになって食べていた(笑)
父は食べられないっちゅうに。
あなたと一緒に食事をしたい、という家族の猛アピールだったのだ。
本当に食べるのが好きな家族
今年も父の日が近づいて
その公告を目にするたびに、なんというか…
本当に写真になって現れてくれた。
*1ハリオ http://www.hario.com/
*2楼蘭(銀座店) http://loco.yahoo.co.jp/place/g-3N40MoXV7_c/

待ちに待った、温泉旅行に行く
まずは小諸城址懐古園*¹ へ。
道は渋滞もなく すいすい
途中、首長竜みたいな形の雲
小諸懐古園には「イロハ英男ガッパ」というのがいて
身体の悪いところをなでると良いというので
腰のあたりを なでなで した。
先日、
妊婦さんのおなかを なでなでさせてもらったが
想像以上に気持ちよくてクセになりそうだ。
なので、別の妊婦さんのおなかも なでなでさせてもらう約束をした。
良いことがありますように❤

ツツジがとてもきれいでした。
懐古園を出て、
次には布引観音*² へ
あんな断崖絶壁に観音堂があります。
このスポットにたどり着くのさえ、大変だった。
これ以上登るのはやめました。
宗教建築物はクレイジーだ。
「ここまでしないと、救われない」
修行だ修行だ!!
…的な感じを受ける。
それは古今東西、共通しているように思う。
不幸から救われるための信仰だろうに
信仰のために、わざわざ不幸を増やしてるような気がします。
今
「死の欲動」*³ という本を読んでいる。
著者は精神科医 熊倉伸宏
その中に、「悪性の運命」について書かれているところがある。
患者ではない正常な人の中に
決まって同じような不幸を繰り返す人達がいるという。
当人は単なる不幸と思っているが
実は不幸な運命を内的理由から反復脅迫している場合がある。
快楽の見込みのない過去の体験を好んで反復するのである。
これは反復脅迫と快楽原則の比較の中で、挙げられた事例だが
反復脅迫は快楽原則と対立し、より「蒼古的」で「悪魔的」だと書かれている。*⁴
はっきりと説明はできないが、
古来からの信仰や宗教と、この「悪性の運命」は
どこかで繋がっているような気がしてならない。
人はそもそも、そんなに幸福にはできていないのではないか?
まぁその価値判断さえ私の傲慢かもしれませんね。
この本はもうすぐ読み終わるが
死の欲動に取り憑かれた人に対して
「このようにしたら良い」などといった
結論は書かれていない。
試行錯誤しながら生きていくしかないのである。
温泉旅行の話でしたよね…
*1 小諸懐古園 http://www.city.komoro.lg.jp/category/institution/kouen/kaikoen/
*2 布引観音 http://www.city.komoro.nagano.jp/www/contents/1248916342456/index.html
*3 「死の欲動―臨床人間学ノート」熊倉伸宏 新興医学出版社 (2000/05)
*4 引用 p.107より









