「紙一枚、鉛筆一本」で「お絵かき」は始まるのだけれど、小学校や中学校での美術の授業にあったような「面白ければよい」で始まって、それで終わる方法では、今日、アートと呼ばれる中身のない行為で終わる。勿論、面白くなければ、まともな始まりも結果もない。何かを成し遂げようとすれば「理念と、その実現のための方法」が必要だ。そして結果のクオリティを求めるならば「技巧・技能」というものが不可欠だ。
紙一枚の中に虚構世界を描き出すためには「能力」が必要だ。ルネッサンスの時代には宗教画が終わって、自然や現実から学んだ世界が描かれるようになって、それは作り出す者たちの間では、いかに「無いものを在るが如きに」作り出せる能力を競い始めた。
私が画学生を始めたころ美術関係の雑誌と言えば「芸術新潮」「芸術生活」「美術手帖」と言うのがあって、芸術新潮は先に述べた「能力を競った美術」を紹介していたが、一方美術手帖は当時流行りの抽象画を主に紹介する雑誌であった。浪人生と言えどもこの美術手帖を小脇に抱えて気取って歩くのが流行っていた。しかし私には「美術手帖」は糞であった。
私にとって「能力」こそが信奉の神の賜物であり、訳の分からない「観念」に引きずられて「感性」を奪われていくのは許せなかった。小学校、中学校の美術の延長では「やりたい放題」「永遠に試しが許される表現」など、私には受け入れない行為だった。さて、今に見ろ!!・・・・AIがこのレベルの行為で生み出されるものを飲み込んでいくだろう。いろんな情報を与えると「作品??」を生み出してくれるなんて馬鹿げている。
その内、AIが物質社会を均等化し、精神生活を退屈なものにするだろう。そのとき人間の多くは自分の精神性を再構築しないと、AIの奴隷になるだけだろう。しかし同時にAIに対する拒否反応も始まっているが・・・・どうやって自分が作り出せるものとAIが作り出すものを分けられるだろうか。また他の人達と自分はどう違うのかを確認しないでいられるだろうか?特に集団主義のこの国と欧米では方向性は大きく異なるだろう。
70年代に大学生の間で政治運動が流行り、社会に対する疑念、当時の民主主義に対する不満が芽生えていたはずだが、80年代に小泉純一郎と竹中平蔵の唱えたグローバル社会と人材派遣会社の解放で、一気に個人の生き方の基本の方向性は失われてしまった。それこそAIならぬ小泉竹中マジックで集団主義が個人の能力を失わせた。今またAIで個人の中にある「感性」が見失われてはいけない。この国の国民性になってしまった集団主義から個人を大切にする個人主義を育てるなんて、私個人の力では何ともしがたい。
だから私が絵画教室の先生をするなら個人主義的な方向性を与えることで「個人の素質」を見出したい。正直言って、物を作り出すのに、誰にも才能があるわけではない。しかし「基礎力」を与えれば、個人で展開できる。AIに惑わされることはない。
その基礎力とは①目の前にあるものを正確に捉える、②それを紙の上に再現する ③自分の感性と他人の感性が異なることを感じ取る、 ④自分が最も快く感じる世界を作り出す
この時こそ「唯我独尊」である。
















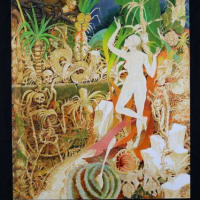


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます