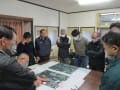気仙沼市本吉町表山田・三段田地区では、地域農業の継続・発展に向けて、今年度、高収益作物の候補としてえだまめとさつまいもを選定し、試験栽培に取り組みました。
令和5年12月14日、地区の中心経営体及び主要農家8名が集まり、試験栽培の振り返りを行いました。担当農家から収支報告がなされ、続いて、普及センターから、試験栽培で明らかになった成果、課題とその対応策について説明し、来年度に取り組む内容について提案するなど、農業者と意見交換をしながら検討しました。その結果、えだまめは、高収益作物の候補品目になり得るとの合意に至り、本作に取り組もうとする意欲が感じられました。
普及センターでは、今後も地域の取組を支援していきます。
<連絡先>
宮城県気仙沼農業改良普及センター 地域農業班 TEL:0226-25-8068 FAX:0226-22-1606