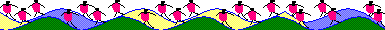【我が家では楸〔キササギ〕と呼ぶ。最近野性化してるらしい。】
今は昔となりにけり。私の祖先のある女性が腎臓を患い
とても苦しんでいたという。何しろ薬の無い時代のこと。
その女性のご主人は、妻の病を治す方法はないかと
農閑期に、あちらこちらと旅をしたのだった。
ある土地で博学の旅人に出会いこんな話を聞いたという。
「キササギの実を煎じて、その汁を飲ませると良い。」
彼は親切にも、そのキササギの実をたくさんくれたという。
ご主人は急いで帰路に着き、煎じ汁を奥さんに飲ませたら
緩やかにではあるが、女性は快気し、当時としては長命で
夫婦仲良く命を全うしたということだ。
その話を親から聞いた私の祖父は
我が家にキササギを植えたのである。
正式名キササゲはノウゼンカズラ科の落葉高木である。
キササゲは中国原産で、高さは5~10mにもなる。
樹皮は黒褐色、葉は大きく、キリの葉に似ている。
花期は6~7月。漏斗状で先の5裂した淡黄色の花を
円錐状につける。紫色の斑点をつける花の種類もある。
果実は秋にでき、細長いさく果でササゲ(大角豆)に
似ているのでキササゲ(木大角豆)とも呼ばれている。
楸は(ひさぎ)と読む。「きささぎ」も間違いでは無いと言う。
■〓〓〓■〓〓〓■〓〓〓■〓〓〓■〓〓〓■
日本へは元々、薬用植物として導入されたが、
段々、河川や小川のほとりなどで野生化し、
今では、あまり家庭では栽培されていない。
実はこの果実に利尿作用があることが分かっている。
また研究の結果、腎炎・妊婦浮腫・脚気などの浮腫に
効果があることも実証されている。
しかし、医療用の漢方薬には使われていないようだ。
あくまでも、民間の漢方薬として使われている。
ただし多量に服用すると悪心・嘔吐・徐脈などの
副作用がみられることがあると言う。
西洋医学も東洋医学も普及していない大昔。この果実で
ひとりの女性の命が助かったことは紛れも無い事実だ。
だからこそ、祖先を大事にした我が祖父は家の庭にではなく
畑の隅や用水路の脇に、たくさん植えたのである。
理由は簡単。「誰でもこの実を採っても良いですよ。」だ。
そんなこととは知らない私。幼い頃、この実をもいでいる
人を何度も見たことがある。《この実に何の効果があるの?》
時は流れ、たくさんあったキササギも一本になってしまった。
老木となって枯れたり、用水路の工事で切り倒されたのだ。
でも、今でもその一本の木の果実をもぐ人を時折見かける。
母は祖父からこの話を聞いて当然知っており
果実をもいでいる人と話をよくする。
聞けば、医者に見離された家族が最後の頼みの綱として
キササギの果実を探していると口を揃えて言うらしい。
数年前、母はキササギの木を裏庭の用水路付近に植えた。
そう、冒頭の写真である。命は次の時代に受け継がれ
先人。祖先の心も次の世代に受け継がれているのである。
キササギは我が家の守り神なのかもしれない。
【キササギの花。時代は変わろうと花の心は変わらないのだ。】