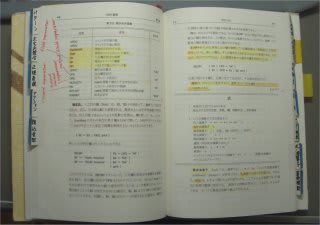エレーヌ・グリモー(Pf)のラフマニノフ「ピアノソナタ第2番」と「練習曲集《音の絵》」(DENON,COCO-70754)を聞いている。後に手直しはされているようだが、ピアノソナタは1912-3年の作曲、《音の絵》作品33は1911年、作品39のほうは1916-7年の作曲だという。
1910年にマーラーの「千人の交響曲」が初演され、1912年にはタイタニック号が沈没、1913年にはストラヴィンスキーの「春の祭典」が初演、1911年にはプロコフィエフのピアノ協奏曲第1番が完成し、翌12年に初演されている。そんな時代背景を考えると、ラフマニノフの音楽はずいぶんロマンティックに聞こえる。少なくとも、当時のモダニズムとは遠い位置にあったことだろう。
このCDは、1985年の7月にオランダのライデンで録音されたもので、エレーヌ・グリモーがパリ音楽院を卒業する15歳の年の録音であるという。少女の内面にある音楽的な感情が表出されている、優れた演奏だと思う。
人気blogランキング
1910年にマーラーの「千人の交響曲」が初演され、1912年にはタイタニック号が沈没、1913年にはストラヴィンスキーの「春の祭典」が初演、1911年にはプロコフィエフのピアノ協奏曲第1番が完成し、翌12年に初演されている。そんな時代背景を考えると、ラフマニノフの音楽はずいぶんロマンティックに聞こえる。少なくとも、当時のモダニズムとは遠い位置にあったことだろう。
このCDは、1985年の7月にオランダのライデンで録音されたもので、エレーヌ・グリモーがパリ音楽院を卒業する15歳の年の録音であるという。少女の内面にある音楽的な感情が表出されている、優れた演奏だと思う。
人気blogランキング