11月28日(日)、標記を私の研究室のPCからZoomを使用し、次のような時間帯で実施しました。
令和3年11月28日(日)13時~ ズーム開催
12:45 ズーム入室開始
13:00 開会の辞
会長挨拶
13:05 総会 ・役員紹介・活動報告・会計報告・会計監査報告
・行事計画・予算案・『書道文化』第18号発行について
13:20 講演
「デジタル化が生起させる感情経験—面白さの基底にある書体験の覚醒」
書家・書法史研究家、佛教大学・本学大学院非常勤講師 松宮 貴之 先生
13:00 開会の辞
会長挨拶
13:05 総会 ・役員紹介・活動報告・会計報告・会計監査報告
・行事計画・予算案・『書道文化』第18号発行について
13:20 講演
「デジタル化が生起させる感情経験—面白さの基底にある書体験の覚醒」
書家・書法史研究家、佛教大学・本学大学院非常勤講師 松宮 貴之 先生
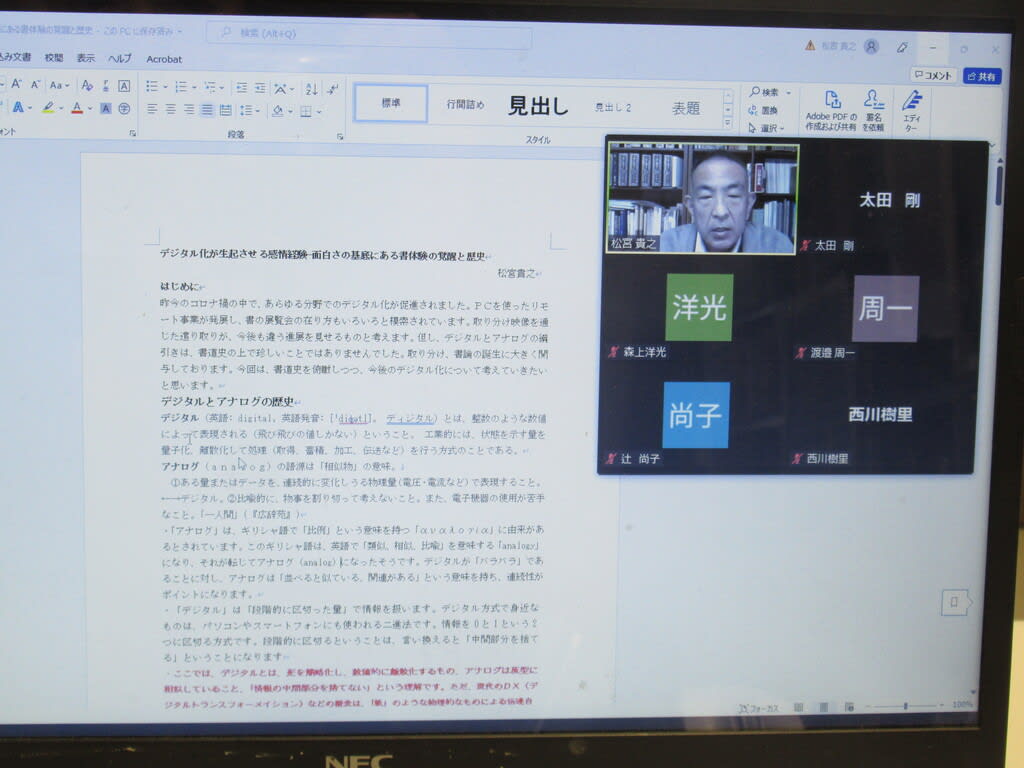
14:20 休憩
14:30 研究発表 「小島切における平仮名「の」の一考察」
本学講師 田ノ岡大雄先生

15:20 卒業生報告
「高校の書道教員として歩む今~生徒と向き合う日々、1年目に思うこと~」
第46期卒業 徳島県立城西高等学校教諭 香川百々花 先生

15:50 休憩
16:00 香港城市大学とのオンライン交流(通訳:渡邊浩樹)


16:35 閉会の辞
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港城市大学との交流は、こちらの挨拶は芳藍書道展の運営委員長の奥野駿介君がして、先方では4名の学生が各自の作品に関する研究発表をパワーポイントでしてくれましたが、すべて中国語でしたので、直後に渡邊君に発表概要を通訳してもらいました。海外の学生同士の交流は初めての経験だったので、外国語の壁を越えて内容理解させる方法に改善が必要なことがわかりました。もっと早く資料を送っていただき、翻訳したパワーポイントを提示する必要がありました。
今回の発表に対する学生たちの感想は、大学のmanabaコースというアプリで記入を依頼しています。Excelで簡単に集計できるので後に各講師にお送りする予定です。このような作業はPCの技術進化でかなりやりやすくなりました。
学会終了後は、交流プラザに移動し、作品搬出を1時間ほどしました。通常の年は交流プラザで学会をしたので終了後に大勢で片付けが出来ましたが、今回は運営委員の学生10名程度と教員2名で実施しました。けっこう疲労しました。
コロナ禍の中の新しい方法の芳藍書道展が終了しましたが、今後、香港城市大学へ送る作品の選定、発送後に香港での展示と再度のオンライン交流などに取り組む予定です。今度は四国大学の学生が自分の作品の内容を紹介することになります。





















































