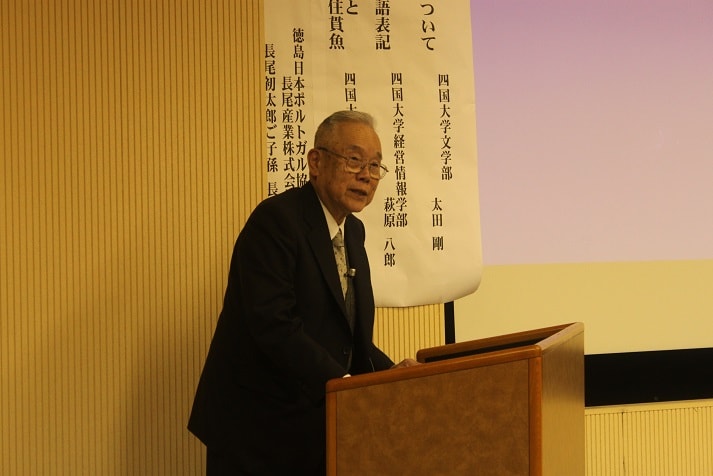3月29日(日)、ソメイヨシノが最盛期を迎えましたので、マルシェのあとに桜の名所の一つである佐古の諏訪神社に行きました。ここは数年前から気に入って行く場所の一つです。
長野県出身の私が故郷の地名がついていることに気になるのもここに行く一つの理由です。神社の由来看板によれば、ここに諏訪神社ができたのは、戦国時代末期のようですが、ここに来る前にも阿波の地には既に諏訪神社は勧請されていました。現在は諏訪神社は全国あちらこちらにありますが、多くの場合は信州出身の人がそれを移住先に勧請しているケースが多いです。諏訪神社は実は上社と下社の二社があって、信州では諏訪氏が諏訪上社を守り、ライバル関係にあった小笠原氏が諏訪下社を応援することになります。
阿波の場合は、承久の乱で中山道の将として活躍していた信州の小笠原長清が六波羅奉行として京都に赴任して阿波守護の佐々木氏を滅ぼし、その子である小笠原長経が新甫地頭として赴任しています。阿波小笠原氏は室町時代には細川氏の配下として阿波・讃岐に土着し、三好・一宮・安宅・大西・十河などの苗字を名乗ります。戦国時代に一時期全国を支配する三好長慶はこの末裔です。徳島県・香川県には小笠原氏は広く土着しました。江戸時代には小笠原氏は徳川氏の姻戚にもなって5家の大名を輩出し、転封も多かったので全国に広がって活躍します。江戸初期には蜂須賀至鎮(よししげ)が徳川家康の養女で小笠原秀政(信州飯田藩・松本藩の藩主)の娘である氏姫(万姫・お虎、敬台院)を娶ります。その御蔭で、蜂須賀氏は徳川氏から特別に目を掛けてもらいます。至鎮が若死にしてからも敬台院は長生きし、自分の息子や孫の藩主のために、江戸城内で側面から阿波藩を支えました。
このように小笠原氏の歴史は、日本歴史の裏を知るには非常に重要ですから一度下のサイトをご覧下さい。私たちが今、儀式に使っている「のし袋」の形式は元々は「小笠原流礼法」の一つで、小笠原氏が日本全国に広がらなければ、絶対に定着しなかったものの一つです。各地の大名配下には必ず「小笠原流礼法」の専門家の武士がいました。貫名菘翁の実家もこのような礼法を教える武家でした。小笠原諸島も、小笠原氏によって発見されたためです。「そごう」百貨店の創始者である「十合」氏も、讃岐小笠原氏の「十河」氏が大阪に移住してできた苗字だと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%B0%8F

面白いのは、この神社の紋です。二つの鎌を合わせた模様が使われていますが、それがヒモで結ばれています。鎌は農業を進めた鉄器の代表ですが、鉄の生産と諏訪神社というのは極めて密接だという説があります。長野県の山奥では、諏訪神の神域を表す場所には巨木の高いところに鎌が刺されているそうです。諏訪神社の紋について調べました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
諏訪神社には、梶紋と鎌紋という2つの神紋があります。梶はクワ科の落葉樹で、紙の原料にも用いられる植物です。古くから神聖な植物とされ、梶の皮の繊維でつくった布が神事に用いられるほか、葉自体もや神事でお供えものを感る食器の代わりに使われていました。また、諏訪神社には、鎌をかたどった神紋を用いているところもあります。鎌は古来、農耕の神様とされ、魔除けの力があるとして、神様への俸げものに用いられていました。諏訪大社は、平安時代の武人・坂上田村麻呂が蝦夷を平定する際、出陣の前に参拝していたことから、「日本第一大軍神」として武家の守護神とされました。源頼朝も諏訪神社を信仰していたといわれています。諏訪大社の分社である諏訪神社は、全国に1万社以上あり、主に武士の聞で信仰が広まりました。全国の諏訪神社の多くが梶や鎌の神紋を用い、諏訪信仰の武士の間に梶や鎌の家紋が広まりました。

この日は雨模様でしたが、桜は美しく咲いていました。
歴史を知りながら桜を見るのもいいものです。