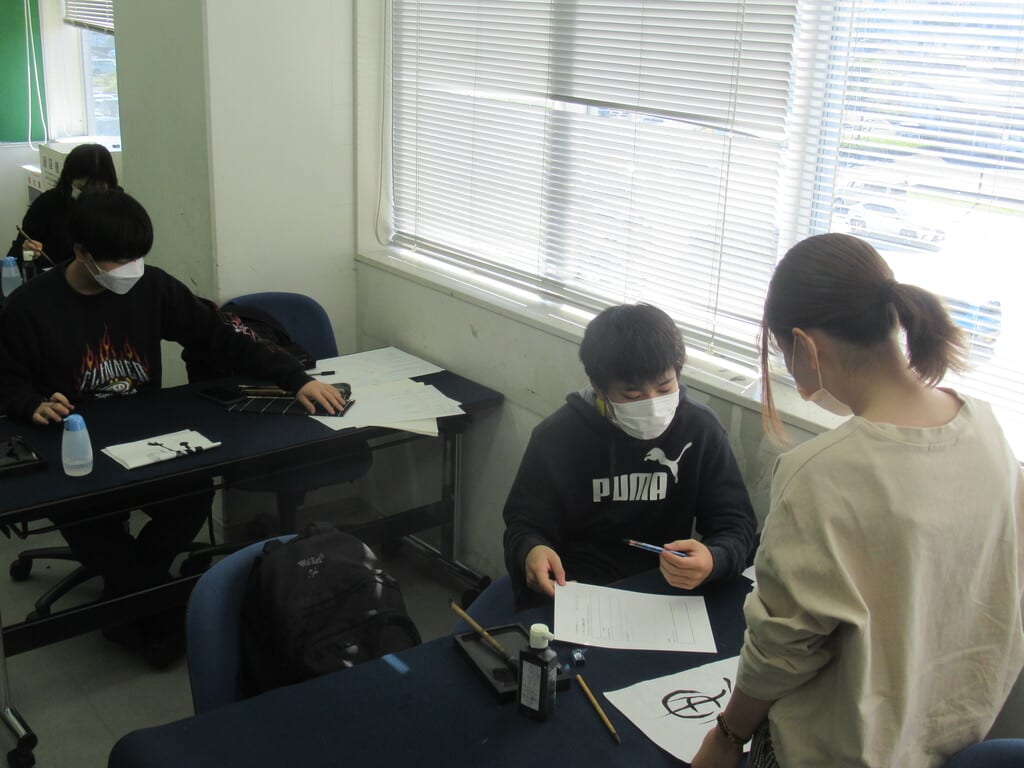10月26日(水)の夕方、書道文化館前の駐車場で、書道部の有志メンバー10名ほどが、11月13日(日)の芳藍祭で公開予定の書道パフォーマンスの練習をしていました。メンバーは全員1・2年生です。
普段は、書道文化館の1Fで練習していますが、本番が屋外である大学中庭で実施されるので、本番のためのリハーサルの段階に至っています。既に空は真っ暗になっていますので、ライトを2台用意して照らし、駐車場にブルーシートを敷き、熱心に取り組んでいました。



発表まであと2週間ほどになりますので、熱が入っています。最近の高校の書道部では、各学校の文化祭や地域のイベントで書道パフォーマンスをする機会が多いですから、指導者を目指す学生たちにとってもこの経験は重要です。自分たち自身が経験して、どんな点が難しいのかを体感しておくことが必須事項になります。
夕方になると、寒風も吹きだす季節ですので、彼らが風邪をひかないように祈りながらシャッターを切りました。