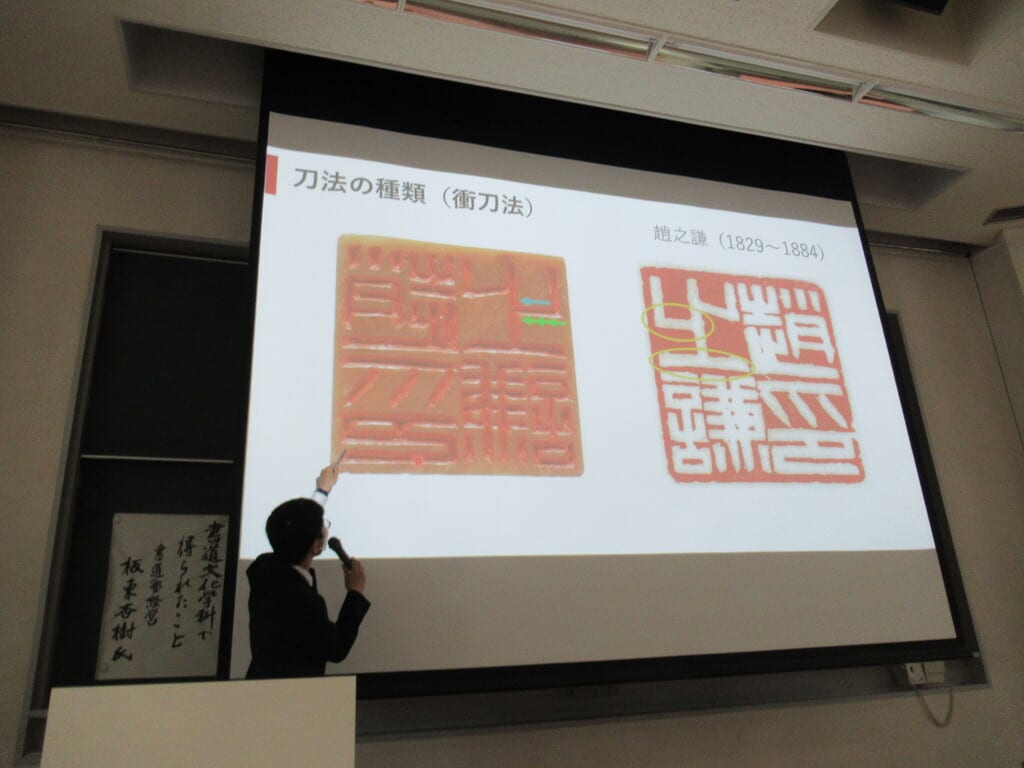5月15日(日)、14日にあった父の49日法要及び納骨で須坂市の実家に帰省し、終了後のこの日は長野市の善光寺に参拝しました。父の供養も兼ねています。

7年に一度の「前立本尊」の御開帳なので、大勢の参拝客であふれています。本来は昨年の実施だったのですが、コロナ禍で1年延期になり、しかも通常2カ月間なのですが、3カ月間に延長されています。6月末まで実施しているそうです。


有名な「鳩字の看板」です。この文字の中に使われている5つの点が鳩の形で「鳥書」の一種です。江戸時代末期の皇族によって書かれた書です。高い門の上にあるので小さく見えますが、畳3畳の大きさがあります。

参道脇にある小さな釈迦堂には涅槃像が祀られています。本堂を参拝したのちに、最後にここを参拝するのが習わしになっているそうです。

大本願内の建物の看板です。中根半嶺の揮毫です。

御開帳期間だけ臨時でお守りなどを販売する建物が建てられていて、そこに立派な看板がかかっていました。この建物内で、昔、中学校で教員をしていたころの教え子の一人が働いています。

宿坊の看板です。富岡鉄斎の揮毫の文字ですが、引首印に、雷神の肖生印が使われています。

二世中村蘭台の篆書の額です。

善光寺の敷地を出て、参道に行きました。小布施の栗菓子の有名店が向い合わせに店を開いており、それぞれ見事な看板です。竹風堂の書は、姫路出身の僧侶である清水公照の書です。彼は華厳宗管長で東大寺別当まで上りましたが、書は抜群に上手です。

風味堂の隷書の看板も味があります。

善光寺の周辺の看板は本当に美しいです。

近辺は昔の雰囲気を残しながら、観光的に再開発されて、お洒落な街になっています。看板もそのアイテムの一つとしてうまく活用されています。