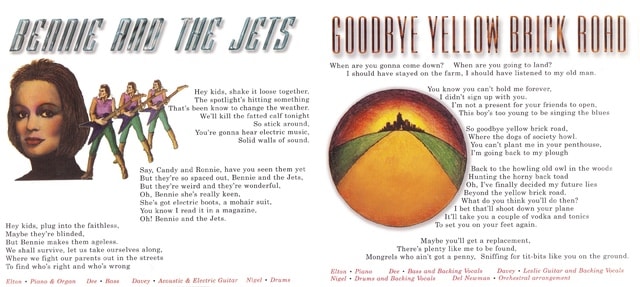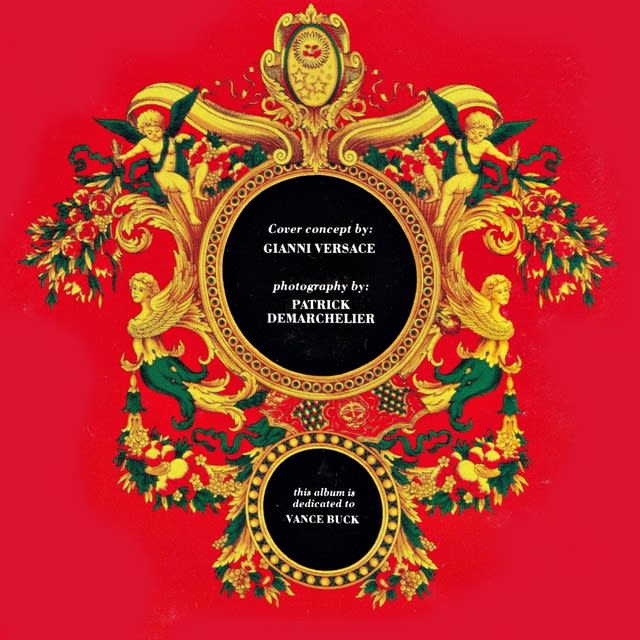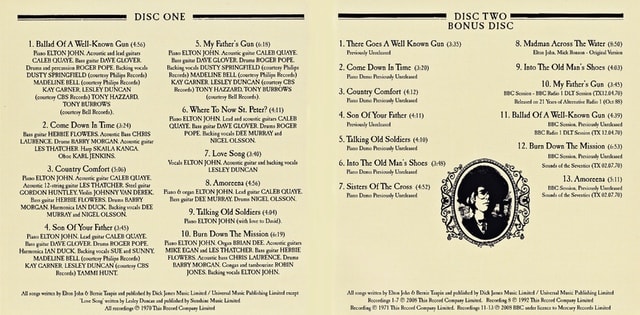エルトン・ジョンはアルバム、A Single Manを前作、Blue Movesから2年後の1978年に彼のロケット・レーベル第2弾として久々に出すことに。


バンド・メンバーもギターのデイビー・ジョンストンとパーカションのレイ・クーパーを除いて全員入れ替え。
更にそれまでエルトンのほとんどの曲の詩を書いてきたバーニーの代わりに、ゲイリー・オズボーンと組むことに。ゲイリーといえばヴィグラスとオズボーンと言うデュオ・グループで活動し1972年に彼らのアルバムからシングル・カットされた”秋はひとりぼっち”が日本でもヒットしたので覚えている人もいるだろう。この曲はForever Autumと言うタイトルでムーディー・ブルースのジャスティン・ヘイワードがカバーしている。
アルバムはそれまでと比べると少々地味と取られたのか、全盛期のアルバムの初登場1位と比べると物足りないかもしれないが、それでも全英/全米のチャートでそれぞれ8/15位と健闘したと思う。
肝心の中身もじっくり聴けばその良さがわかる。
どのような経緯でバーニーとのコンビを解消したのか定かではないが、アルバム・タイトルの如くSingle Manとしてエルトンは新たなる航海へと旅立ったのであった。

あれ? 船じゃなくて車で行くの?