久しぶりに訪れた「蓑虫庵」。
といっても最近、4/8に「 」(写真アリ)は、外(駐車場側)から見せていただきました。
」(写真アリ)は、外(駐車場側)から見せていただきました。
もっと前は、
「蓑虫庵のもみじ」(2020/11/19 過去ログ)
う~んと昔の2007/10/7(平成19年デス)には、、、
「蓑虫庵/灯りと座の世界」という催しがあったことを思い出しました。
遠い思い出ですが、とても風情があって、
足元を照らす行灯の淡い光に癒され、尺八の音色に耳を傾けつつ、
芭蕉さんの俳句仲間たちの集いの場に居るんだなぁと、感慨深かったものです。
さて、江戸時代の俳諧のことを紐解くにはワタシには難しいので、
世の中から切り離されたような静けさの残る「庵(いおり)」がここにある、
残されているということに改めて喜びを感じました。
「庵の庭」は自然豊かで多くの草木や花に、四季折々触れることができます。
俳句のたしなみはないけれど、緑豊かな場所にいると心落ち着きます。
そんな「庵の庭」…
「古池」と「古池塚」



古池の左のツルツルの木は「百日紅」、
≪「古池や 蛙飛ひこむ 水乃音 はせを」句碑
この句は貞享3年(1686)春、江戸深川の『芭蕉庵』での作。
芭蕉の代表作。碑に蕉風開眼をあらわす円窓をうがち、
躍動する蛙を浮き彫りにしています。≫(蓑虫庵案内より)
またこの句碑は江戸深川にあったものを移しています。
「史蹟蓑虫庵の東門、元の正門」

現在、外から見た「東門」、新緑が綺麗です。


この門を見て左奥に「駐車場」があります。
「服部土芳供養墓」
≪昭和4年(1929)1月18日の土芳二百年忌に際して、
河東碧梧桐(カワヒガシ ヘキゴトウ)が揮毫して、菩提寺の西蓮寺に建立された供養墓。
昭和13年(1938)に蓑虫庵へ移される。≫


彫られている字体は「六朝楷書」といわれるものだそうです。
「芭蕉堂内部」(全体は撮ってません)


≪真ん中に芭蕉翁像を安置、脇侍に土芳の位牌を祀る。≫
≪昭和5年(1930)12月に、大津市の義仲寺芭蕉堂にならって、
庵の保有者 菊本碧山 が建立。≫

「芭蕉堂」の傍らに「ユズリハ(譲り葉)」。
縁起の良い木とされ、新しい葉が開いてから古い葉が落ちることからこの名がついたそうです。
庭の奥の方に「水琴窟」、管理棟から見た「庭園」


水の音、耳を澄ませば聞こえます…
座っているだけで心落ち着くいいところです。
「服部土芳業績のまとめ」など

管理棟に置かれていた「蓑虫庵 花ごよみ」

この「庵」のことを研修する場を設けていただきましたが、
多くの石碑であれ歴史であれ、学ぶことは多くて奥が深い。
勉強は始まったばかりですが、
ココに通って四季折々の自然を眺めていたいと…
昔いただいた「蓑虫庵 花の歳時記」を眺めることといたします…

 春・夏
春・夏

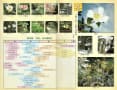 秋・冬
秋・冬
 野の草に 谷間の花に 杖とめて
野の草に 谷間の花に 杖とめて
「自然」を探り 詩に生きる あゝ芭蕉さん
ではまた
といっても最近、4/8に「
 」(写真アリ)は、外(駐車場側)から見せていただきました。
」(写真アリ)は、外(駐車場側)から見せていただきました。もっと前は、
「蓑虫庵のもみじ」(2020/11/19 過去ログ)
う~んと昔の2007/10/7(平成19年デス)には、、、
「蓑虫庵/灯りと座の世界」という催しがあったことを思い出しました。
遠い思い出ですが、とても風情があって、
足元を照らす行灯の淡い光に癒され、尺八の音色に耳を傾けつつ、
芭蕉さんの俳句仲間たちの集いの場に居るんだなぁと、感慨深かったものです。
さて、江戸時代の俳諧のことを紐解くにはワタシには難しいので、
世の中から切り離されたような静けさの残る「庵(いおり)」がここにある、
残されているということに改めて喜びを感じました。
「庵の庭」は自然豊かで多くの草木や花に、四季折々触れることができます。
俳句のたしなみはないけれど、緑豊かな場所にいると心落ち着きます。
そんな「庵の庭」…
「古池」と「古池塚」



古池の左のツルツルの木は「百日紅」、
≪「古池や 蛙飛ひこむ 水乃音 はせを」句碑
この句は貞享3年(1686)春、江戸深川の『芭蕉庵』での作。
芭蕉の代表作。碑に蕉風開眼をあらわす円窓をうがち、
躍動する蛙を浮き彫りにしています。≫(蓑虫庵案内より)
またこの句碑は江戸深川にあったものを移しています。
「史蹟蓑虫庵の東門、元の正門」

現在、外から見た「東門」、新緑が綺麗です。


この門を見て左奥に「駐車場」があります。
「服部土芳供養墓」
≪昭和4年(1929)1月18日の土芳二百年忌に際して、
河東碧梧桐(カワヒガシ ヘキゴトウ)が揮毫して、菩提寺の西蓮寺に建立された供養墓。
昭和13年(1938)に蓑虫庵へ移される。≫


彫られている字体は「六朝楷書」といわれるものだそうです。
「芭蕉堂内部」(全体は撮ってません)


≪真ん中に芭蕉翁像を安置、脇侍に土芳の位牌を祀る。≫
≪昭和5年(1930)12月に、大津市の義仲寺芭蕉堂にならって、
庵の保有者 菊本碧山 が建立。≫

「芭蕉堂」の傍らに「ユズリハ(譲り葉)」。
縁起の良い木とされ、新しい葉が開いてから古い葉が落ちることからこの名がついたそうです。
庭の奥の方に「水琴窟」、管理棟から見た「庭園」


水の音、耳を澄ませば聞こえます…
座っているだけで心落ち着くいいところです。
「服部土芳業績のまとめ」など

管理棟に置かれていた「蓑虫庵 花ごよみ」

この「庵」のことを研修する場を設けていただきましたが、
多くの石碑であれ歴史であれ、学ぶことは多くて奥が深い。
勉強は始まったばかりですが、
ココに通って四季折々の自然を眺めていたいと…

昔いただいた「蓑虫庵 花の歳時記」を眺めることといたします…

 春・夏
春・夏
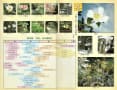 秋・冬
秋・冬 野の草に 谷間の花に 杖とめて
野の草に 谷間の花に 杖とめて 「自然」を探り 詩に生きる あゝ芭蕉さん

ではまた




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます