青空のぞき、雪残る丸山城址の碑を見上げつつ周りを見渡す。

2023年現在、樹木が生い茂り視界はあまりよくないのですが、
440余年前に思いを馳せて、天守や石垣・櫓などがあったのか…と。
寿福寺にてお話を聞いているときに、
当時(中世の頃)の「丸山城想像図」を見せていただき、
※出典(戦国の城・中・目で見る築城と戦略の全貌・西国編/学研社1992年
著者/西ケ谷恭弘・イラスト/伊藤展安)
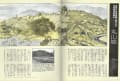
 (追記、後日古本ヲ購入シマシタ)
(追記、後日古本ヲ購入シマシタ)
また、家にあった「伊賀の中世城館」(伊賀中世城館調査会/会長:福井健二)の測量図を見ても、

これはなかなか素晴らしい城郭だったと…しかし、
当時、ここは伊賀の中心地、ここに織田方がこの城を建てかけた、
その様子を向かいの天童山無量寿福寺から見ていた伊賀衆たち。
「伊賀の中世の城館は、近世の城と違い、草深い山地に密かにたたずみ、
古くから合戦話や城にまつわる秘話とともに、身近に語り継がれている。」と、
福井健二先生が書かれているように、この伊賀の人間だからこそ、
しっかり見て聞いて紡いでいくことが大切な使命なのかもしれないと感じた次第です。
では、丸山城跡及び供養塔に別れを告げ、問題の下り道。


やはり下山はコワかった…生い茂る木々に残る雪。
低山とはいえ雪道・泥道・枯葉道は「横歩き、カニさん歩き」がベストと教えられ…
おかげで、誰一人コケることも滑ることもなく無事に麓に着きました。
比自岐川の支流の小さな小川沿いに「丸山駅」に向かいますが、
途中、ここにも登山口(二つ目)見つけました、
その先は「石の橋」、やっぱり雪はそのまま残っています。
石橋から見た「丸山城跡」の山(なんていう名前かなぁ?)。




ここで「忍びの里」の案内板、地図を確認すると

3本の登山口があります、ということは・・・
昔、「ここに案内碑があるけれど、この川をこの橋でわたるのか??」と、
撮った写真を引っ張り出しました (撮影日:2020/8/25)
(撮影日:2020/8/25)



登山口三つ目、北側です。
ワタシはこの橋を渡る勇気はなかったので パス。
パス。


私的に寄り道しましたが、無事にみなさん「丸山駅」到着、
天童山を背にした「雪だるま」。


再び伊賀鉄道で忍者市駅へ戻る、
車内で子どものように運転席の後ろでスマホ片手にはしゃいでいたのです(笑)。
最後に、一緒に参加した知人とのツーショット、


ご一緒していただいたdawnさんに撮ってもらった記念写真。
恥ずかしいけど、見てください。とてもいいミニ旅だったので。
主催してくださった「2023中世伊賀自治国再発見委員会」のみなさん、
ありがとございました。
そこで感じた風は、確かに「中世伊賀の冬の風」だった気がします。
ではまた。

2023年現在、樹木が生い茂り視界はあまりよくないのですが、
440余年前に思いを馳せて、天守や石垣・櫓などがあったのか…と。
寿福寺にてお話を聞いているときに、
当時(中世の頃)の「丸山城想像図」を見せていただき、
※出典(戦国の城・中・目で見る築城と戦略の全貌・西国編/学研社1992年
著者/西ケ谷恭弘・イラスト/伊藤展安)
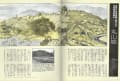
 (追記、後日古本ヲ購入シマシタ)
(追記、後日古本ヲ購入シマシタ)また、家にあった「伊賀の中世城館」(伊賀中世城館調査会/会長:福井健二)の測量図を見ても、

これはなかなか素晴らしい城郭だったと…しかし、
当時、ここは伊賀の中心地、ここに織田方がこの城を建てかけた、
その様子を向かいの天童山無量寿福寺から見ていた伊賀衆たち。
「伊賀の中世の城館は、近世の城と違い、草深い山地に密かにたたずみ、
古くから合戦話や城にまつわる秘話とともに、身近に語り継がれている。」と、
福井健二先生が書かれているように、この伊賀の人間だからこそ、
しっかり見て聞いて紡いでいくことが大切な使命なのかもしれないと感じた次第です。
では、丸山城跡及び供養塔に別れを告げ、問題の下り道。


やはり下山はコワかった…生い茂る木々に残る雪。
低山とはいえ雪道・泥道・枯葉道は「横歩き、カニさん歩き」がベストと教えられ…
おかげで、誰一人コケることも滑ることもなく無事に麓に着きました。
比自岐川の支流の小さな小川沿いに「丸山駅」に向かいますが、
途中、ここにも登山口(二つ目)見つけました、
その先は「石の橋」、やっぱり雪はそのまま残っています。
石橋から見た「丸山城跡」の山(なんていう名前かなぁ?)。




ここで「忍びの里」の案内板、地図を確認すると

3本の登山口があります、ということは・・・
昔、「ここに案内碑があるけれど、この川をこの橋でわたるのか??」と、
撮った写真を引っ張り出しました
 (撮影日:2020/8/25)
(撮影日:2020/8/25)


登山口三つ目、北側です。
ワタシはこの橋を渡る勇気はなかったので
 パス。
パス。

私的に寄り道しましたが、無事にみなさん「丸山駅」到着、
天童山を背にした「雪だるま」。


再び伊賀鉄道で忍者市駅へ戻る、
車内で子どものように運転席の後ろでスマホ片手にはしゃいでいたのです(笑)。
最後に、一緒に参加した知人とのツーショット、


ご一緒していただいたdawnさんに撮ってもらった記念写真。
恥ずかしいけど、見てください。とてもいいミニ旅だったので。
主催してくださった「2023中世伊賀自治国再発見委員会」のみなさん、
ありがとございました。
そこで感じた風は、確かに「中世伊賀の冬の風」だった気がします。
ではまた。


































 、そして温まったところで本堂へ移動。
、そして温まったところで本堂へ移動。

































 ということを再確認。
ということを再確認。











