
ハビアー・ブラス、ジャック・ファーキー著、日本経済新聞出版刊
「コモディティー」という言葉は、文脈によって異なる意味をもちますが、本書のタイトルの「コモディティー」の意味するところは、下記リンクによれば「原油やガソリンなどのエネルギー、金やプラチナなどの貴金属、トウモロコシや大豆などの穀物といったような商品」を指すようです。
本書が扱っているのは、銅などの金属、燃料の石炭や石油など、小麦などの穀物類などです。
また、本書で登場する「商社」は、日本人が想像する総合商社ではなく、上記のコモディティーの一つや複数の商品に特化しています。
これらの商品が世界でどのように売買されるかについての知識を殆ど持たず、本書が対象とする「商社」の様な存在を知らなかったので、本書で語られる「商社」の『冒険(adventure)』の足跡を辿る旅は圧巻でした。
彼らは正しくリスクテイカーというべき人々で、資金回収が不確か、紛争や戦争の渦中で危険性が高い、交渉ルートが定かではないなど、何らかの事情で先進国が取引を規制しているなど、ありとあらゆる困難が待ち受けている中に飛び込んで、安く買い高く売るのです。
そのような危険に飛び込む人々はタフであることは当然として、根本的な動機は「人がやりたがらない、人が行きたくない所に富が存在する」ということなのでしょう。
彼らの存在や活動は、長らく日の目を見ることなく、法令や条例、あるいは取り決めに違反することも辞さず暗躍してきましたが、近年になり、次第に活動実態が明らかになり、世界から非難されるようになった。また、彼らの独自の情報取得は極めて重要であったが、情報通信技術の進展で、優位がかなり損なわれたそうです。
しかし、コロナパンデミックの際に、ロックダウンなどで世界の石油消費量が激減し、価格が暴落しマイナスの値段が付いた時に、これらの商社が一斉に買いに走り、巨大タンカーに貯蔵したことにより需要が維持され、石油生産を続けなければならなかった石油業界が壊滅を逃れ、その後の需要回復期に、速やかに供給できた事例が挙げられています。
時代と状況が変わり、昔のようなアクドイ手法がとれなくなっても、可能な方法で「商社」は活動して利益を得ながら世界に貢献できる、ということが本書の結論です。
本書は、「商社」の年代記とも言うべき著作で、著者達の専門分野に関する取材結果が高密度で詰まっており、最後まで緊張感を以て読むことが出来ました。
知らない世界が本の扉の向こうに存在することを再確認できた良書でした。
--------------------
○コモディティー
--------------------
評価は4です。
※壁紙専用の別ブログを公開しています。
〇カメラまかせ 成り行きまかせ 〇カメラまかせ 成り行きまかせその2














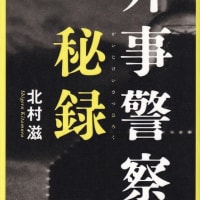











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます