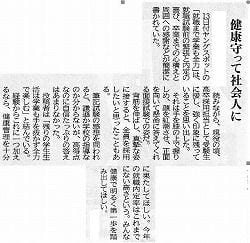門徒という言葉は「宗門を同じくする信徒のことだが、特に浄土真宗の信者」とある。そんな信者として1年には春季彼岸会、親鸞聖人降誕会、永代経法要、盂蘭盆会、秋季彼岸会、親鸞聖人報恩講など数回、本堂に集う機会がある。出来るだけ山門をくぐるようにはしているが全てにお参りできないでいる。ここ数年、本堂という特定の場所柄かもしれないが、信徒の姿に高齢化の波が世間一般より早いと感じている。
12月は恒例の「親鸞聖人報恩講」が開かれる。これは「親鸞聖人のご命日を縁に宗祖の遺徳を偲ぶ集い」で3日間続く。正装の住職に合わせ「正信偈」「五十六億和讃」を勤行集を繰りながら読経する。数十人を超す信徒の声が一つになるとその重みが伝わるといつもそう感じる。法話は日々の生活のなかの小事も宗祖の教えの中にあると説く。
人の背中が見え始めたら考えようという趣旨の話が印象に残った。今まで顔を見て話していた人が背を向けて遠ざかるようになったら、自己のふるまいを顧みろというシグナルだという。相手が背を向けるのは相手にされなくなった、関心を示さない無関心な態度になる。世間に背を向ける、と人様の行状は口にするが、我が身がいつそうなるかも知れぬ。
集いに参加すると、お昼は仏教婦人会の皆さんが作られるお斎をいただく。季節に見合った料理は健康への原点を思い至らせる精進、時節柄、地産のレンコンと人参のさんばい、勿論酢魚はなし。終戦のころ野菜づくしでも満腹した食卓を思い出す。今年は除夜会で鐘を撞き善哉をいただく会が残っている。鐘のにぶい音とゆったりした振動は冷えた体に活をくれ年明けとなる。