平成二十六年度四月二十二日
聖霊会舞楽大法要次第 「道行」
総本山 四天王寺
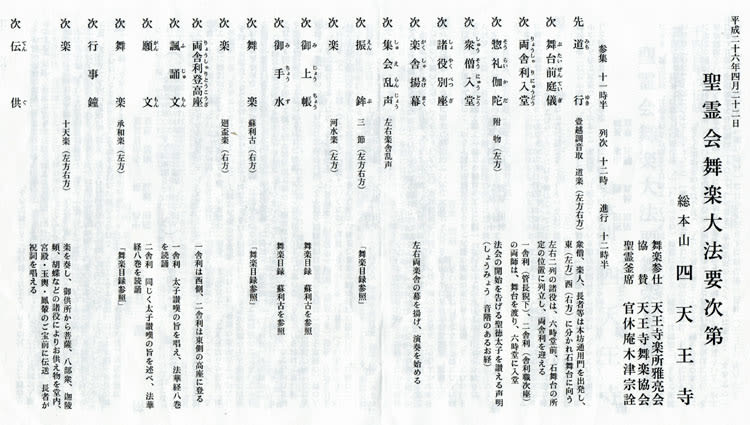

四月二十二日曇り
正午12時半から夕刻5時半までの五時間、四天王寺の聖霊会の神事や舞楽や雅楽を拝見させて頂きました。
四天王寺さんで聖霊会を見るのは二度目です。
一度目は雨天のため石舞台の上では演じられませんでした。
今年は願望の石舞台上の舞楽を楽しませて頂く事ができ、感無量です。
五時間の間じっと座り続け、終演の頃には足がしびれていました^^
気持ちの晴れやかになり、楽しい時間を過ごす事ができました。
この満足感が太平楽(曲)のようにいつまでも続いてくれればいいなと感じます。
とりあえず、道行の部分をUPしようと思います
見て下さいますれば嬉しいです。









諷誦文(ふじゅもん)を大切にお持ちになっておられます。
 【諷誦文】(ふじゅもん)とは (ウェブ辞書)
【諷誦文】(ふじゅもん)とは (ウェブ辞書)〘仏〙 仏事で死者の追善のために布施物を三宝に供えて読み上げる文。
古くは施主が作り導師に読ませたが,のちには導師などが作るようになった。
【諷誦文】(ふじゅもん)とは (ウェブ辞書)
仏教儀礼として諷誦を行うために出す文書。
ふじゅもん 【諷誦文】とは (ウェブ辞書)
仏教で諷誦は節をつけて経文を暗誦することだが、今は法要に趣意文を読むことをいい、その文をいう。
もとは葬儀や追善供養の際、施主が僧に諷誦を願って施主自らが読んだもの。→ 諷経
【諷経】ふぎん とは goo辞書
《「ぎん(経)」は唐音》声をそろえて経を読みあげること。
禅宗では、仏前での勤行(ごんぎょう)をいう。⇔看経(かんきん)。
【看経】 かんきん とは goo辞書
[名](スル)《「きん(経)」は唐音》
1 禅宗などで、声を出さないで経文を読むこと。⇔諷経(ふぎん)。
2 声を出して経文を読むこと。読経。
↓
【諷誦文】(ふじゅもん) (いた最多演目表より)
一舎利 太子賛嘆の旨を唱え、法華経八巻を読誦
全てがおわる頃には四天(四天王寺学園)の中高生が出てこられました。
皆さん嬉々とした表情で楽しそうでした。
彼女たちに出会い、四天王寺の境内を歩き、大変懐かしい思いが致しました☆
やっぱり、四天王寺も好き^^vと当然の事ながら、改めて感じました。
つづく

















 まぁ!懐かしい☆堀高(堀川高校)の近く…
まぁ!懐かしい☆堀高(堀川高校)の近く…





















